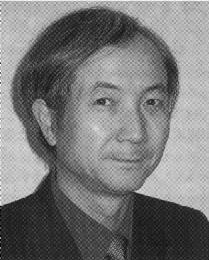
���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.15 No.1 February 2003
�ޗ��Z�p�����{���~��
�L���m���ޗ��Z�p�����������@�@�� �� �[ ��
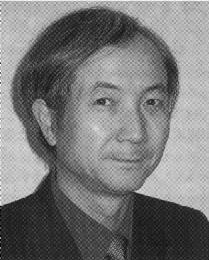
�͂��߂�
�@1990�N�Ƀo�u�����͂����Ė����ɓ��{�o�ς̍s����͌����Ȃ��B���i�̐������������͂��߂Ƃ���A�W�A�Ɉړ����āA�����̐����̋����n�܂��āA���̂Â�������ƌ|�Ƃ��Ă������{�̎Y�Ƃ����C���Ȃ��B
�@���̂悤�ȏ��ɂ����čK���ɓ��Ђ͉��Ƃ��Ɛт��ێ����Ă���B�����͂̂���A�Ǝ����̂��镡�ʋ@�A���[�U�[�r�[���v�����^�[�A�C���N�W�F�b�g�v�����^�[�Ȃǂ̏��i�𐢂̒��ɋ������ڋq�Ɏg���Ē������Ƃ��o���Ă���B�����͂̂��邱���̍��ʉ����ꂽ���i��n��o���ɂ͗Ⴆ�Ε��ʋ@�A�v�����^�[�Ƃ������n�[�h�ƍޗ�����̂ƂȂ����Z�p�J�����K�{�ł���A���Ƀg�i�[�A�C���N�ɑ�\�������Օi�Ƃ��Ă̍ޗ��Z�p���傫����^���Ă���B���Ђł͐V���Ƃւ̎Q�����邢�́A�V���i�����鎞�̋Z�p�̕]�����ڂƂ��āA�Ǝ����A�ޗ��ł̍��ʉ��̃��x���A�R�X�g�A�����̗D�ʐ�����]�����邱�Ƃ������Ƃ��Ă���B
�@���ł��A�d�v���ڂƂ��āA�ޗ��ł̍��ʉ��������͂̊m�ۂ̂��߂ɂ͕K�{�ł���ƍl���Ă���B�����̊�Ƃ̋����͂����コ���A�s���̓��{���~�����߂ɍ��ʉ����ꂽ�ޗ��Z�p�������J�����邱�Ƃ̏d�v���ɂ��ďq�ׂĂ݂����B
�ޗ��Z�p�ɂ�鍷�ʉ�
�@���ɁA�f�t�����ɂ����ċ����͂����コ���邽�߂ɂ͐����R�X�g�̒ጸ���K�v�ł���B��Ƃ��ē��{�̊�Ƃ͂������Ē����A�A�W�A�̊e���֍H�����萶�Y���V�t�g�����Ă���B���̂��ߓ��{�����ł̐��Y�䗦���ɒ[�ɒቺ���H��������ꎸ�Ǝ҂��������Ă���A�f�t���ւ̈��z�̈���ɂȂ��Ă���B���i�Ƃ��Ă̋����͂̌��オ�R�X�g�݂̂ɋ��߂��鏤�i�ɂ͂��̌X���������Ȃ�A�Ǝ��̋Z�p�����荞�܂�Ă��鏤�i�ɂ͂��̌X�����キ�Ȃ�B���{�̗D�ʂȋZ�p�Ǝv���Ă����g���̂Â���h�̋Z�p�����ł͑傫�ȍ��ʉ��ɐ����Ȃ��Ă���B
�@�i�m�X�P�[���̒������ȉ��H��v����t�����l�̍����Z�p�荞���i�ł���A�����ł̐��Y�������Ɏn�߂���邱�Ƃ͂Ȃ����A�@�\���i�̑g�ݍ��킹�ō��x�ȋ@�\�����鐻�i�ł͊ȒP�ɓ��l�̋@�\����肾�����Ƃ��\�ł���B���ɍŋ߂̉Ɠd���i�AIT�֘A���i�ł́A�@�\�Ƃ��Ă͍��x�ł����i�̑g�ݍ��킹�Ŋ��ƊȒP�ɐ������邱�Ƃ��o����B
�@���ɁA�����Ŏ��ꂽ�Z�p�ɂ��D�ʐ��̊m�ۂ��d�v�ł���B���Ƀu���b�N�{�b�N�X�Ƃ��ėD�ꂽ�ޗ��Z�p����������ċ@�\�����Ă��鐻�i�́A�ȒP�ɉ�͂��^�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�]���̓n�[�h�ƃ\�t�g�Ƃ��̋@�\�ɏd�_���u����č��ʉ����v���Ă������A���܂łɑ����čޗ��Z�p�ł̍��ʉ������{�̗D�ʂ����߂ɕK�v�ł���B���������āA�R�X�g���ł��A�t�����l�̍����ŗD�ʐ����m�ۂł������ł̐��Y�̉��l�������i�̋����̂��߂ɁA���ɂ͐^���ł��Ȃ����ʉ����ꂽ�ޗ��Z�p�������J�����邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@���ɁA�d�q�f�o�C�X�ޗ��A�\���f�q�ޗ��A���@�\�V�K�ޗ��A���Ή��ޗ��A�f�f��Íޗ��A�o�C�I�֘A�ޗ��A�i�m�\���ޗ��ȂǁA3�N�`5�N����������������J�����ɂ߂ďd�v�ł���B
�ޗ��Z�p����
�@�傫�Ȏw���͂̉��ɁA���Ƃ��Ă̂���ׂ������ւ̖��ƕ�������`���A�r�W�����Ƃ���搂�������K�v������B
�@�Ⴆ�A�č��ł̉ߋ��̗�Ƃ��Ă̓A�|���v��A���n�C�E�F�[�Ȃǂ�����B��w�����̎g���Ƃ��Ă̓V�[�Y�u���̌����݂̂Ȃ炸�A���̏����̋Z�p�Ƃ��āA�����Љ�ɁA�l�X�ɂƂ��ĕK�v�����\���ɋc�_���A�F�����A���悻�̕�������n�肾���ӔC������B���ꂩ��̎���̕������Ƃ��ẮA���q�E�����A�n�����̕ی�A���K�Ȗ��Ƃ�Ƃ肠�鐶���Ȃǂ�����B��������������Z�p�ۑ�Ƃ��ẮA�Ȏ����A������G�l���M�[�A���N��ÁA�N�ł��g����IT�Ȃǂ̊�b�Z�p����������B�����āA��b�����Ƃ��Ă̑�w�A�Ɨ��s���@�l�̌������Ɖ��p�����Ƃ��Ă̊�ƌ������̘A�g�������K�v�ł���B
�@���{�݂̂Ȃ炸���E�̊�Ƃ̒�������������V�K�ȑ�^�̋Z�p�����ݏo����Ȃ��Ȃ��ċv�����B�T�C�G���X�̉����Ƃ��Ă̋Z�p�n�o�̏�ƁA�s��̃j�[�Y�֒����������i�J���̏ꂪ�A�d�Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ����̗��R�Ƃ��čl������B��Ƃɂ����Ă��A�����I�Ȏ��Ɛ��i���s�����߂ɂ͕��Ɖ��̐��i���K�v�ł��邪�A���̌��ʁA��������̖ڕW�ƁA���ƕ���̖ڕW�Ƃ��d�Ȃ肠��Ȃ��Ȃ��ė��Ă���B���������āA��Ƃɂ����Ă͊�b��������J���܂őS�̍œK�Ƀ}�l�[�W�����g����V�X�e�����čl�����ׂ��ł���B���̂��߂ɂ͊�ƌ����J���ł̈�т����ϊv���K�v�ł���B���̂��߂ɂ͈ȉ��ɏq�ׂ�n���I�Ȑl�ނ̈琬���d�v�ۑ�ƂȂ낤�B
�n��������ޗ��Z�p�������s���l�ނ̈琬
�@�o�ς̐����A��Ƃ̐����A���W�ɂƂ��ăC�m�x�[�V���������������K�v�ł���B�C�m�x�[�V�����𒆐S�I�Ɍ�������n�����L���Ȑl�ނ��K�v�ł���B�n�����L���Ȑl�ނ�g�D�̒��ŏ��Ɉ琬���������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ������ɔ��W�����Ă������߂ɂ͊m���Ō����I�ȉ^�c�Ɛ��i���K�v�ƂȂ�B
�@�������Ȃ���C�m�x�[�V���������������̒i�K�ɂ����ẮA�s�m���Ő�̌����Ȃ��A�����Ɋ�Â����A�^�c�Ɛ��i���K�v�ɂȂ�B�n���I�Ȋ����͂��̂悤�ȁA���ŏ��߂ĊJ�n�ł���B�������A�����ő傫�Ȗ��������݂���B�����Ȏ��Ƃ̉^�c�ƃC�m�x�[�V�����̑n���Ƃ͑��e��Ȃ������������Ƃ������ł���B���Ȃ킿�C�m�x�[�V�����Ƃ͖����ɖ����������ł���B���̂悤�Ȗ����ɖ�������̊������ɑg�D�I�ɍs��Ȃ���Ί�Ƃɂ�����C�m�x�[�V�����͐��܂�ɂ����̂ł���B
�@�d�v�Ȃ��Ƃ́A���̑n���̏����ނ��Ƃ��ł���r�W�����Ƃ���𗝉����Ă���}�l�[�W���[�����݂���g�D�A�X�ɏ_��ȉ��̍L���}�l�[�W�����g���K�v���Ƃ������Ƃł���B
���{�̍ޗ����[�J�[�A���w�H�ƂɊ��҂���
�@�ޗ����[�J�[����ޗ����������Ă��������A�V���i��n�����Ă�����X��ƂɂƂ��āA���{�̍ޗ��E���w���[�J�[�ɑ�����҂͑傫���B�ߋ��ɂ����Ă��D�ꂽ���{�̐��i����s������{�̌o�ς̔��W�ɑ傫�Ȋ�^�����Ă������Ƃ͕�������������ł���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߂̉��w�ƊE�̌��C�������C�ɂȂ��Ă���B�o�ς̏�����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�ޗ����[�J�[����̏����ւ̒�Ă����Ȃ��Ȃ��Ă���Ɗ�������B5�N�`10�N��ɐ��E�A�Љ�A������ω�������ł��낤�Z�p�Ƃ��̏��i�ɗp����ޗ������Ȃ��B3�N�A���̃m�[�x���܂Ɠ��ɓc������̎�܂́A��X��Ƃ̋Z�p���ɂƂ��Ă͗�݂ɂȂ邪�A���E�̃��x������݂�X�Ȃ��K�v�ł���B�i�m�e�N�m���W�[����̃J�[�{���W�͓��{���哱�������Ƃ������Ă��̕���͊����ł��邪�A���̑��̕���͈قȂ�B�ڋq�T�C�h�ɋ߂���X�n�[�h�W��Ƃ̌����J���͏����̕����������i�Ƃ��ĕ`���Ă��邪�A���{�̑����̍ޗ����[�J�[�ɂ͗��������Ă��������Ă��Ȃ��Ɗ�������B
�@��ɏq�ׂ��悤�ɁA�����������ɂ����Z�p�̑n���ɂ������ẮA�g�D�I�ȑΉ����ł��Ă��Ȃ����Ƃ������łȂ����ƍl������B���{�o�ς̍��{�I�ȉ��P�̂��߂̋Z�p���삩��̒��킪��w�ł̌����A�Ɨ��s���@�l�ł̌����A�ޗ����[�J�[�ł̌����ɑ�����Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�������ɂ��ꂩ��̍ޗ��W�҂̌䊈��Ƃ��̐��ʂ����҂��Ă���B
| �A����F��146 -8501 �����s��c�扺�ێq3 -30 -2�@�L���m���ޗ��Z�p������ �������ʁF03 -3757 -6120�@http://canon.jp/ |
��14����{MRS�w�p�V���|�W�E����
�w�p�V���|�W�E����抲���@�� �F �� �Y
�@���{MRS�P��̊w�p�V���|�W�E���͎�ɐ��s�a�̌�KSP�i���Ȃ���T�C�G���X�p�[�N�j�ŊJ�Â���Ă����B���̉��͕������Ɍ��肪���邽�߃Z�b�V�������𑝂₹�Ȃ��Ƃ�����肪�������B2003�N�ɂ�IUMRS-ICAM����{MRS��ÂŊJ�Â���\��ł���B���̂��߁A2002�N�w�p�V���|�W�E���͈ȑO���K�͂�傫�����邱�Ƃ��]�܂�A�����ʼn���s���̑�w�Ɉڂ����Ƃɂ����B����ɂ��Z�b�V����������ь������\���̑����ɑΉ��ł���Ɨ\�����A����14�N12��20���i��)�A21���i�y�j��2���ԁA�����H�Ƒ�w�剪�R�L�����p�X�ŊJ�Â��ꂽ�B�Z�b�V������15�A���\����582���A�Q���Ґ��͖�800���ł������B�ߋ����N�Ԃ̓��{MRS�w�p�V���|�W�E���Ɣ�ׂĂ������͑����A�e���ł͊����ȓ��_���s��ꂽ�B�Z�b�V�����ɂ���Ă͗���Ґ����N���Ɨ\�����Ă������߁A�������̐l���o���ƕ����Ă���B��ꂪ�s���ֈړ��������ƁA�����ăZ�b�V�������̑����Ȃǂ��S�̂������ɂ����v���ƍl������B���݊�悪�i��ł���2003�N10��IUMRS-ICAM�ɂ����Ă��A����ɑ����̔��\�҂�Q���҂��W�܂邱�Ƃ����҂��Ă���B
�@����܂͍��܂Ŏ�茤���҂̃|�X�^�[���\��ΏۂƂ��Ă������A����͌������\���ΏۂɐR�����s�����B�Ȃ��A��҂̊����͐R���Ώێ҂�10%���x�Ɖ������B����͏���܂̕]�����グ��l������ł���B��҂̈ꗗ�����Ɏ����B�����̎�҂ɂ͂��j����\���グ�����B
�@�Ō�ɁA���\�҂̕��X�A�R�����̕��X�A�`�F�A�̕��X�A���̑������̕��X�Ɋ��ӂ�\���グ��Ƌ��ɁA�S�����҂̍���̊���E���W�����҂������B
�������҈ꗗ
Session A�F�֓��ꔎ�i����)�A�É�q�V�i�Y����)�A���r��i�Ȋw�Z�p�U�����ƒc)�A�n�ӈ�j�i�s����)�A���T�q�i����)
Session B�F���@�O��i�}�g��)�A���@���āi�}�g��)�A�_�`�A���E�g�[�}�X�i�L���Z�ȑ�)�A��W����i���H��)
Session E�F�ё�����i�F�s�{��)�A�c������i��������)
Session F�F�R��ז��i���H��)�A�y�c�P�V�i���H��)�A�ђˍK�F�i�_�ˑ�)
Session G�F�R����q�i�R����)�A�{�ԋM���i�H�w�@��)�A���V�@��i��q��)
Session H�F���c�@���i�Ȋw�Z�p�U�����ƒc)�A���ёO�i�����ّ�)�A���茒��i���)
Session I�F���Ԕɖ��i�J�[�� �c�@�C�X)�A�����[���i���l����)
Session J�F�F�J�����q�i��q��)�A�Ð�֎j�i���)
Session K�F���c�����i�ޗǐ�[��)�A�A���~��i�O�䉻�w)
Session L�F�c���ǖ��i�x�R����)�A���엳���i��t��)�A���{���j�i���C��)
Session M�F�{�������i�w��)�A��F�����i�\�j�[�P�~�J��)�A�˓c�G�F�i�F�s�{��)�A�����a�L�i�w��)
Session N�F�؊w���i����)�A���R�h�Y�i��������)
Session O�FChuhyun Cho�i�����Z�ȑ�)�A�Y���i�i�c���)�A��@�L�S�i����)�A����䗝�����i��t�H��)
Session A�F���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\V
�Q���Ґ��F40��
���ҍu�������i3��)�A�������\�����i12��)�A�|�X�^�[���\�i41��)
�@�{�Z�b�V�����͍����5��ڂ��}�������A�N�X�u���ۂ̔����v����u�ޗ��ւ̓W�J�v���Ӑ}���������������Ă���B�Ƃ�킯����́A�L�@�n���疳�@�n�A���̌n�A�X�ɂ̓i�m���q�n�Ɏ���A�l�X�ȁu���ȑg�D���v�Ɋւ���������\�Ȃ�тɃ|�X�^�[���\���s��ꂽ�B�i�m�e�N�m���W�[�����̒��̒��ڂ��W�߁A���̒��S�I�������ʂ������̂Ƃ��āu���ȑg�D���i�{�g���A�b�v��@)�v�Ɋ��҂��W�܂��Ă��邱�Ƃ����̔w�i�ɂ�����̂ƍl����B3���̏��ҍu���́A�c��E�R�����̒����q�A����E���鎁�̃o�C�I�~�l�����[�[�V�����A�L���m���E�{�c���̖��@�i�m��ԍޗ��ƁA��������Ő�[�̃z�b�g�ȃg�s�b�N�X�Ɋւ�����̂ł������B
�@�^�c�Ɋւ��ẮA�t���v���W�F�N�^�[�̍u�����Z�b�V�����Ƃ��Ď��ꂽ�B����̗�����l����ƁA�u���̎嗬��OHP����t���v���W�F�N�^�[�Ɉڍs��������̂ƍl����B�c�O�Ȃ���A�R���s���[�^�[�Ƃ̐ڑ��̃g���u���������N���Ă��܂����B�ڑ��@���܂߂āA����̑K�v�ł���ƍl����B�܂�����̃`�F�A��abstract�����t�����d�g�݂́A���P����]�n������̂ł͂Ȃ����낤��?�@���\�\�����݂Ɠ��l�ɁA�z�[���y�[�W�ɒ��ڏ������ތ`�Ԃւ̕ύX����]�������B
�@�{�Z�b�V�����́A���N�x��IUMRS-ICAM2003�ɂ����Ă��A����E�֎����\�`�F�A�Ƃ��ĊJ�Â���\��ł���B�L�͂ȉ�������҂������B
�@�Ō�ɁA�����ǂ��͂��߁A�{�Z�b�V�����ɂ����͂������������ׂĂ̊F����ɂ��̏����Ďӈӂ�\���܂��B
�i��v�ےB��i������w��w�@))
Session B�F�X�}�[�g�}�e���A���E�X�g���N�`���[
�Q���Ґ��F120��
���ҍu�������i5��)�A�������\�����i46��)�A�|�X�^�[���\�i15��)
�@�{�Z�b�V�����ł́A�X�}�[�g�}�e���A���E�V�X�e���̌����E�J���E���p�Ɍg��錤���҂��ꓰ�ɉ�A�ޗ��̐����v���Z�X�A�����g�D����A�����]���A�O��i���́A����A�d��A�C�I���r�[���A���x���j�̌��ʁA�������A�V�X�e�������Ɋւ��錤�����\���s�����B���\���ꂽ�X�}�[�g�}�e���A���ɂ́A�s�G�]�f�q�A�`��L�������A�@�\�������ޗ��A�@�\���|���}�[�����������B
�@�u���̒��ŁA�Z���T�[�ƃA�N�`���G�[�^�̋@�\��L����X�}�[�g�}�e���A����g�ݍ��ނ��Ƃɂ��L�p�ȃX�}�[�g�V�X�e�����\�z�ł��邪�A21���I�ɋ��߂���T�O�Ƃ��ďȎ����A�ȃG�l���M�[�A�Z�p�̊Ȗ������L�[���[�h�ɂ����J���̕��������d�v�ł���Ǝw�E���ꂽ�B�e�@�\�v�f�͒P���ł��邪�A�V�X�e�����\�z���邽�߂̊�{�@�\�ɉ����Ĉ��S���̊m�ۂ̂��߂̋@�\���t������Ƃ����悤�ɁA�����̋@�\�G�ɗ��߂Ă����ƃV�X�e���͕��G�ɂȂ肪���ł���B�Ȏ����A�ȃG�l���M�[�A�Z�p�̊Ȗ�������͗��������ł���A�Љ�ɗL�p�ȋZ�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�L�p�ȃX�}�[�g�V�X�e���̍\�z�̂��߂ɔ��z�̓]�����s���ł���Ƃ��������[�������ł���B�X�}�[�g�}�e���A���E�V�X�e���̌����ɂ́A�f�ގ��g�̊J���̑��ɕ������ƃV�X�e�������s���Ď��p����i�߂邱�Ƃ��܂܂�邽�߁A��b����������p�����܂ł̍L���͈͂ŁA�����̌����҂�����������̒������Ԃ̌����E�J�����v�������B�����̎Y�Ɗ�Ղ̍\�z�ɕs���̂��̂Ƃ��āA�X�}�[�g�}�e���A���E�V�X�e���̊J���𑨂炦�Ă����K�v������B
�@�{�Z�b�V�����́A�����MRS-J�w�p�V���|�W�E���̒��ōł��u�����̑����Z�b�V�����ł������B��u���A���ҍu�������ꂽ���j�I�����҂ɉ����āA��������у|�X�^�[���\�҂͎��A�����̌����҂������A���̕��삪�����Ɍ����Ĕ��W���čs�����Ƃ�\�������镵�͋C���������B
�i�{��C��i�}�g��w))
Session C�F����ɂ��\���A�g�D�A�@�\����
�Q���Ґ��F50��
���ҍu�������i5��)�A�������\�����i22��)�A�|�X�^�[���\�i0��)
�@����𗘗p�����l�X�ȍ\���A�g�D�A�@�\����ɂ��Ĕ��\���s��ꂽ�B�ΏۂƂ���ޗ��͋����A�Z���~�b�N�X�A�����q�A���̍זE�܂ŋɂ߂čL�͂ɂ킽��B����𗘗p���Ă��錤���҂͑������A����قǑ���ɂ킽��ޗ��Ɋւ��Ĉꓰ�ɉ�Ĕ��\���s�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��������߁A�ٕ���̌����ғ��m�̌𗬂��\�ƂȂ�M�d�ȋ@��ł������BMRS-J�̓��������܂����������Ǝv����B�܂��A�ΏۂƂ���ޗ����قȂ��Ă���������鎥����ʋy�т��̃��J�j�Y���Ɋւ��Ă͎Q�l�ɂȂ邱�Ƃ������A�V���Ȋϓ_����̎��ꉞ�p�̃q���g������ꂽ�B5���̏��ҍu���͎�Ƃ��Ď��ꒆ���ϑԂ𗘗p�����������\�ł������B���ϑԋ����A�g�D�A���ʁA�`�ԓ��ɋy�ڂ�������ʂ𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA����𗘗p�����@�\�ޗ��ւ̉��p�܂ŋ����[���u�����Ȃ��ꂽ�B��ʍu���ł����ϑԊW�̔��\�������������A���̑��ɂ�����𗘗p�����ޗ��v���Z�b�V���O�⎥�C�����Ɋւ��錤���ɂ��Ă��u�����Ȃ��ꂽ�B
�i��ˏG�K�i�����E�ޗ������@�\))
Session D�F�i�m���[�^�[�X�P�[���R�q�[�����g��N�n
�Q���Ґ��F40��
���ҍu�������i3��)�A�������\�����i9��)�A�|�X�^�[���\�i0��)
�@�{�Z�b�V�����ł͏����̃f�o�C�X���p������ɓ���ăi�m���[�^�[�X�P�[���̍\���̗�N�Ƃ����ɂ�����d����̎U��̐�����\�ɂ���Z�p�ɂ��Ă̕��������o�����Ƃ�ڎw�����B�����͂��̕����ɉ����Ċ����Ȕ��\�Ɠ��_���s��ꂽ�B
�@���ɁA��Ì�����H�Ƒ�w�����ɂ��A���̕���ɂ����鏫���̃f�o�C�X�̃j�[�Y���܂߂����̕���̌����̈ʒu�Â��Ɋւ���u�������̃Z�b�V�����̕K�v���E�ʒu�Â��m�ɂ����B�܂��A���эF�Ó�����w�����̍u���ł́ATime-resolved
spectroscopy�̎�@�ɂ������ԂŗL�@���q�̓��Ԃ𖾂炩�ɂ��A�ޗ��𐧌䂷��Ƃ����ϓ_����L�Ӌ`�ȓ��_���s��ꂽ�B�܂��A�x�T�a�R����w�������̍u���ł́A�d����̎U��𐧌䂷�邱�Ƃ̌����I�Ȗ��_���w�E����A�t�ɂ�����������邱�Ƃɂ��A�����̕����ł͑��炦����Ȃ��V���ȕ��삪�J���邱�Ƃ��������ꂽ�B
�@�X�ɖk���a�v���ۊ����w�����A�吼���B�R����w�����𒆐S�Ƃ����Z�b�V�����Ō�̓��_�͑�ϊ����ɒ����ԍs���A����ɂ�茻���_�ł͖{�Z�b�V�����̖ړI��B�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̎����̂��߂̕��r�������Ă����B�܂��A���_�Ƃ�����������邽�߂̍ޗ��Ɋւ��闼�ʂ���̓��_�����ݍ����A���{MRS�Ȃ�ł͂̃V���|�W�E���Ƃ��邱�Ƃ��ł����B
�i����@�ρi�����E�ޗ������@�\))
Session E�F�L�@�������̍쐻�ƕ]���\���q�z��E�z������̊ϓ_����\
�Q���Ґ��F36��
���ҍu�������i0��)�A�������\�����i24��)�A�|�X�^�[���\�i12��)
�@�Z�b�V����E�́A�R�{�@���i���嗝�H)�A���{�r�ǁi�Y�����E�i�m�e�N)�A�r��h��i�Y�����E�i�m�e�N)�A�O�Y�N�O�i�ˈ����l��H)�A�{��@�́i�ˈ����l��H�j�̏�������ѐ��@���v�i�ˈ����l��H�j���`�F�A�p�[�\���Ƃ��ĐV���Ɋ�悳�ꂽ���̂ł���B
�@21���I���}���ăi�m�e�N�m���W�[�Z�p�̓u�[���̊ς�悵�Ă��邪�A���̒��ɂ����āA���q�z��E�z���̐����i�Ƃ���LB���ȂNJe��̗L�@�������v���Z�X�Z�p���V���ȋr���𗁂тĂ���B���Z�b�V�����ݗ��̖ړI�́A���̂悤�ȏ܂��ėL�@�������̍쐻�ƍ\���E�@�\�]���q�z��E�z������̊ϓ_���瓢�_���邱�Ƃɂ���B
�@��1���ڂ���ё�2���ڂ�ʂ��Č������\24���A�|�X�^�[���\12���A���v36���̌������\�ɂ������ȓ��_���s��ꂽ�B�e�[�}�́A�E�ʉ��w�̊�b����V�K�@�\�����̑n���ƕ]���A�f�o�C�X�E�v���g�^�C�v�̎���܂Ŋe��̕���̂��̂��o�����A�����̖ړI�͒B�����ꂽ�ƍl���Ă���B�Q���҂̊�Ԃ��1980�N��Ɍ���ꂽ�L�@�������u�[���ȗ��̃��F�e�������炻�̑���q����ɂ������w�@�E�w�����܂ł̔N��w�ɂ킽�����B�����̂��Ƃ́A������̍���̈�w�̗�����\�z��������̂ł���A����ȍ~�����̎�|�̃Z�b�V�����𑱂��Ă������Ƃ��]�܂��B
�i���@���v�i�ˈ����l��w))
Session F�F�\�t�g�n�t�v���Z�X�𗘗p�����ޗ��n��
�Q���Ґ��F50��
���ҍu�������i1��)�A�������\�����i17��)�A�|�X�^�[���\�i13��)
�@�{�Z�b�V�����̔��\���e�́A�n�t�����𗘗p���������q�����Ɩ��`���Ɋւ�����̂���̂ł������B�ߑO���̃Z�b�V�����ł́A�����ɔ����q�����Ɠ���ꂽ�����q�ɑ���L�����N�^���[�[�V����������]���Ɋւ��錤�����\���������B�`�^�j�A�A�W���R�j�A�A�A�p�^�C�g�Ƃ������_�����n�̂��̂���A�_�����|��_�����△�@�|�L�@�̕����̂Ɋւ��錤���܂ŗl�X�ȍޗ��̘b�������A�����[�������B����A�ߌ�̃Z�b�V�����ł́A�܂����H��̈��������ɂ��t�F���C�g�Ɋւ�����ʍu�����������B�t�F���C�g�͓��H�唭�̍ޗ��ł���A���̗��j�I�Șb����ŋ߈��������̃O���[�v�ōs���Ă���t�F���C�g���̒ቷ�����Ƃ��̓d�C�E�d�q������×p����ւ̉��p�Ɋւ���b���������B��ʔ��\�ł́A�n�t�@�ɂ�閌�`���Ɋւ��錤�����\����̂ł������B������ł́A�`�^���_����j�I�u�_���Ȃǂ̕��G�ȉ������̔�����n�t�����𗘗p���č쐻�����������������\����A���w�I�ȕ��@�̔��������ւ̗L�p�����������ꂽ�B�܂��A�p�^�[���j���O�⌋�������̒��ڍ����Ȃǂ̋����[���������\���������B�|�X�^�[�Z�b�V�����͑�w�@���ɂ�锭�\�������������A���ꂼ��M�S�Ɏ����̌������ʂ�������Ă��ꂽ�̂ŁA�S�������ĉ��̂ɂ͏������Ԃ�����Ȃ������ł������B
�@�S�̓I�Ȉ�ۂƂ��āA�������\�ƃ|�X�^�[���\�̗�����1���ōs�������߁A���Ƀ|�X�^�[�̎��Ԃ��Z�����ď[���ɋc�_���s�����Ȃ������悤�Ɏv��ꂽ�B
�i���c�@���i�����H�Ƒ�w��w�@))
Session G�F��炵��L���ɂ���ޗ��\���E��ÁE�����\
�Q���Ґ��F60��
���ҍu�������i0��)�A�������\�����i30��)�A�|�X�^�[���\�i0��)
�@��炵��L���ɂ���ޗ����L�[���[�h�Ƃ��āA�Z���T�[�A�d�r�A���ޗ��A�l�H����A�l�H���A�g�D�H�w�̃X�L���z�[���h�A�C�̕������A��ܓ���ړI�Ƃ����@�\���Z���~�b�N�X�A�|���}�[�A���������ޗ��A�����A�����ė��_�Ȋw�ƃV�X�e���ɂ��Ă̕��W�܂����B�l�ނ̍K����ڕW�Ƃ����g��H�w�h����сg�����H�w�h�Ƃ����W���������A�ޗ��Ȋw�̕���ɂ����Ă��m�����ꂽ���Ƃ�����������ꂽ�B
�@��啪��̈قȂ錤���҂��ꎞ�ɉ�A���𗬂ł������ƂɁA�傫�ȈӖ����������Ǝv���B�e�N�j�J���^�[���̈Ⴂ�Ƃ����ǂ����z���āA�M���f�B�X�J�b�V�������J��L���Ă����茤���҂̎p���ڂɕt�����B�{�Z�b�V�����̂悤�ȉ�́A���̊w��ł͂Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ����Ƃ���A���{MRS�Ƃ����w�ۓI�Ȋw��̈Ӗ��������������B
�i�䉜�^��i�R����w��w�@))
Session H�F����i�m�\���̂̃f�U�C���Ɠ���
�Q���Ґ��F70��
���ҍu�������i4��)�A�������\�����i27��)�A�|�X�^�[���\�i22��)
�@�N���X�^�[�A�i�m���q�A�i�m���C���[�i�m�`���[�u�A�i�m�R�[���A�i�m�z�[���A�i�m�V�[�g�Ȃǂ��L�[���[�h�Ƃ����i�m�X�P�[���Œ���̍\����L����ޗ����Ƃ肠�����B���������ޗ�����X�̋Ɍ����𗘗p���č������R�x�Ɛ��䐫�őn��������@�₻���ɔ�������d�C�I�A���C�I�A���w�I�A���w�I�A�@�B�I�ȋ@�\�E�����Ɋւ��錤�����\���s��ꂽ�B�i�m�\���𐧌䂵�đn�����邽�߂̗l�X�ȕ����E���w�I�Ȏ�@�ƍ\���`���̃��J�j�Y���ɂ��Ă̊�b�I�Ȍ���������������p���邽�߂ɒ���i�m�ޗ���z����_�ɒ��ڂ����p�ւ̓W�J���������������܂ōL�͂ȕ���̔��\���W�܂�A�i�m�@�\���Z�p�Ƃ��Ă̎��p���Ɍ����Ē��X�Ɛi�����Ă��邱�Ƃ��������킹��B�܂��A�ٕ���̌����҂����݂��̃m�E�n�E������������A����̌����̓W�J�����ɑ��ĐϋɓI�ɗv�]����ȂNJ����ȋc�_���s��ꂽ�B
�i�����M�v�i�����H�Ƒ�w))
Session I�F�A���n�ޗ��̍ŋ߂̐i��
�Q���Ґ��F45��
���ҍu�������i2��)�A�������\�����i11��)�A�|�X�^�[���\�i18��)
�@�؍ނ͐l�ގj�̒��ōł���\�I�ȍޗ��ł���A�����ɂ킽��g�p���ꂽ�ޗ��̈�ł�����B�����܂��A�����̔��B�Ƌ��ɋ}���Ɏ��v�������Ȃ�A���`�B�p�A�ۑ��p�A�����ĕ�p�Ƃ��đ�ʂɏ����Ă����B�������A�؍ނ⎆�̐A���n�ޗ��̑�ʏ���͐X�ю������͊������邱�ƂɂȂ�B����ɂ́A�����̍ޗ����ċp����ꍇ�����ʂ̒Y�_�K�X���C���ɕ��o�����邱�Ƃ���n�����g���̈���ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȏɊӂ݂āA�{�Z�b�V�����ł́A�X�ю����̗L�����p�A�V���ȐA���n�����̊J���A����ѐA���n�����̃��T�C�N�������܂߂����@�\�I���p�@���ɂ��ē��c������̂ł���B�����\������ҍu���A�������\�A�|�X�^�[���\��3����ō\�����A�����ӎ������A���n�ޗ��̊J���E�����A�E�b�h�Z���~�b�N�X�̓����E�p�r�A�Y�����ޗ��̊J�����𒆐S�ɔ��\���s��ꂽ�B���ɁA�|�X�^�[�Z�b�V�����ł́A�w���ɂ��ϋɓI�ȎQ���̂��ƁA�����[�����e�̔��\���s���A�Ӌ`�[�����̂ł������B
�i�`�@�[�S�i����E�Ɣ\�͊J����w�Z))
Session J�F�R���d�r�ޗ�
�Q���Ґ��F55��
���ҍu�������i3��)�A�������\�����i8��)�A�|�X�^�[���\�i14��)
�@��ϐ����ł��藧�����̐l�����Ȃ�o���B�����Ƒ傫�����������肢���Ă����Ηǂ������Ɣ��Ȃ��Ă���B���ҍu���҂̔��\���e�����@���A�����[����[�I�ȓ��e�ł���]�����ǂ������B����͎��3���̎�Âɂ��V���|�W�E���ł��������u���ҁA�Q���ҋ��ɖ����ł�����e�̍u�����W�܂�A�܂����̕��͋C���M�C��ттĂ���A�����ł������ƌ��_�ł���BKSP�ŊJ�����i2�N�O�j�����Q���҂͖�2.5�{�����āA�����ŊJ�Â���ꏊ�̗����������Ǝv����B�����MRS-J�̎Q���҂��W�߂邽�߂ɂ�KSP�����s���̗L����w�ŊJ�Â�������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�i�{�ԁ@�i�i�Y�ƋZ�p����������))
Session K�F�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ�
�Q���Ґ��F60��
���ҍu�������i8��)�A�������\�����i9��)�A�|�X�^�[���\�i22��)
�@�{�Z�b�V������2�N�ڂƂȂ�A�h���C���Ɋւ���T�C�G���X�A������@�A���p���A�L���ϓ_���瑽���̎Q���҂��W�߂邱�Ƃ��ł����B���ɖ{�N�͗��N�̍���MRS���l�����A�C�O����̌����҂Ƃ��Ċ؍�����搶�ɉ����A�����ɂ�����h���C���֘A�̑�ꋉ�̌����҂��W�߂邱�Ƃ��ł��A���Ƀ��x���̍����u�����e�ƂȂ����B���̂���100�l�K�͂̉������������ɂ��ւ�炸�A���ԑтɂ���Ă͐Ȃ����܂藧�����̐l���o���ԂƂȂ����B
�@�܂��A���搶�ɂ��90�x�h���C���ǂ̍\���Ŏn�܂����{�Z�b�V�����ł́A��]�F�搶�ɂ��i�m�h���C���c�݂��l�����郂�f���ő����̓��ٕ����̐����A��搶�ɂ��SBN�Z���~�b�N�X�ɂ�������\���ƗU�d�����Ƃ̊W�A�ɓ��搶�ɂ��_�f18�u���̃`�^���_�X�g�����`�E���̋��U�d���]�ڋ����̐����A����搶�ɂ�锽�d��ɂ�钁���\�������h���C���\���̐����@�\�A���搶�ɂ��i�m�h���C����p���������x�L�^�}�̂ւ̉��p�A�`�^���_�r�X�}�X�P�����ɂ�����h���C���\���A���}���ώ@�Ȃǂ����X�ƏЉ��A�����̎Q���҂̋������������A���̂��ߗ\�莞����15���߂��Ă̒��H�ƂȂ����B�ߌ���ACross�搶��PZT�������̐��f�C�I���ɂ��h���C���Ljړ��}�����f���̒�āA�K���搶�ɂ��`�^���_�o���E���P�������ɂ�����h���C���ǂ̗U�d�����ւ̊�^�ɉ����APZT�����ɂ�����V�K���d����̒�āAPZN
-PT�P�����ɂ����鋐�刳�d�����A�z������ɂ��r�X�}�X�w�U�d�̃Z���~�b�N�X�̈��d�����A�A�G���]���f�|�W�b�V�����@�ɂ��U�d�̖��̒����g�ɂ��V�K�e������Ȃǂ��Љ��A�����ȓ��_���s��ꂽ�B���ɁA�I���搶�A�����搶�A�k���搶�ɂ��j�I�u�_���`�E���P�����ɂ�����h���C������ɂ��t�H�g�j�N�X�����ւ̒�ẮA�h���C���G���W�j�A�����O�ɂ�����j�ƂȂ肤��V�K�Z�p�ł���A����̓W�J�ɑ傫�Ȋ��҂����Ă�u���ł������B
�@����Ƃ͕ʂɃ|�X�^�[�Z�b�V�������ߌ�4������5�����܂ŊJ�Â��ꂽ�B�����ł�22���̔��\������A���̂����������\���܂�17��������܂̐R���ΏۂƂȂ����B�����ȐR���̌��ʁA�O�䉻�w�̜A�����A�ޗǐ�[�Ȋw�Z�p��w�̕��c����2��������܂̌��҂ƂȂ����B�{�Z�b�V�����ł́A��N�x���炩�ɂȂ������_�܂��A�u���Ґ��̑����A�K�͂̑傫�ȉ��A�Q���Ґ��̑����Ȃǂ̉��P�����݂����A����̖��_�������яオ�����B�܂��A�\�z�ȏ�ɑ����̎Q���҂����������߁A�ꎞ�I�ɉ��ŗ������҂��ł�悤�ȏ�ԂɂȂ����B���N�x�͍X�ɑ傫�ȉ����g�p����K�v������B�܂��A�Q���҂̂ق�70%�߂�����w�W�҂ł���A�Y�w���̊_�������������Ċ����ȋc�_�̏�ɂ������Ƃ����{�Z�b�V�����̗��O�����s���邽�߂ɂ́A���N�x��50%�ȏオ��Ƃ���̎Q���҂ɂȂ�悤�ɁA���͓I�ȃZ�b�V�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�Ɋ������B�܂��A1���ōs�������Ƃ�����A�X�P�W���[���I�ɔ��Ƀ^�C�g�ł��邱�Ƃ����ȓ_�Ƃ��ċ�����ꂽ�B
�i�a�c�q�u�i�����H�Ƒ�w��w�@))
Session L�F���E�̈�Ƃ��ẴQ���̉Ȋw�ƍH�w�\����̉Ȋw�����[�E���Ȋw�܂Ł\
�Q���Ґ��F52��
���ҍu�������i1��)�A�������\�����i15��)�A�|�X�^�[���\�i28��)
�@�����q�Q�����l�X�̑��ʂ���w�ۓI�Ɍ�������Ă��鎖�f���āA��ȍu�������ł��A�u�t�B�u�����̃Q���`���ߒ��̌��U���v�i�Q��E�E�c)�A�u�זE�^���ɂ�����זE���i�Q�����Ƃ������͊w�I�������v�i�k��E��[��)�A�u�M�����������q�d�����Q���̖c�������F�s�ψ�d�ׂ̉e���v�i�}�g��E���{�c)�A�u�����q�Q���ł̖c���Ɖ��͂̃J�b�v�����O���ہv�i����E���)�A�u���n�̍L�ш�U�d�����v�i���C��E���،�)�A�u�Q���ǖ������}�C�N���J�v�Z���v�i�Q��E�y��)�A�u�Q���̖c���E�͊w�E�j���ɋy�ڂ��ˋ��̌��ʁv�i�x�R����E�c����)�A�uNIPA-PEG�W�u���b�N���d���̐��n�t�̑������v�i��t��E�����)�A�u�\���F�������������Q���v�i������E�|����)�A�u������Ԃɂ����鍂���q�Q���̗U�d�I�����v�i���C��E���{��j�Ƃ����悤�ɁA��b�Ȋw����V�K�@�\�ޗ��J���A�H�i�Ȋw�A���Ȋw�ɂ܂ŋy�ԑ���̕���ɂ킽�锭�\���Ȃ���A�����q�Q���ɊW���錤�����e���ʂŊ����ɍs���Ă��鎖�����߂Ė��炩�ƂȂ����B���ɍ���́A�ʏ�̊w��\���ł͎��Ԃ������b���Ȃ����e�܂œ��ݍ���ōu�����Ă����������߂ɁA�w��1���ڂ͂��̕���Ő擱�I����������Ă�����X�̍u���i�˗��u��45���A���ҍu��60���j�݂̂Ƃ��A��2���ڂ̈�ʌ������\���u�����Ԃ�20���Ɨ]�T����������x�Ƃ����v���O�����쐬��̍H�v���s�����ɂ��A�������Ƃ������͋C�̒��ōu���⎿��E���_�������ɍs���A�����̎Q���҂�����]�T�̂���u���Ŕ��\���e��������₷�������Ƃ̍D�]�������������B
�i���@��L�i��B��w��w�@))
Session M�F�X�p�b�^�@�ɂ�锖���쐻�Z�p
�Q���Ґ��F80��
���ҍu�������i2��)�A�������\�����i18��)�A�|�X�^�[���\�i19��)
�@�X�p�b�^�@�Ƃ������ʂ̔������Z�p����g�������������A���G�}�����A���`�������A�U�d�̔����A�������d���ȂǁA�F�X�ȍޗ�����̔��\�����v39���������B�e����ŁA���ꂼ��قȂ������_����X�p�b�^�@�ɍH�v�������āA���]�̍\��������������������������邽�߂Ɏ��g�������ʂ����\����Ă���A���ɐV�N�Ȋ����Ŕ��\�����Ƃ��ł����B�R�w�@�傩�甭�\���ꂽTiO2������AVO2�����A�������d���Ȃǂ̎_���������̍쐻�ɂ��Ă̕A�F�s�{�傩�甭�\���ꂽ�K�X�t���[�X�p�b�^�@�ɂ��e�픖���̍쐻�Ɋւ���ȂǁA���e�̏[���������\����������A�����ȓ��_���Ȃ��ꂽ�B���k��̍������搶����́Anm�I�[�_�[�̔������̔����q�̗��a���z����єz�������A�������a�̐���@�A�������_���w�̐����@�ȂǂɊւ���Z�p���Љ��A�X�p�b�^�@�ɂ����Ă�nm�I�[�_�[�̔��\�����䂪�A�v�X�d�v�ƂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ�Ɋ�������ꂽ�B
�i���@�z��i�����H�|��w))
Session N�F�C�I���H�w�𗘗p�����v�V�I�ޗ�
�Q���Ґ��F50��
���ҍu�������i4��)�A�������\�����i19��)�A�|�X�^�[���\�i18��)
�@�C�I���𗘗p�����ޗ��Ȋw�́A���͂���ޗ��n���ɂ킽�蒘�������W�𐋂��A��ɐV�Z�p�ւ̊���Ƃ��ď�Ɋ��҂���ė������A�ߔN�͋������鏔�Z�p������ė��Ă���A���ĂуC�I���Z�p����b�Ƃ����u���[�N�X���[�����҂����Ƃ���ł���B�{�Z�b�V�����ł́A�C�I���H�w��p�����V�ޗ��A���邢�͐V�Z�p��ΏۂƂ��āA���ɑ��l�Ȍ����҂��ꓰ�ɉ�A������������ȋc�_���s��ꂽ�B���\�_���́A�C�I����ɂ��ẮA�勭�x�p���X�C�I���A���G�l���M�[�d�C�I���A�v���Y�}�C�I���A�A�[�N�C�I���A���C�I���A�N���X�^�[�C�I�������l�ȋZ�p�ɂ킽��A�ޗ��n�ɂ��ẮASi�n�i3C-SiC�ASi1-xGex���AFe/Si���w��)�AC�n�iC�i�m�`���[�u�ADLC���A�Y�f��)�A�������n�iCr
-N -O���A�����Y�f��)�A�����n�iTiAl�����ATiFe)�A�i�m���q�n�i�������AFe
-Co�����j���A�V�ޗ������������������������B���ҍu���ł́A�p���X�C�I���E�A�u���[�V�����i�����F�����Z�ȑ�)�A�����E�זE�ڒ��U���Z�p�i����I���F����)�A�N���X�^�[�C�I���Z�p�i������Y�F����)�A���C�I�������Z�p�i�ΐ쏇�O�F����@�j�̌���Ƃ��̍ŐV���ʂ���I���ꂽ�B
�@�܂��A�C�I���ɂ��������ُ̈�ό`��A�C�I���Ǝ˗U�N�����ȂǁA�]������ɂ͎��܂肫��Ȃ��悤�Ȕ��\������A�������ĂB�Ƃ�킯�A���̍ޗ��ւ̃C�I���Z�p���p�̔��\�ł́A���̂̑I��I�����𗘗p�����Ȗ��ȃA�v���[�`���A�����̌ő̕����I�Ȍ����҂ɃJ���`���[�V���b�N��^�����B�����C�I���Z�p���L�[���[�h�Ƃ������l�Ȍ������\�́A���ԓI�ɂȂ鋰������邪�A����A���f�I�E�w�ۓI�c�_�������ɍs��ꂽ���Ƃ͗\�z�ȏ�ł���A�ٕ���Z����ʂ����u���[�N�X���[�����҂������ƂȂ����B
�i�ݖ{�����i�����E�ޗ������@�\))
Session O�F�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�E�|�X�^�[
�Q���Ґ��F200��
���ҍu�������i0��)�A�������\�����i0��)�A�|�X�^�[���\�i57��)
�@�{�Z�b�V�����͓��蕪��̌����ɍi�炸�A�l�X�ȕ���̌����҂����̌������ʂ̏Љ�ƁA���݂��̌𗬂�ʂ��A�V�����ޗ������̕����̔�����A�����c�_��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ���ꂽ�B���̔��\���e�͑ΏۂƂ���ޗ��������݂Ă��Z���~�b�N�X�A�����A�����q�ȂǂɎn�܂�A�����ޗ��A�o�C�I�A�����̂Ɏ���܂ŕ��L�����삩��Ȃ��Ă���A�܂��MRS-J�̏k�}�̊ς�悵�Ă����B
�@����̓��C����ꂩ���◣�ꂽ�ꏊ�Ƀ|�X�^�[��ꂪ�ݒ肳�ꂽ���߁A����Ґ��͍�N�x�V���|�W�E��������⏭�Ȃ��悤�Ɏv�����B�������A���̕��A����̃|�X�^�[��ڎw���ė�������������A�e�|�X�^�[�̑O�ł͐^���ɐ������锭�\�҂ƔM�S�Ɏ��₷�钮�u�҂̎p������������ꂽ�B���̈Ӗ��Ŕ��\�҂ɂƂ��Ė��x�̔Z�����_���ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�{�Z�b�V�����̓����Ƃ��Ĕ��\�҂̔N��w�����Z�b�V�����ɔ�ׂĒႢ���Ƃ�����B�S���\57���̂���43��������܂̑ΏۂƂȂ��茤���҂ɂ�锭�\�ł������B���̒����珫���̃}�e���A���E�T�C�G���X�̐��E��S���l�����o��������̂Ɗ��҂������B�Ȃ��A�R���̌��ʁA4���̕��ɏ���܂����^���ꂽ�B�����A�b�������������\�������A�R���������Ȃ蓪��Y�܂��ꂽ���Ƃ�t�L����B
�@�Ō�Ƀ`�F�A���\���āA����܂̐R����S�����Ă����������搶���Ȃ�тɎ��s�ψ���̃����o�[�Ɋ��ӂ������B
�i��ԗ��j�i�����_�H��w))
��MRS
Fall Meeting 2002��
���{MRS����E���{��w���H�w�������@�R�{�@��
�@�{�X�g���ɂ�12��2������6���i�ߑO�j�܂ŁA5���Ԃɂ킽��Materials
Research Society�H�G���J�Â��ꂽ�B��c�͗�N�̂悤�ɐ����ł������B�Q���o�^�҂�4600���ȏ�A�C�O����̎Q���҂�4���ɒB�����Ƃ̂��Ƃł������B
�@��40�̃Z�b�V�����𒆐S�ɂ��Ċ����ȃv���O�������g�܂�Ă����BHynes��Sheraton�̖L�x�ȕ������c���Ɏg���ăv���O�������g�߂�͉̂��Ƃ��A�܂�����c�J�Ê��ł���B�|�X�^�[�����L��ŁA1�������蕝2m�̃{�[�h���ґ�Ɏg���Ă����B���ԓI�ɂ������Ղ�]�T���Ƃ�A��������[��5���܂łɌf�����A5������8���܂ł̓|�X�^�[�ܐR���A��11���܂ł̒����f�B�X�J�b�V�������Ԃ��ݒ肳��Ă����B
�@���̉�c�ł́A�{�v���O�����̂ق��ɂ������̊�悪�Ȃ���Ă���̂����͓I�ł���B���ۋ��������Ɋւ�����ʃZ�b�V�����ł͉Ȋw�Z�p�U�����ƒc�̖k�V�G�ꎁ�����{����̔��\�҂Ƃ��ăA�s�[�����Ă����B�܂��A8�̃Z�b�V�����Ń`���[�g���A���v���O�������݂����Ă����B���ł��A3�����i�m�t�@�u���P�[�V�����ł͕P�H�H��̏���搶�A���`���ł�ISTEC�̑��㎁�����ꂼ��䂪������̃C���X�g���N�^�[�Ƃ��Ċ���Ă����B����ɁA�o�ς��͂��A��������Ă���Ƃ͂����A200�Ђɋy�ԑ�K�͂Ȋ�ƓW�����s�ςł������B
�@���N�̓V��͂��s���ł���������ǁA���Ⴊ�����U��A�ቻ�ς̃{�X�g���̊X���݂͎�[�������B�������Ƃ�����������Ԃ̗]�T�������ɂȂ������̂��c�O�ł������B
���@�{�搶ICSTR���я܂����
�@The
International Conference on Solvo-Thermal Technology�iICSTR�j�ψ���́A���{MRS��C�ږ�E�����H�Ƒ�w���_����
�@�{�d�s�����i�N�ɂ킽�萅�M�Z���~�b�N�X�����ihydrothermal
reactions/solvo-thermal reactions�j�̌����E��������ۓI�ȍL����̒��Ń��[�h���Ă����Ɛт��̂��āA����2002�N7��22�`26���A�č�Rutgers��w�ŊJ�Â��ꂽ��5��International
Conference on Solvo-Thermal Technology�̉������7��24����ICSTR Distinguished
Lifetime Achievement Award�i���я܁j�悵���B
�@�@�{���_�����Ƃ��̌����O���[�v��1976�N�ɓ����H�Ƒ�w�H�ƍޗ��������i���A���p�Z���~�b�N�X�������j�ɐݗ����ꂽLaboratory
for Hydrothermal Synthesis����Ղɓ��{�̐��M���������𐄐i���ė����B���M���������̓`���͌��g�������ɂ����solvo-thermal
solution�Ƃ����n����������܂���V����discipline���J���Ă���B
�@�Ƃ���œ��{�ɂ����鐅�M�����̍��ۉ�c��1979�N�ɃX�E�F�[�f���ŊJ�Â��ꂽNobel
Symposium�̌p���Ƃ���1982�N�A���l�s�̓����H�Ƒ�w���Óc�L�����p�X�ŊJ�Â��ꂽ��1��International
Symposium on Hydrothermal Reactions�iISHR�j��Ƃ�����̂ł������BHydrothermal�Ƃ͒؈䐽���Y������w���_�������w�E���Ă���悤�ɁA���Ƃ��Ƃ͒n���w�̗p��ł������B�@�{������Joseph
A. Pask�J���t�H���j�A��w�����Ƒ������āA���M�����ƋZ�p�ɊW�̂���S�Ă��܂߂���c�Ƃ��āA�������g�s�b�N�X�́A�����̐��n�t���w�A�n�������A�z���̗n���A���M�v���Z�X�̃��f�����A�L�@���n���̐��n�t���w�A���M�v���Z�X�̓��͊w�A�z���\�ʂ̑��ݔ����A���������ƍz�������A���ՊE���_���ł���B�@�{�����͂��̉�c�Ń`�F�A�}���߂�ꂽ�BISHR�͂��̌�A�č��i1985)�AUSSR�i1989)�A�t�����X�i1993)�A�č��i1997)�A���m�i2000�j�Ő��M�������ۉ�c���J�Â��Ă��Ă���B
�@����A��1��International Conference on Solvo-Thermal Reactions�iICSTR�j��1994�N�ɍ��쌧�����s�ŊJ�Â��ꂽ�B���̉�c�͖��̂��番����悤�ɁA�����������̗n�}�isolvent�j�̉��w�������e�[�}�Ƃ�����c�ŁA�K�p�͈͂ՊE���́A�����A�G�l���M�[�E�����A��i�ޗ��A�p���������ɍL���Ă���̂�����Ƃ��Ă���BICSTR�͂��̌�A�����i1996)�ABordeaux�i1999)�A���m�i2000)�A�č�East
Brunswich�i2002�j�Ɖ���d�˂Ă��Ă���A2004�N8��23�`27���ɂ̓C���h��The
University of Mysore�ő�6��ICSTR���\�肳��Ă���i�A����F���m��w���w���������M���w�������E���V�a���Ayanagi��cc.kochi-u.ac.jp)�B
��International Conference on Advanced Materials: IUMRS-ICAM 2003�_����W
��ÁF���{MRS�EIUMRS�iInternational
Union of Materials Research Societies)
�����F2003�N10��8���i��)�`13���i��)
���F�p�V�t�B�R���l�i���l�݂ȂƂ݂炢)
�@�@�@38�V���|�W�E���A�v���i���[�A�ޗ�����t�H�[�����������̍u���E��悪�\�肳��Ă��܂��B
�ڍׂ�2nd Circular���������������B
�₢���킹��FIUMRS-ICAM2003�����ǁi��؏~�j)�ATel/Fax: 045 -339 -4305,
E-mail: icam2003��ynu.ac.jp; http://www.mrs-j.org/ICAM2003
�����{MRS���^�̌����
����1��u�V�@�\�ޗ��WApril
2004�v�A��ÁF�����H�Z�p������A2004�N4���i����)�A�����r�b�O�T�C�g�i�\��)�A�₢���킹��F�����H�Z�p������V�@�\���ޗ��W�W�ATel:
03 -3861 -3858�AFax: 03 -3861 -3894
����12��C���e���W�F���g�ޗ�/�V�X�e���V���|�W�E��
��ÁF�������Ȋw�Z�p����C���e���W�F���g�ޗ��E�V�X�e���t�H�[����
�����F����15�N3��17���i��)
�ꏊ�F���w��فi�����s���c��_�c�x�͑�1 -5)
�\�����ݐ�F��105 -0001 �����s�`��Ճm��1 -2 -10 �Ճm����c�ʃr��
�@�@�@�������Ȋw�Z�p����C���e���W�F���g�ޗ��E�V�X�e���t�H�[����
�@�@�@Tel: 03 -3503 -4681, Fax: 03 -3597 -0535, URL:
http://snet.sntt.or.jp/imf/imf-SY12.html, E-mail: imsf��sntt.or.jp
����51�I���W�[���_��
��ÁF���{���I���W�[�w��A���{�o�C�I���I���W�[�w��
���ÁF���{�ޗ��w��A�v���X�`�b�N���`���H�w��
���^�F���{�@�B�w��A���{MRS�A��
�����F2003�N9��17���i��)�`19���i��)
���F�ޗǏ��q��w�i��630 -8506 �ޗǎs�k��������)
�@�@�@�ߓS�ޗljw���k��5��
�\�����݁E�₢���킹��F���{���I���W�[�w��_��W
��600 -8815 ���s�s�����撆�������c��93 ���s���T�[�`�p�[�N6����3�K
�@�@�@Tel: 075 -315 -8687, Fax: 075 -315 -8688,
�@�@�@E-mail: byr06213��nifty.com
��IUMRS�����o�[�̉
��2nd
International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT
2003)&IUMRS-International Conference in Asia (ICA) 2003�A2003�N6��29���`7��4���ASingapore�A�ڍׁFhttp://www.iumrs.org/
��MRS Spring Meeting�A2003�N4��21���`25���ASanFrancisco�A�ڍׁFhttp://www.mrs.org/
��9th International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM2004)�A2004�N4��12���`16���ASanFrancisco,
California, USA�A�ڍׁFhttp://www.iumrs.org/
�@
To the Overseas Members of MRS-J
��Materials Technologies Can Save Japan�c�cp.1
Dr. Keiichi MURAI, Director, R&D Institute, Canon Co. Ltd.
�@It is more than ten years ago that the bubble economy crashed and the financial
system of Japan failed, but at this point in time the future aspect of Japan economy is
still uncertain and instable. Under such circumstances, I believe that only Japanese
material technology, eventually, has held the key to regenerate the Japan economy. To
produce a valuable product that is very competitive and distinguishable, it needs to
create an excellent material that shows very high performance and work well in the product
like a black box. For that purpose, both of the national project for university�\industry
cooperation and the national training program for the young people who can create novel
materials should be enhanced strongly based on the national vision by the authority. At
the same time Japanese chemical companies have been expected to make a aggressive effort
to develop novel materials that will be qualified in the five to ten years future.
��Report: The 14th MRS-J Academic Symposium�c�cp.3
Yasuro IKUMA, Kanagawa Inst. of Tech.
�@The 14th Symposium of MRS-J was held on 20th and 21st of December, 2002 at Tokyo
Institute of Technology, Ookayama Campus. In order to attract many participants, the
conference site was moved to new location. As a consequence, papers of 582 were presented
and approximately 800 attendees registered. These figures are larger than last several
years. Stimulated discussions were found in many sessions.
Session A �gFunctional Materials Based on Self-Assembly V�h; Prof. Tatsuya OKUBO (Univ.
of Tokyo); Invited (�R), Oral (1)2, Poster (4)1
Session B�gSmart Materials/Structures�h;Prof.Shuichi MIYAZAKI (Univ. of Tsukuba);
Invited (5), Oral (4)6, Poster(1)5
Session C �gControl of Structures, Morphologies and Properties of Materials by Magnetic
Fields�h; Prof. Tomoyuki KAKESHITA (Osaka Univ.); Invited (�T), Oral (2)2, Poster ( )0
Session D �gCoherent Excitation of Nanometer-scale Structures�h; Dr. Hitoshi NEJO
(NIMS); Invited (�R), Oral (�X), Poster ( )�O
Session E �gFabriction and Characterization of Organic Ultrathin Films�h; Prof. Michio
SUGI (Toin Univ.); Invited ( )�O, Oral (2)4, Poster (1)2
Session F �gPreparation of Innovative Materials Using Soft Solution Process�h; Prof.
Kiyoshi OKADA (Tokyo Tech.); Invited (�P), Oral (1)7, Poster (1)3
Session G �gMaterials for Living�\Environment�Medicine�Welfare�\�h; Prof. Kenichi
OKAMOTO (Yamaguchi Univ.); Invited ( )�O, Oral (3)0, Poster ( )�O
Session H �gDesigning and Properties of Low Dimensional Nanostructured Materials�h;
Prof. Kunio TAKAYANAGI (Tokyo Inst. Technol.); Invited (�S), Oral (2)7, Poster (2)2
Session I �gProgress in New Plant Materials�h; Prof. Masahisa OTSUKA (Shibaura Inst. of
Tech.); Invited (�Q), Oral (1)1, Poster (1)8
Session J �gSymposium of Advanced Materials for Fuel Cells�h; Dr. Itaru HONMA (AIST);
Invited (�R), Oral (�W), Poster (1)4
Session K �gDomain Structure Related Properties and Materials�h; Prof. Satoshi WADA
(Tokyo Inst. of Technol.); Invited (�W), Oral (�X), Poster (2)2
Session L �gScience and Technology of Gels as an interdisciplinary field�h; Prof.
Kazuhiro HARA (Kyushu Univ.); Invited (�P), Oral (1)5, Poster (2)8
Session M �gSputter Deposition Technology�h; Prof. Y. HOSHI (Tokyo Institute of
Polytechnics); Invited (�Q), Oral (1)8, Poster (1)9
Session N �gInnovative Materials Using Ion Technology�h; Prof. K. YATSUI (Nagaoka Univ.
of Tech.); Invited (�S), Oral (1)9, Poster (1)8
Session O �gMaterials�Frontier�Poster�h; Prof. Tatsuo NOMA (Tokyo Univ.of Agricult.
and Tech.); Invited ( )�O, Oral ( )�O, Poster (5)7
��Report of MRS Fall Meeting 2002�c�cp.8
MRS-J Vice President Prof. Hiroshi YAMAMOTO (Nihon Univ.)
�@The meeting was held in Dec. 2 -6, 2002 at Boston. The number of participants was about 4600 and its 40% came from foreign countries. About 40 sessions and other related programs were successfully organized.
��ICSTR Honors to Prof. Somiya�c�cp.8
�@Prof. Somiya received the 1st ICSTR Distinguished Lifetime Achievement Award (July
2002) for his outstanding accomplishments in teaching, scholarship and research relating
to Solvo-Thermal Reactions.
�ҏW��L
�@�@�{���́A�ҏW�ψ��Ƃ��Ă̏��߂Ă̎d���ł���܂����B�E�������킩��Ȃ����ɂƂ��āAMRS-J�W�҂̕��X�̃A�h�o�C�X�͔��ɐS���������܂����B���ɈɌF�搶�ɂ́A��600���ɏ��V���|�W�E�������܂Ƃ߂āA�j���[�X�ҏW�ɂ��傫�Ȃ��s�͂����������܂����B���\���グ�܂��B
�@����A��N12���ɊJ�Â��ꂽ�w�p�V���|�W�E������W�Ƃ��Čf�ڂ����Ă��������܂����B�e�Z�b�V�����̑�\�A�A���S���̕��X�ɂ́A���Z�������A���M���������܂����B���̏�����肵�āA���\���グ�܂��B
�@MRS-J�V���|�W�E���͖��N���N�J�Â̂��ƂɁA�ł����ڂ��W�߂Ă��錤������̃Z�b�V�����L���݂��A�ϋɓI�Ɋw�p�����𗬂̏����Ă���Ɗ����Ă��܂��B�����āA�����܂߂܂��܂���y�҂̌����҂����荞�߂鑋�����L���݂��Ă��邱�ƂɊ��ӂ������܂��B������܂��A���N���N�ł���Z�b�V�����E�V���|�W�E�����J�Â���邱�Ƃ����҂��܂��B(��c�W�K)