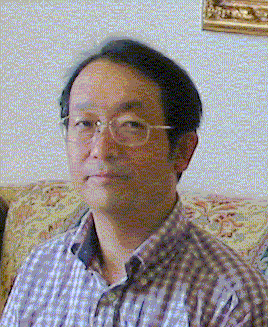 �@
�@���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.15 No.4 November 2003
�T �� �� ��
�����H�Ƒ�w ��w�@�������H�w������(�����Ȋw�n����U�j �����@ �R�� �z���Y
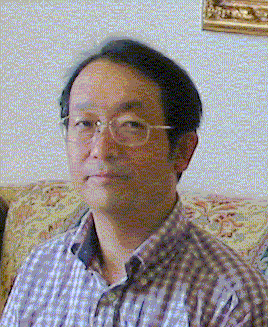 �@
�@
�@�u������research���Ȃ킿�A�J��Ԃ��T���Ƃ����Ӗ��ł��B�P���L���E�ł͉������߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��݂����ł��ˁv�Ɛ̗��w����A��������̐搶����f�������Ƃ�����B����Ȃ�A�D�ꂽ�����҂͒T���̂����Ȑl�̂��Ƃł���A�������ʂ��オ�����Ƃ��ɂ͉��l�̂�����̂��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł͒T���Č�����Ƃ��낪��{�ł���B���ɒT�����߂ɂ́A��x�T�����ꏊ���ĂђT�����肵�Ȃ��悤�ɁA�T�����ꏊ�Ɉ�����Ă����B�܂��A�吨�ŒT���ꍇ�́A�N�͂�����T���A���Ȃ��͂�����T���A�Ǝ蕪�����ĒT���������\���͏オ��B
�@���߂�ꂽ�ꏊ��T��������Ǒ_�������̂����������Ƃ��ɁA���̌����͐��������̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B���ׂĂ݂Ȃ���A�������Ƃ͕�����Ȃ������̂�����A���̌����́A���l�������Ƃ͂����Ȃ��B���������ו��͓K�łȂ���Ȃ�Ȃ��B��������ƌ����́A�������������i�_�������̂��������������j�ƁA���������ׂ�����ǂ�������Ȃ����������ƁA���ו������������̂Ŕ�ꂽ�����̌�����3��ނɕ��ނ����B
�@�u�T���O�ɗǂ��l����A�����������ƂɋC���t�����͂��̌����v����������B�i�v�@�ւ�T���悤�ȏꍇ�ł���B�����3�Ԗڂ̕��ނɓ���B�����ҏ����ŒT���Ă���Ƃ��ɁA�x��ĉ����������Ƃ��́A�����Ƃ����邩�ǂ����������ł���B��ɓ���������Ă��܂������琬���ł͂Ȃ��B�������_�������̂͌����������琬���Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@���܂�T�����Ƃ���l����ƁA������悢�̂ł���A���K�v�͂Ȃ��ƂȂ��Ă��܂��B�����Ȃ�ƍ��͂��̃x���`���[�n���͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B�����܂ōs���Ȃ��Ă��A���̍���J���͒T�������ł͐������Ȃ��B������research and development�ƒlj����Ă���B�\�z�͂��������l�͏]���̃��T�[�`�����ł͕�����Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B
�@�����҂̋C�����ɂȂ��Ă݂�ƁA�u���͒T�����̂����Ă���v�Ƃ͒ʏ�l���Ă��Ȃ��B�u����������x�����A���܂������͂���!�v�Ǝv���Ă���B���̋C������������A���A�T�����߂̒��ӗ́E�W���͂��N���Ȃ��B���̌����҂ɂƂ��āA����2�Ԗڂ̌�����Ȃ��������ʂ͑傢�Ȃ�u���]�v�ł���A���̌�����3�Ԗڂ̕��ނ֓���邩���m��Ȃ��BResearch�Ƃ������t�͌����s�ׂ������l�����A�u�����v�͌����҂���������t�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�����}�l�[�W���[���猩����ǂ����낤���B�T���Ȃ�A����T��?�@�ǂ����A�ǂ̂悤�ɁA���܂łɒT��?�@�ȂǁA���⋤��������i�߂�Ƃ��ɂ́A���̌������͕֗��ł���B�u�����肻���ɖ������̂�T�������̂��v�Ȃǃ}�l�[�W���[�̎w���ӔC�����������B�u�����v�Ȃ�A�����҂́u�ł��ꐶ�������������̂�����c�v�̂悤�Ɍ������₷���B�u�T���v�ꍇ�ɂ́A�u���nj�����Ȃ������̂ł��ˁv�ƕ]�������Ɖ��킵�ɂ����B�u���͌���������Ă��܂��v�ƌ�����ƁA�u�����ł����v�Ɠ������܂܂ł��悢���A�u���͒T���Ă��܂��v�̏ꍇ�́A�u�����ł����v�ƕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�ڕW���ŏ�����q�����Ă���B�T���Ƃ��ɂ́A������u�I���v�ł��邪�A���߂�̂ł�����܂ł���������B
�@��������o�������猩����ǂ����낤���B�u�������ɖ𗧂ĂĂ��������v�ƌ����Č��������������͍ŋ߂߂����茸�������A���ꂪ��Ԃ��肪�����B���͏o���������ꂪ��Ԋy�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ڕW�𗝘H���R�ƌ����Ē����ƁA�u�悵��邼�v�ƌ��ӂ�V���ɂ��邪�A�������R���~�����Ȃ�B
�@�����ƃ��T�[�`�̈Ⴂ�ɂ��Ďv���t�����Ƃ������A�˂Ă݂��BResearch�̌ꌹ����͂��ꂱ�ꔭ�z���L����������ǁA�u�����v����͎��X�ƃC���[�W���O�֍L�����Ă������Ƃ͖����悤�ł���B�|���̎�_���\��Ă���ƌ���̂��A���₱�ꂱ�����m�̒m�b�ł��茳�C�̂��Ƃƍl����̂��B�c�_�͐s���Ȃ��B
�d��@�ɂ������A���R�L�V�h�̍���
������Ѝ����x���w�������Z�p�J�����@�n��@�a��
�@1.�@�͂��߂�
�@��ʂɋ����A���R�L�V�h�́A�����_����������o���N�̐������@�ł���]���Q���@��MOCVD�@�̌����Ƃ��ėp�����Ă���B�ߔN�A�����̃������[�̍����\���A��e�ʉ��ɔ����A���U�d���̖������߂��A�܂�La���͂��߂Ƃ��郉���^�m�C�h�A���R�L�V�h�͕s�č����G�}�̌����Ƃ��Ă����ڂ���Ă���B
�@�����ƂȂ�����A���R�L�V�h�͒ቿ�i���������߂���Ɠ����ɂ��������ۂ̊��ʂł̔z�����]�܂�Ă��邪�A�]���̋����A���R�L�V�h�̐����͋������������������A������o�������Ƃ��ăA���R�[���Ɣ��������鎼����������ʓI�ŁA��ʂ̉��f�K�X�̎g�p�ɂ���Ɗ��̈����A�������K�X�̏����A���u�̕��H�A�����������₷�������������̎�舵�����A�l�X�Ȗ�������Ă���B
�@�����ŏЉ��d��@�ɂ������A���R�L�V�h�̍����͏o���������������̂��̂ł��莼�������Ɣ�וK�v�Ƃ��鉖�����f�K�X�͏��ʂł��邽�ߔr�K�X�����Ȃ��A���u�̕��H�����Ȃ����Ƃ���ʎY�����\�ł���A�ቿ�i�̋������\�Ƃ���B
�@2.�@�]���̋����A���R�L�V�h�̐������@
�@�]���A�����A���R�L�V�h�̐����͋��������������A������o�������Ƃ��ėp���鎖�������B���悤�Ƃ�������A���R�L�V�h���\�����鐬���ł���A���R�[���Ɠ���̃A���R�[�����ɂ��̉�������n�������A���̌�A�����j�A�Œ��a���A�������鉖���A�����j�E���𒾓a�A�������Ď�菜������̉t�������A�������ċ����A���R�L�V�h�Ă����i�}
-1)�B
�@�o�������ł�������������̐����́A����������_�����Ɖ��f�ڔ���������̂���ʓI�ł���A���f�K�X��500���ȏ�̍����Ŏg�p���邱�Ƃɂ�鐻�����u�̕��H�������ۂ̍�Ɗ��ʂł̐������ƂƂ��ɔ��������������A�܂����������f�K�X���X�N���o�[���ŏ�������K�v������A�傪����Ȑ��Y�ݔ���K�v�Ƃ����B�܂�������������������A���R�L�V�h�ɕϊ�����ۂɂ͕������鉖���A�����j�E������������K�v������A���ΐ��t�̂Ƃ̍��������Ƃ������S�����l��������^�ݔ���K�v�Ƃ��A�܂����������ʂ̉����A�����j�E���͐��i�̋����A���R�L�V�h�Ɋ܂܂��s�����̌����Ƃ��Ȃ��Ă����B
�@�����A���R�L�V�h��d���Ő���������@�́A���������\����Ă��邪�A�h�C�c����2,121,732���A�t�����X����2,091,229���ɋL�ڂ����NH4Cl�̂悤�ȃA�����j�E������d�����Ɏg�p���ėz�ɋ�����d�C�����ŗn����������@�ł́A�A�����j�E�����̃A���R�[���ɑ���n��x���Ⴍ�A�d�����Ƃ��Ă̎g�p�ʂɐ��������邽�߂ɑ����̓d�����������d���ɒ����Ԃ�v�����B�܂��A�A�����j�E�����͓d�𒆂ɓd�C�`�����ω����A����ȓd���������s���Ȃ������B
�@�J�i�_����1,024,466����Polyhedron, Vol.15, 3869 -3880(1996)�ɋL�ڂ���Ă���LiClO,
LiCl�̂悤�ȃ��`�E������d�����Ƃ��Ďg�p����ꍇ�A��r�I�ǍD�ɓd�C�������s���邪�A���`�E�������悤�Ƃ�������A���R�L�V�h�Ɣ������ă_�u���A���R�L�V�h���`�����ĕs�����ƂȂ�B�d���t���ɗn�����鉖�����`�E���͔����q�Ńg���G���A�x���[�����̗L�@�n�}��p���Ă��h�߂ł����A������������������Ă����B
�@Inorg. Chim. Acta, Vol.53, L73 -76 (1981�j�ɋL�ڂ���Ă���(C4H9)4NBr�̂悤�Ȏl���A�~������d�����Ƃ��Ďg�p������@�ł́A�d�C�`�������\���łȂ��A�܂������A���R�L�V�h���ɕs�����Ƃ��ďL�f�𑽗ʂɊ܂݁A�������������͍̂���ł������B
�@�ߔN�A�d�q�ޗ�����ɂ����ċ��U�d�̔������J������A���̍ޗ��Ƃ��ă^���^���A�j�I�u���̋����A���R�L�V�h���g�p����Ă���B�����̋��U�d�̔����ޗ��͕s�����̍����ɂ���Ă��̐��\���������j�Q�����B���Ƀ��`�E���A�i�g���E���Ƃ������A���J�������̍����͌����Ȑ��\�ቺ���������Ƃ��m���Ă���A��L�̕��@�ł͐����Ɏ��Ԃ������邱�Ƃ�A�s�������������邨���ꂪ���邱�Ƃ�����p��������̂�����ł������B
�@3.�@�V�d�������@�ƌ���
�@��L�̌��_���������邽�߁A���܂��܂ȕ�����d�����Ƃ��Č��������ʁA�������f��d�����Ƃ��ċ����A���R�L�V�h�̐����������Ȃ����Ƃ����ʐ��Y�ɕs�����ȋ������������܂������g�p�����������ł��A�������d�q�ޗ�����Ō����A���J���������܂܂Ȃ������x�̋����A���R�L�V�h�̐����ɐ�������1)�B
�@�d�������ʼn������f��d�����ɗp�����{���@�̗v�_�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�����A���R�L�V�h���\�����鐬���ł���A���R�[���Ɠ���̃A���R�[�����ɉ������f�K�X��1�`15wt%��������B���a���������d�𑅂ɃA���R�[�����[�U���������f�K�X��K�v�ʐ������ݗn��������B�s�����K�X�����A���̗n�t���ɋ����A���R�L�V�h���\����������Ɠ���̋�����z�ɂɎg�p���A�A�ɂɂ͂���Ɠ��l�̋����A�܂��̓J�[�{�����g�p���Ē�����ʂ��ēd�C�������s���A�����A���R�L�V�h�̃A���R�[���n�t��B����ꂽ�A���R�[���n�t���牖�f���������邽�߃A�����j�A�K�X�����Ē��a���A�����A�����j�E���̒��a���Ƃ����h�߂��邱�Ƃɂ��A���R�[�����番�����ď�������B�ߏ�̃A���R�[�����ɗn�����Ă�������A���R�L�V�h�����邽�ߌ��������������Ȃ��A���R�[���𗯋�����B
�@����ɏ��x���グ�邽�߂ɂ́A�w�L�T���A�I�N�^���A�g���G�����̗n�}�Œ��o�������������邱�Ƃɂ���č����x�̋����A���R�L�V�h�邱�Ƃ��ł���i�\
-1�F�၁�y���^�G�g�L�V�^���^��)�B
�@�d��@�̔����@�\�͈ȉ��̂悤�ɍl�����Ă���B
��z��
�@�@M+�{Cl-�{OR-�@����������M(OR)nClm
��A��
�@�@M(OR)nClm�{e-��M(OR)nClm-
�@�@�@�|Cl-�@��������M(OR)nClm-1
�@�@�@�{ROH,�|1/2H2�@��������������M(OR)n+1Clm-1
�@�@�@�{e-�@�������c�{ROH,�|1/2H2,�|Cl-�@��������������������M(OR)n+m
�@�{���@�ō����x�̋����A���R�L�V�h�������闝�R�́A�d���̒i�K�ŋ������̕s���������F�̒��a���Ƃ��Ĕ������A�A�����j�A�K�X���a��ɃA���R�[�����ɐ������鉖���A�����j�E���ƈꏏ���h�ߕ����ł��邩��ł���B���̎��ɕ����̎��Ă��铯�����f�������ł��A����ɔ����t�ɐ������������{���邱�Ƃŕ��_�̈قȂ�s�������������邱�Ƃ��ł���B
�@���Ƃ��Ώo�������ł���Ta�����ɂ͕s�����Ƃ��ē������f�ł���Nb��18ppm�܂�ł���A���̑���Al�ACa�AFe�ATh���g�[�^���Ő�ppm�܂�ł���B����ɓd�������������Ȃ��A�������������{���邱�Ƃŋ����A���R�L�V�h���̕s������Nb�ɂ��Ắ�100ppb�ȉ��A���̑��̋����͐�ppb�`���\ppb�ȉ��܂Ō��炷���Ƃ��ł���B
�@4.�@�܂Ƃ�
�@�]���̋����A���R�L�V�h�̐������@�Ɖ������f��d�����Ƃ����V�������@�A�����ɂ��ďq�ׂ��B
�@�d�������ʼn������f��d�����ɗp�����ꍇ�ATa�����̓d���͐������Ă��蓯���̌��f�ɂ��Ă��d���ɂ���ċ����A���R�L�V�h���������邱�Ƃ��ł���B
�@���݂�Ga�AY�ATi�AZr�A�L���p�V�^�[�ޗ��Ƃ��Ē��ڂ������Hf���̓d�������������Ȃ��Ă���A�d�����A���������A�������@�ȂǑ����I�ϓ_���猟���J����i�߂Ă���B
���@�@��
1) �������x���w�������@������3455942��
�@
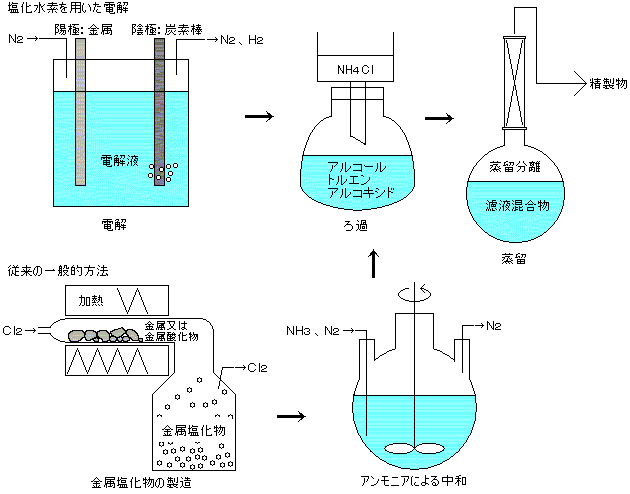
�}�P�@�������f��p�����d��@�Ə]���̋����A���R�L�V�h�����@
�@
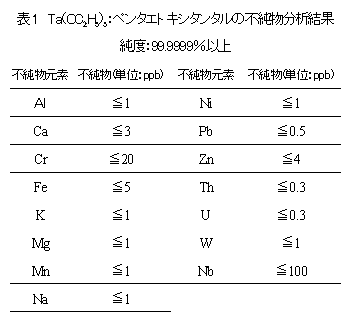
�@
| �A����F������Ѝ����x���w�������Z�p�J���� �n��a�� ��350 -0284�@��ʌ���ˎs���c5 -1 -28 Tel: 049 -284 -1511�AFax: 049 -284 -1351 E-mail: kjcgikai��kojundo.co.jp |
�@
������������T�[�`�Z���^�[
�\T&T: Trust and Technology�\
������Г������T�[�`�Z���^�[�Z�p��掺�����@���R�@�z��
�@1.�@�͂��߂�
�@������Г������T�[�`�Z���^�[�i�ȉ��ATRC�Ə̂��j�́A����������Ђ̌����J������̕��́E�����]���O���[�v���̂Ƃ��A���x�ȋZ�p�ŎЉ�ɍv�����邱�Ƃ�ڎw���āA1978�N6���ɐݗ�����܂����B�{�N6����25���N���}����TRC�̊����̊T�v�ɂ��Ă��Љ�܂��B
�@2.�@TRC�̊����Ƒ̐�
�@TRC�̎�ȋƖ�����́A
�@�@�@���́E�����]��
�@�A�@��[�Z�p�E�s�꒲��
�@�B�@�Z�p�����������|�[�g�̔�
����\������܂��B
�@�ݗ����̎�̂ł������@���́E�����]�������݂��傫�Ȓ��ł��B�@�A�A�A�B�Ƃ��A���q�l�ւ��n������u���i�v�́A�����Ƃ��āA�u���v�ł��BTRC�ł̕����́A�����Ȃ���y�v�`�h�����ƃC�I���������������A�@�ł̊����̈�Ɋ܂܂�܂��B
�@�@�őΏۂƂ���Y�ƕ���́A�u�G���N�g���j�N�X�v�A�u�H�ƍޗ��v�A�u���E�G�l���M�[�v�A�u���E�o�C�I�v�A�u���̑��v�ƕ��L������ɂ킽���Ă��܂��B
�@�@�ɂ����镪��ʔ䗦��} -1�Ɏ����܂��B���Ƃ��ƃG���N�g���j�N�X��H�ƍޗ��̔䗦���������ŁA�ߔN�A���E�o�C�I�̔䗦�����܂��Ă��܂��B
�@��БS�̂̔���z�́A�ݗ����i1978�N�x�j�̖�5���~�ɑ��A2002�N�x�͖�65���~�ł��B
�@���������������̎�̂ƂȂ�g�D�Ƃ��ẮA��������A������������A�c�ƕ����3���傪����A���݂ɘA�g�����������s���Ă��܂��B�܂��A�S�ГI�ȑg�D�Ƃ��āA�Ǘ����A�������ɉ����A�i���ۏؕ�������܂��B
�@�����ł́A��������̊����𒆐S�ɏЉ�A�i���ۏɂ��Ă��ȒP�ɐG��邱�Ƃɂ��܂��B
�@(�P)�@��������̊���
�@���̊����́A�c�ƕ����ʂ��Ď������́E�����]���Ɩ��̐��s�ł��B��b�����ɂ����鐸���ȃf�[�^�̎擾�A�J���i�K�ɂ������X�̌��ۂ̃��J�j�Y���̌��A�����i�K���邢�͐��i�ɂ�����g���u�������Ȃǂ��������܂��B
�@���̍ہA�@���ێ��̂��ƐM�����̍����Z�p�ł��q�l�i����Ɍ����A���Y�̐��Ɓj�̖����������Ƃ��̗v�ł��B���̂��߂ɂ́A���́E�����]���Z�p�Ƃ��Ĉꗬ�̂��̂�����߂�ƂƂ��ɁA�e�f�ށA���i�A�v���Z�X�Ɋւ���Z�p��̒m����g�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@TRC�ł́A�����Ƃ��āA���͒S���Ҋe�l�������̃T���v�����O���瑪��A���́E�����]���A��́A���쐬����т��q�l�ւ̐����Ɏ����т����Ɩ��𐋍s�ł��鎩�Ȋ����^�̋�������{���Ă��܂��B�܂��A�Г��O�̃Z�~�i�[���ɐϋɓI�ɎQ�������邱�ƂŁA��v�ȑf�ށA���i�Ɋւ���ŐV�̏���@���݂��Ă��܂��B������͂̐����ɂ���ẮA�����̎�@��K�p����K�v�������܂��B�����������ꍇ�A���̃e�[�}�̃��[�_�[�̂��ƂɁA�W���镪�͒S���҂����S���������邱�Ƃɂ��A�����I�ȉ��߂Ɍ��т�����̐��ɂȂ��Ă��܂��B
�@��N7���ɂ́A�|�X�^�[�Z�b�V�������J�Â��A�e���͒S���҂��ŐV�̋Z�p���Љ�邱�Ƃł��q�l�Ƃ̒��ڑΘb�̋@���݂��Ă��܂��B2003�N�x�́A���l�A���A�����ŊJ�Â��A���v��1,000���̂��q�l�ɏo�Ȃ��������܂����B
�@���E�����ł̍ŐV�̕��́E�]���Z�p�����邤���ł́A����̕��͊����ɂ�����n�ӁA�H�v�ƂƂ��ɁA�V�K���͋Z�p�y�ё��u�̓�����i�߂Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A�i�m�e�N�m���W�[�ɂ�����]����@�Ƃ��ċߔN���W�̒����������^�v���[�u�������iSPM�j�́AIBM��Binnig��Rohrer�ɂ�鑖���^�g���l���������iSTM�j�̔����i1982�N�j�ɒ[���܂��BTRC�ł́A��������STM�̏������ɒ��ڂ��A1987�N�ɒʏ��Y�ƏȍH�ƋZ�p�@�d�q�Z�p�����������i�����j�̃O���[�v�ɉ�����Ċ�b�I�Ȍ������n�߁A1989�N�ɂ͎s�̑��u�����Ď�����͂��J�n���܂����B
�@1991�N�ɂ͌��q�ԗ͌������iAFM�j�����܂������AAFM�͌��݂Ɏ���܂�SPM�̎�v�Ȏ�@�Ƃ��Ċ��Ă��܂��B
�@1997�N�ɂ́A�X�C�X�E�o�[�[����w��H.-J. Gu�Nntherodt�����̂��Ƃ�SPM�̌����҂����w���ASPM�Z�p�����p�����������x�M���͂̌������s���Ă��܂��B
�@����ɁA1997�N����A�����̃f�o�C�X�̃h�[�p���g���z��]�����鑖���^�L���p�V�^���X�������iSCM�j�̎�����J�n���A2001�N�ɂ͓����p�r�̑����^�g�����R�������iSSRM�j�����܂����B����2��@�́A�����̃f�o�C�X�̗L�͂ȕ]����@�Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���������C�O���w���x�ɂ��TRC�Ј��̔h����Ƃ��ẮA1991�N���猻�݂ɂ����āA�X�E�F�[�f���E�E�v�T����w�iX�����d�q�����@�FESCA)�A�č��E�I�n�C�I�B����w�i���}�������@)�A�h�C�c�E�~�����X�^�[��w�i��s���Ԍ^2���C�I�����ʕ��͌v�FTOF-SIMS�j�̂悤�ȕ\�ʁA�������̉��w�\����͎�@���삩��p���E�I�b�N�X�t�H�[�h��w�i�j���C�������@�FNMR)�A�č��E�n�[�o�[�h��w�i�Q�m����͋Z�p�j�Ȃǂ̐����Ȋw����Ɏ�������̌����@�ցA�v15��������܂��B
�@������͂ɂ����Ă��A�č��ECharles Evans&Associates�iCE&A�j�ЁiSIMS�j���͂��߂Ƃ���C�O�̒�]�����啪�͋@�v13�ЂƂ̒�g�����{���Ă���A���q�l����̎�X�̗v���ɂ������ł����������Ă��܂��B
�@�ŋ߂̐V�K�������u�̗�Ƃ��ẮA���\��̔����̈敪�͗p�Ƃ��Č����ԊO�C���[�W���O�V�X�e���i��ԕ���\�F��6��m�j�FSpotlight300�iPerkin-Elmer���j�A���f�E���\��̕\�ʔ��������͂��\��X�����d�q�����iESCA,
XPS�j���u�FQuanteraSXM�iPHI��)(��ԕ���\�F��10��m)�A�]������ł������C���`�����ⓜ���Ȃǂ̍\����͂ɈЗ͂�����Ɗ��҂����A�}�g���b�N�X�x���C�I����
-��s���Ԍ^���ʕ��͌v�iMALDI-TOF/MS�j�FAXIMA-QIT�i���Ð��쏊��)�A���ԕ��͗p�Ƃ��Ẳt�̃N���}�g�O���t/�^���f���^���ʕ��͌v�iLC/MS/MS�j�FAPI4000�iAB/MDS
Sciex���j�y��TSQ Quantum�iThermo Quest��)�A�����͗p�r�ł̍�����\�K�X�N���}�g�O���t���ʕ��͌v�iGC/MS�j�FAutoSpec-Ultima
NT�iMicromass���j�ȂǁA��X�̕���ɂ�����ŐV�̋@�킪�������܂��B
�@����A���ƃv���W�F�N�g�ւ��n����̑����i�K����Q�悵�A�Ȋw�Z�p���v���W�F�N�g�u�\�ʊE�ʂ̐���Z�p�v(1981�`1986�N�j�����߂Ƃ��Čv17����������Ă��܂��B
�@���̂����A�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�iNEDO�j�u�����㔼���̃f�o�C�X�p�����x���������ނ̂��߂̊�ՋZ�p�J���v�ANEDO/�Вc�@�l�o�C�I�Y�Ə�R���\�[�V�A���iJBIC�j�u���̍����q���̍\������̓v���W�F�N�g�v�A�Ȋw�Z�p�U�����ƒc�iJST)�uCREST�V����J�[�{���i�m�`���[�u�̑n���A�]���Ɖ��p�i2002�`2006)�v�ȂǁA�v5�������ݐi�s���ł��B
�@�������ċZ�p�J�������������ʂ̂������J�ł�����e�ɂ��ẮA�ϋɓI�ɎЊO���\���s���Ă��܂��B�ЊO���\�́A�ΊO�I�Ȕg�y���ʂ����ł͂Ȃ��A�l�ވ琬�ɂ��L���ł���A��ЂƂ��Ă��������Ă��܂��B�ߋ�19�N�Ԃ̔��\������\
-1�Ɏ����܂��B
�@�������������̒��ŁATRC�ݗ��ȗ��A12���̌����҂��w�ʁi���m���j���擾���Ă��܂��B
�@�܂��A�m�I���Y�̗L�����p�̊ϓ_����A�����o�蓙�̊����������Ɏ��{���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���Ð��쏊�̓c���k�ꔎ�m�̃m�[�x����܂��_�@�ƂȂ�A�ŋ߁A���͋Z�p�̏d�v�����e���ʂŌ�������A�����x���ōŐ�[�̕��͋@��̊J���Ɋւ���d�v�����w�E����Ă��܂��B�����Ȋw�Ȃł�������ݒu����ATRC�����̃����o�[�Ƃ��ĎQ�����Ă��܂��B����A���̂悤�Ȑ�[���͋@��̊J�����ɂ����Ă��A�����ł��v���ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�@(2)�@�i���ۏؑ̐�
�@���q�l����̂��˗��ɑ��A�u�M�����̍������ɂ���Ă���������v�ϓ_����A���ەW���ł���ISO9001����{�Ƃ����i���ۏؑ̐����\�z���Ă��܂��B�����̎�����͉�ЂƂ��ď��߂āA1999�N�ɁA�c�ƕ�����܂߂��S�Ј�̂Ƃ��Ă̔F���擾���܂����B
�@�o�c���O�ł���u���x�ȋZ�p�������ĎЉ�ɍv������v�̂��ƂɁu�ڋq�����v�A�u�@������v�A�u���M�����Z�p�v�A�u�i������A����v�̕i�����j���f���Ă��܂��B
�@�܂��A�g�L�V�R�L�l�e�B�N�X����Ɋւ�����iGLP�̓K���m�F�ł̕]���uA�v�F��A�����͌������i���ꎖ�Ə��j�ł̓���v�ʏؖ����ƎҔF�萧�x�iMLAP�j�̔F�肨���ISO14001���}�l�W�����g�V�X�e���o�^�Ȃǂ��������܂��B
�@3.�@�܂Ƃ�
�@TRC�́A�ݗ������̗��O�ł���u���x�ȋZ�p�ŎЉ�ɍv������v���|�Ƃ��A�i�m�e�N�m���W�[�A�o�C�I�e�N�m���W�[�Ȃǂ̍Ő�[�Z�p�̐i�W�ɑΉ��ł��镪�́A�����]�����邢�͋Z�p�����ɂ�����Z�p�͂���w���コ���A�Y�ƊE�E�w��ւ̍X�Ȃ�v���������Ă���������悤�w�߂Ă��܂��B
�@TRC�́A���q�l�E���������ҋy�ђ�g�@�ւȂǂ̎��͂̕��X�ƂƂ��ɐ����𑱂����Ђł��B����Ƃ��A�F�l�̂��w�����ڝ������肢�\���グ�܂��B
�@4.�@�Q�l����
�@TRC�̃z�[���y�[�W1)�y��TRC�j���[�X85��2)�����킹�Ă�������������K���ł��B�z�[���y�[�W�ʼn���o�^�����Ă����������ƂŁATRC�j���[�X�iPDF�t�@�C���j�ւ̃A�N�Z�X���\�ł��B
�@���@�@��
1) URL http://www.toray-research.co.jp/
2) TRC�j���[�X85���|�n��25���N�L�O���|,
������������T�[�`�Z���^�[, 2003�N10��
�\�P�@TRC�Ј��̎ЊO���\������1�i1984�`2002�j
| �����_�� | 319���i�p���F270�A�M���F49�j |
| �����E����E�P�s�{(���S���M���܂�) | 221�� |
�w��\�i�����E�|�X�^�[�j
|
1203���i���ۉ�c#2�F304�A�����w��F899�j |
| �w��W�̃Z�~�i�[�E�u����ł̍u�� �@ | 350�� |
#1�c��w���̑��̌����@�ւƂ̋������\���܂ށB
#2�c���{�����ŊJ�Â��ꂽ���ۉ�c���܂ށB

�}�P�@���́E�����]���ɂ����镪��ʔ䗦(2002�N�x)
�@
| �A����F������Г������T�[�`�Z���^�[�Z�p��掺 �@���R�z�� �@ ��520 -8567�@��Îs���R3 -3 -7 �@ Tel: 077 -533 -8544�AFax: 077 -537 -6434 �@ E-mail: youichi-nakayama��trc.toray.co.jp �@ Home page: http://www.toray-research.co.jp/ |
�@
�����{MRS��14��N�������
2002�N4��1���`2003�N3��31��
�@���{MRS�̑�14��N������́A2003�N5��29��(�j�A18�F15��蓌���s�`��Ճm��1
-2 -10�Ճm����c�ʂ�r��7�K�Вc�@�l�����Ȋw�Z�p�����c���ŊJ�Â��ꂽ�B�c��́A��14���ƔN�x���ƕA��14���ƔN�x���x�A��15���ƔN�x���ƌv��A��15���ƔN�x���x�v��A��15���ƔN�x�����I�C��5���B�e�c�肪�R�c�̂������F�E������܂����B���ꂼ��̊T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
����14���ƔN�x�i2002�N4��1���`2003�N3��31���j�ɂ����܂��Ă͐V���ȉ�v�N�x�̂��ƁA���ƌv��ɉ����A2002�N12��20��(��)�`21��(�y)�A�����E�����H�Ƒ�w�剪�R�L�����p�X�ɂđ�14��N������A�w�p�V���|�W�E�����J�Â��܂����B�V���|�W�E���́A1.
���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\�i����15/�|�X�^�[41)�A2.
�X�}�[�g�}�e���A���X�g���N�`���[�i46/15)�A3.
����ɂ��\���A�g�D�A�@�\����i17/0)�A4.
�i�m���[�^�[�X�P�[���R�q�[�����g��N�n�i12/0)�A5.
�L�@�������̍쐻�ƕ]���\���q�z��A�z������̊ϓ_����\�i24/12)�A6.
�\�t�g�n�t�v���Z�X�𗘗p�����ޗ��n���i17/13)�A7.
��炵��L���ɂ���ޗ��\���A��ÁA�����\�i30/0)�A8.
����i�m�\���̂̃f�U�C���Ɠ����i31/22)�A9.
�A���n�ޗ��̍ŋ߂̐i���i13/18)�A10. �R���d�r�ޗ��i11/14)�A11.
�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��i17/22)�A12.
���E�̈�Ƃ��ẴQ���̉Ȋw�ƍH�w�\����̉Ȋw�����[�E���Ȋw�܂Ł\�i15/28)�A13.
�X�p�b�^�@�ɂ�锖���쐻�Z�p�i21/19)�A14.
�C�I���H�w�𗘗p�����v�V�I�ޗ��i23/18)�A15.
�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�E�|�X�^�[�i0/58)�A���v582�i302/280�j�Ɛ����ł������B
�@���Êw�p�V���|�W�E���Ƃ��āA��3����{MRS�R����w�x���������\���2002�N10��5���i�y�j�J�ÁB���ʍu��2���A��ʍu��14���ł������B
�����O�̊֘A���@�ւƂ̘A���ɂ��ẮAIUMRS�̒���c�ɏo�Ȃ����ق�21���̍����V���|�W�E���ɋ��^�����B
���w�p�_�����ATransactions of the MRS-J, vol.27, Nos.2, 3, 4, vol.28, No.1�����s�����B���{MRS�j���[�X�Avol.14,
5���A8���A11���Avol.15, 2���̔N4��o�ł��S����ɔz�z�����B
����W�́A��14��N�������2003�N5��29��(��)18�F15���疢���Ȋw�Z�p�����c���ŊJ�ÁB��1��Վ������2002�N4��9��(��)11�F30����NIMS�ޗ�����������51�����ɂŊJ�ÁB��33���C�������2002�N4��9��(��)10�F00����NIMS�ޗ������������ŊJ�ÁB��34���C�������2002�N12��20��(��)14�F30���瓌���H�Ƒ�w�S�N�L�O�قɂĊJ�ÁB��35���C�������2003�N5��29��(��)16�F00���疢���Ȋw�Z�p����ɂĊJ�ÁB
�@2003�N3��31�����݂̉�����́A�l���579���i�ΑO�N��13����)�A�w�����53���i��7����)�A�@�l���12�Ёi��6�Ќ�)�A���_���5���i��1����)�A�����4���ł��B
�@��14���ƔN�x�̎��x�́A�������v17,361,276�~�A�x�o���v18,820,229�~�ŁA��1,458,953�~�̐Ԏ��ƂȂ�܂����B
����15���ƔN�x�i2003�N4��1���`2004�N3��31���j�̎��ƌv��ɂ����܂��ẮA�w�p�V���|�W�E���Ƃ��đ�8���i�ޗ����ۉ�c�iIUMRS-ICAM2003�j��2003�N10��8��(��)�`13��(��)�A�p�V�t�B�R���l��c�Z���^�[�ɂāA(�`)Nanotechnology
and Nanoscale Materials Processing: 9�V���|�W�E���G(�a)Electronic and Photonic
Materials and Devices�i9�V���|�W�E��)�G(�b)Advanced Materials for Environment and
Society�i9�V���|�W�E��)�G(�c)Modeling, Fabrication and Processing of Advanced
Materials with Novel Performance�i11�V���|�W�E���j; Forum on Materials Education
and Research Strategy; Workshop on Nanotechnology Networking and International Cooperation�̊J�Â��\�肳��Ă���B���O�̊֘A���@�ւƂ̘A�����͂𑱂���Ƌ���Transactions
of the Materials Research Society of Japan, ���{MRS�j���[�X�̒���I���s�A���{MRS�z�[���y�[�W�̉^�c�E�ێ����s���܂��B
����15���ƔN�x�̎��x�́A����13,795,000�~�A�x�o10,991,000�~�A���x���z2,804,000�~�̌����݂ł���܂��B�x�o�팸�y�щ�������A�����������ɓw�߂鏊���ł���܂��B����e�ʂ̐ϋɓI��x���A�䋦�͂����肢�v���܂��B
����15���ƔN�x�̖����͊P�Y�����E�ޗ������@�\���������ĔC���ꂽ�ق��A����s�̐��͎��̒ʂ�ƂȂ�܂����B
����F�P�Y�i�����E�ޗ������@�\�A�ĔC�j
������F���䎡�i����A�ĔC)�A�R�{���i����A�ĔC�j
����C�����F�g�����O�i���H��A�ĔC)�A�R�{�Lj�i����A�ĔC)�A���R�痢�i���A�ĔC)�A�R�c���i���喼�_�A�ĔC)�A����i������A�ĔC)�A��㖾�v�i���k��A�ĔC)�A�a�c�m�i���ދ@�\�A�ĔC)�A�����l�i�ʼnY�H��A�ĔC)�A���c�B��i�Z�C�R�[�G�v�\���A�ĔC)�A���c�h�d�i���{�����A�ĔC)�A�r�؍F��i����A�ĔC)�A�ɌF�טY�i�_�ސ�H��A�ĔC)�A���c�`�m�i�k��A�ĔC)�A���c���v�i���A�ĔC)�A�����v�i�ˈ����l��A�ĔC)�A�ݖ{�����i���ދ@�\�A�ĔC)�A�{�c�q�a�i�E�\�J��A�V�C)�A���{����i�R����A�V�C�j�A��؏~�j�i������A�ĔC)�A�ߌ��h�́i���H��A�ĔC)�A���c���Y�i����A�ĔC�j
�������F�y��`���i���H��A�ĔC)�A�����L���i�鋞��A�ĔC)�A�V��L��i�{�c�Z���A�ĔC)�A�����K�O�i�����Z�ȑ�A�ĔC)�A�����q�O�i�X�H���A�ĔC)�A�������I�i���H��A�ĔC)�A�k������i���A�ĔC)�A���Ζ��i����A�ĔC)�A����N�v�i��B��A�ĔC)�A��ԗ��j�i�����_�H��A�ĔC)�A�䉜�^��i�R����A�ĔC)�A�����g�j�i���H��A�V�C)�A�����O�B�i���k��A�V�C)�AManuel
E. Brito�i�Y�����j
����C�ږ�F���R���j�i�鋞�Ȋw��A�ĔC)�A�@�{�d�s�i���H�喼�_�A�ĔC)�A���J�쐳�i���喼�_�A�ĔC)�A���{���i���k�喼�_�A�ĔC)�A���؏r�X�i�L���H��A�ĔC�j
���ږ�F���q�O�Y�i���{�w�m�@�A�ĔC)�A�R��D�́i�P�C�G�X�s�[�A�ĔC�j
���Ď��F�R�c�b�F�i�鋞�Ȋw�喼�_�A�ĔC�j
�������ǁF
�Q�l�F�@�l����i�ΐ쓇�d���d�H�Ɗ�����ЁA�V�`�Y�����v������ЁA�V���{���c������ЁA����{�C���L���w�H�Ɗ�����ЁA���z�U�d������ЁA�����d�͊�����ЁA���ŃZ���~�b�N�X������ЁA�����@�튔����ЁA���{SGI������ЁA�O�ʍO�O�����ʊ�����ЁA������Ж{�c�Z�p�������A������Ѓ��R�[
��International
Conference on Advanced Materials: ICAM 2003
��ÁF���{MRS, International Union of Materials Research Societies
�����F2003�N10��8��(��)�`13��(��)
�ꏊ�F�p�V�t�B�R���l�i���l�݂ȂƂ݂炢�j
���e�F39�V���|�W�E���A�v���i���[�Z�b�V�����A�ޗ�����t�H�[�����A�W��������̍u���Ɗ�悪�\�肳��Ă��܂��B
�ڍׁFIUMRS-ICAM2003�����ǁAhttp://www.mrs-j.org/ICAM2003
�@Nanotechnology and Nanoscale Materials Processing (10�V���|�W�E��), Electronic
and Photonic Materials and Devices (��9), Advanced Materials for Environment and Society
(��9), Modeling, Fabrication and Processing of Advanced Materials (��11)�A��4����A39�V���|�W�E���ɑ��v2114���̔��\�ғo�^�����A�Q���҂͓��O�S�]���ȏ�ɒB�����B�I�����_�ƒ�����Collaboration�`�[���ADr.
Klaas de Groot of IsoTis NV, Professor FuZhai Cui of Tsinghua University��So~miya Award������ꂽ�B
�����{MRS���^�̌����
����w�ƉȊw���J�V���|�W�E���F21���I���J�����f�̐��E�\�V�ޗ��ƃN���[���G�l���M�[�V�X�e���\�A2003�N11��15�`16���A�_�ˍ��ۉ�c��A�₢���킹��F�A�h�X���[Tel:
03 -5925 -2840, info��adthree.com
���g����v�Z�ޗ��w�|��[�ƓW�]�|�A2003�N12��5���AJFE�X�`�[�������{�Љ�c���A���{�����w��֓��x���ATel:
03 -5734 -3142, hatumi��mtl.titech.ac.jp
��IUMRS�����o�[�̉
��2nd International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT
2003)&IUMRS-International Conference in Asia (ICA) 2003, 7 -12 December, 2003,
Singapore, http://www.mrs-j.org/ICAM2003
��First International Conference of the African Materials Research Society (MRS-Africa)
December 8 -11, 2003 -Johannesburg�\South Africa
��9th International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2004) April 12 -16,
2004, San Francisco, California, USA
��9th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2005) July 3 -8, 2005,
Singapore
���o�ňē�
Transactions of the Materials Research Society of Japan, vol.28, No.2, June, 209 -510,
2003�����s����܂����B�{���́A���e�_��2��̑��ɁA2002�N12��20�`21���ɊJ�Â��ꂽ��14����{MRS�w�p�V���|�W�E���̂�������A�uControl
of Structures, Morphologies, and Properties of Materials by Magnetic Fields�v23��A�uSoft
Solution Process�v26��A�uInnovative Materials Using Ion Technology�v25���ڂ���Ă��܂��B
�₢���킹��F���{MRS�����ǁAshimizu��sntt.or.jp
���g�s�b�N�X
�����{�w�p��c��7��22���V��ɓ��C��w������w���������̍��쐴����I�B����ɂ́A���{MRS��œƗ��@�l�����E�ޗ������@�\�������̊P�Y���A����c��w�@�w�������̉��\�ʌ��������܂����B���{�w�p��c�͐ݒu�`�Ԃ����I�o���@�Ȃǂ̉��v�𐭕{���狁�߂��Ă���B
�����c�@�l����c�i600 -8009���s�s������l��ʎ������������J�g��88�ԒnK.I.�l���r���A�d�b075
-255 -2688�j��2003�N��19�s�܂̎�҂����肵���B���̂��т̎�҂́u��[�Z�p����v�ōޗ��Ȋw�̕��삩��A�L�@���q�̎��ȑg�D���@���J�A�i�m�@�\�ޗ��̍\�z�ɑ傫�ȕϊv�������炵���A�����J�E�n�[�o�[�h��w�����AGeorge
McClelland Whitesides���́u�L�@���q�̎��ȑg�D���@�̊J��ƃi�m�ޗ��Ȋw�ւ̓W�J�v�ɑ��đ�����B������11��10���������s���ۉ�قōs����B
�@�z���C�g�T�C�Y�����́A��b�Ȋw���牞�p�A�����ċZ�p�܂Ō��ʂ������L������ɑ����āA�L�@���q�̓��ٓI���ȑg�D���𑽗l�ȉȊw�I�g�ݍ��킹�ƁA�O��I�ȕ������w�I�L�����N�^���[�[�V�������s�����Ƃɂ���āA�i�m�@�\�ޗ��̍\�z�ɑ傫�Ȋv�V�����A�ޗ��Ȋw�̐V��������̐i�W�ɑ���ȍv���������B
�@�z���C�g�T�C�Y�����̓A���J���`�I�[���������̊�ɂ悭�z�����邱�Ƃɒ��ڂ��āA���ȑg�D������P���q���iSAM�j���`������Z�p���J���A�W�J�����B���̋ɔ����̗L�@���q�̖��́A���݁A�L�@�i�m�e�N�m���W�[�̕���ł͕s���̍ޗ��ƂȂ��Ă���B�����SAM�Z�p�W�����A�L�@�̂��g�����~�N�����T�C�Y�̕��G�ȃp�^�[�j���O���\�ɂ����u�~�N���ڐG����@�v���Ă����B���̕��@�̓\�t�g���\�O���t�B�[�Ƃ��Ă�A�]����IC�����ɗp����ꂽ�����\�O���t�B�[�̂悤�ȍ����Ȑݔ��⍂�x�ȋZ�p��K�v�Ƃ����A�܂����l���̑傫���L�@���q��̕��q�Ȃǂ̃p�^�[�j���O�ɂ����p�ł��邱�Ƃ��番�q����Ƃ���������̂ŁA���̉��p�͌v��m��Ȃ��B
To the Overseas Members of MRS-J
��Research and Ken-Kyu�cp.1
Prof. Dr. Yotaro YAMAZAKI, Department of Materials
Engineering, Graduate School of Engineering, Tokyo Institute of Engineering
�@The English word of research which comes from �gsearch�h was translated into Japanese
long ago as �gken-kyu�h. The ken means �gpolish�h and the kyu means �gstudy
thoroughly�h or �gattain the summit of a mountain�h. We can find a large difference in
the meanings between the �gresearch�h and �gken-kyu�h. It is interesting to
investigate the origin of the discrepancy. It may be because the word was made in Europe
by the people who were not researcher, and was made in Japan by researchers who have pride
to a certain degree. We can discern the expectation of Japanese people to the academic
activity by thinking over those meanings of the words.
��Synthesis of metal-alkoxides by method of electrolysis�c�cp.2
Kazuki BABA, Research and Development Division, Kojundo
Chemical Laboratory Co., Ltd.
�@New synthesis method of metal-alkoxides by electrolysis has been investigated to obtain
highly pure metal-alkoxides. The metal-alkoxide is generated by electrolysis in alcohol
(for example, ethylalcohol in case of metal-ethoxide) electrolyte introducing hydrogen
chloride, applying target metal as anode and same metal or carbon as cathod. The
metal-alkoxide generated is extracted with solvent such as hexane, octane, toluen, after
neutralization treatment by NH3 gas. Finally highly pure metal-alkoxide can be obtained by
reduced pressure distillation.
��Toray Research Center, Inc. (TRC)�c�cp.4
Youichi NAKAYAMA, Manager, Research Planning Department,
TRC
�@Toray Research Center, Inc. (TRC) was founded in June 1978, as a wholly owned
subsidiary company of Toray Industries, Inc., with the guiding principle of �gcontributing
to the industrial world through advanced technologies�h. TRC has been providing customers
with technical support primarily for �gproblem solving�h in research, development and
manufacturing. This article presents various aspects of TRC's activity briefly from a
viewpoint of research department and quality assurance system.
��IUMRS-ICAM 2003�c�cp.7
�@The 8th International Conference of Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2003) including the
2nd Workshop on Nanotechnology Networking and International Cooperation was held from
October 8th to 13th, 2003, at the Pacifico Yokohama, in Yokohama. The conference was
organized by The Materials Research Society of Japan (MRS-J), sponsored by Nanotechnology
Researchers Network Center of Japan and supported by commemorative Organization for the
Japan World Exposition '70. Attendance of more than 2300 materials scientists and
engineers from all over Asia, the USA and Europe, the meeting and exposition is large
materials research event in Japan. It featured 2144 technical papers (oral 1259; poster
855) presented in 39 technical symposia and two FORUM on materials education and research
strategy. The Exposition, held in conjunction with the Conference, host international and
domestic companies in the materials industries. Proceedings will be published as a series
of the the Transactions of the Materials Society of Japan. The Conference was cofunded by
the 73 institutions and companies, and also supported by the following governments (MEXT,
METI and ME) and City of Yokohama.
��2003 SO~MIYA Award on International Collaboration�c�cp.7
�@The 2003 So~miya Award for International Collaboration in Materials Research was
awarded to a Dutch-Chinese research team led by Professors Klaas de Groot, IsoTis NV and
FuZhai Cui, Tsinghua University for their investigation of Biomimetic Calcium Phosphate
Composites. So��miya Award Ceremony and Lecture was held at the IUMRS-ICAM 2003, October
11, 2003 in Yokohama, Japan.
��Members in the News
�@Dr. Teruo Kishi, a president of the MRS-J and president of the National
Institute of Materials Science, was appointed as the vice-president of the Science Council
of Japan.
�ҏW��L
�@�@21���I�͂܂��܂���Љ�ɂȂ�A���낢��ȃA�C�f�B�A��m�������l�ݏo������ƌ����Ă���܂��B�܂��A������w���̓Ɨ��s���@�l���͎��ȐӔC�̊�Ɍl�̐��ʂ����߂�Љ�ƂȂ�O���[�o�������i��ł��Ă��܂��B�Y�w���̎�芪���Љ�ω��͏����̌����̂�����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��ƍl�����܂��B���ꂩ��̉Ȋw�Z�p�͂ǂ̂悤�Ȕ��W�̎d��������̂ł��낤���B21���I�ɂ�����}���ɔ��W���镪��͌��G���N�g���j�N�X�Z�p���l�����A���̋Z�p�̊�{�͓d�q�_�ƍޗ��Z�p���d�v�Ƃ���Ă���܂��B
�@�����̋Z�p�������I�ɔ�������ɂ́u�i�m�Z�p�v������܂��B����Ɋւ�鐢�E���V�����Y�Ɗ�Ղ����Ǝv���܂��B�u�i�m�Z�p�v�̈�ɂ����čޗ��A�����Z�p�A�V�ޗ������̓����Ƃ��ĕ����E���w�E�����I���ۂƐ����≞�p�Ɋւ��錤���͓d�q�_�A�ʎq�_���v������܂��BMRS-J�͊w�ې��E�ƍې����d�v�����āA���낢��Ȍ�������̉��f���̊�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ɋ������A�V�Z�p�n�o�����҂��Ă���܂��B�i��R����)