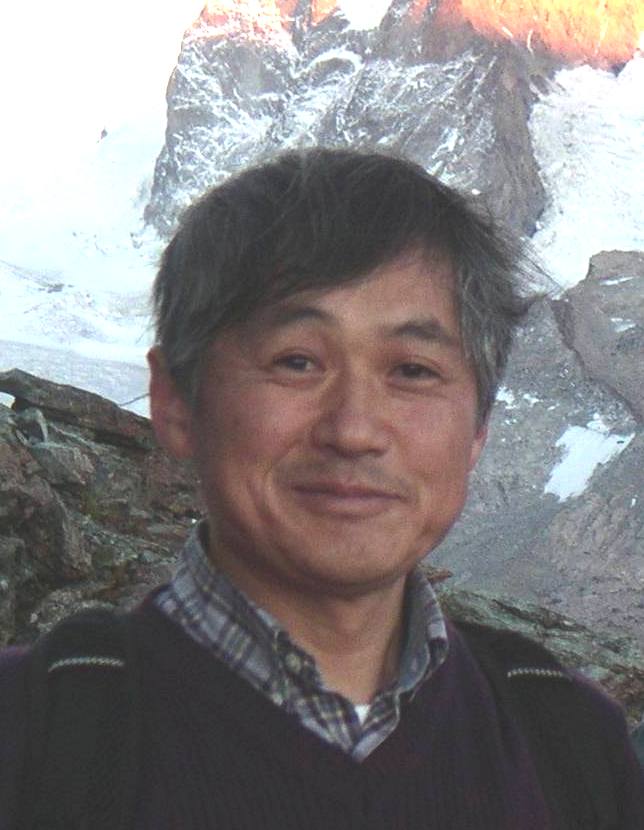
日本MRSニュース Vol.17 No.1 February 2005
マイクロ液体プロセスによる低エネルギー工業
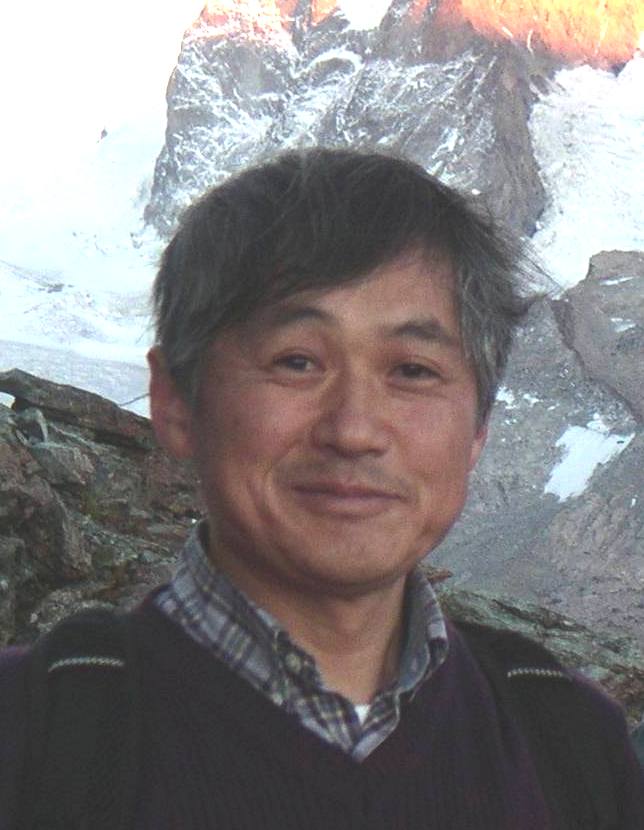
日本MRS副会長、セイコーエプソン株式会社理事(フェロー)・下 田 達 也
「マイクロ液体プロセス」という微細デバイスのための新しいプロセス技術にここ10年取り組んでいる。世間でインクジェット印刷法などと呼ばれているプロセスで、機能性液体から後加工無しに直接に電子デバイス等を作成する方法である。インクジェットプリンターの技術進歩は目覚しく、今では銀塩写真に匹敵する高品質の写真を印刷できるほどに発達してきている。その技術を微細デバイスに使ってみようと10年前考えたわけである。
私は、今から約11年前の1994年に研究開発分野を大きく換えた。この転換は必ずしも自分の意志では無い。しかしこのような業務命令による商売替えは会社では良く起こることと思う。それまでは、永久磁石を中心とした磁性材料と磁気応用の研究開発を行ってきたが、新しい分野は、それとは全く違う半導体、表示体関連分野であった。そこで驚いた。新しい分野の市場規模はそれまでの分野に較べ表示体では一桁大きく、半導体では二桁も大きい。使える研究開発予算はそれなりに増えたが、コンペチター会社の規模は途方もなく大きく強力になった。そして何よりも驚いたのは、研究開発に使う装置類が大変高額であることであった。それまでは、高額の装置といっても高々数千万円のオーダ。しかし、半導体、表示体用の装置は一台が5億円、10億円するものも珍しくはない。何でこんなに高いのだと、判を押す前に部下に尋ねると、部長(当時)はこの分野を知らないからでこの程度の値段は常識ですよ、と言うような顔をされてしまう。少し慣れてきてこの分野の技術をつぶさに見ていったところ、さらに驚かされる事実を知った。このようなハイテク分野では、いろんなパラメータが相当高度まで煮詰められていると思っていた。しかしどうだろう。薄膜を製造する真空装置はCVDにせよPVDにせよ、原料源から基板に堆積する材料の割合(歩留まり)は10%以下である。さらにフォトリソで削り取るので最後まで残る分は1%も無い! そしてフォトリソに用いられるレジストはスピンコートで塗られるので、それも高々2,3%程度の塗布効率である。結論として薄膜製造プロセス中の材料利用効率は押しなべて低く、高々数%であった。ハイテクは材料の利用効率に対しては全く考慮されていないことを知って驚いたのであった。同じようにエネルギーの利用効率を見ると、そこにも桁違いの改善の余地があるように思えた。また、装置の大きさ、値段、工場の大きさ、TAT(Turn
Around Time)においても同様に改善の余地が大いにありそうだと思えるようになった。
そこで考えたのが、真空装置やフォトリソグラフィーを使わないで、微細な電子デバイスを直接基板上に作成する方法であった。これにはインクジェットが大変良い出発点になった。インクジェットは4色から6色の異なった色材を吐出してきれいなカラー写真を印刷する。それではトランジスタをこのようにして描けないだろうかと考えた。トランジスタには、半導体材料、絶縁体材料、導体材料と2種類のドープ材料があればよい。カラーにすると5色である。このような動機から始めたのが、「マイクロ液体プロセス」であった。
実際に行ってみると、インクジェット技術は直径が20μm程度の大きさの微小液滴を精度良く作成し、ある程度の精度(±10μm程度)で基板上に着陸
させる技術であることが分った。液滴は着陸後に基板との接触角に応じて直径30~100μm程度に濡れ広がる。しかしこのままでは、ディスプレイ用、半導体用にははるかに精度的に及ばないことも分った。そこで考え出されたのが、表面エネルギーを利用してパターニング精度を上げる方法である。前もって基板上に撥液-親液パターンをつくっておくと、液体はエネルギーミニマムを実現するため自己組織的にパターニングされる(液体パターニング)。この方法により、1μm以下のアライメント精度が可能になりディスプレイ用のデバイス作成に道が拓けた。液体パターニングの後は何らかの手段で液体-固体変換(成膜)を行って目的の形状の固体薄膜を得る。最もありふれた方法は溶剤を乾燥させ固体にする方法であるが、溶媒を乾燥する際にある条件下では液滴の端がピニングされ液体内部で対流が生じる。その微小流は溶質を中心から端まで運ぶ、いわゆる「コーヒーのシミ」現象を引き起こす。この微小輸送現象は厄介な現象であるが、原理を理解して制御できるようになると、薄膜の厚みのプロフィールを任意にコントロールする手段になる。
このように微小液滴から所望の性質、寸法の固体薄膜を基板上の任意の位置に精度良く直接形成する新しい方法が開発された。この方法の要は微小液滴作成にこそインクジェットを用いるが全体のプロセスは微小液滴の挙動をうまくコントロールするところにある。そのような理由で我々はこの一連のプロセスにインクジェット法の上位概念として「マイクロ液体プロセス」という名をつけている。このプロセスを用いて今までに、液晶ディスプレイ用のカラーフィルター、有機ELディスプレイ、有機TFT、面発光レーザ用μ-レンズ等のデバイス、また金属バス配線、セラミックス薄膜、SiO2薄膜等のパターンニング薄膜を形成し、この技術の有効性を検証してきている。工業という視点からは、マイクロ液体プロセスは、製造エネルギーの低減、短工程化、工場のコンパクト化等を実現する有力手段の一つと思われる。
■第15回日本MRSシンポジウム報告
2004年12月23~24日、日本大学理工学部駿河台校舎(東京都千代田区)
本シンポジウムは、例年に比べ若干遅めの2004年12月23日(木)、24日(金)の2日間、東京・御茶ノ水にある、日本大学理工学部・駿河台校舎1号館で行われました。建物は2003年に立て直されたため、機器・設備は新しく充実しており、御茶ノ水駅から近いこともあって非常に好評であったように思います。シンポジウムは17のセッションからなり幅広い分野をカバーしており、日本MRSの理念「先進材料に関する科学・技術の専門家の横断的・学際的研究交流を通じて、その学術・応用研究および実用化の一層の発展を図る」をまさに再現していたと思います。口頭発表(招待講演含む)334件、ポスター発表324件、合計658件でありました。各セッションの発表の様子、トピックスなどは、チェアの皆様にまとめて頂いた以下の報告を参照してください。また、ご参加いただいた発表者各位、セッションチェアならびにシンポジウム企画・運営にあたられた皆様方にあらためて感謝を申し上げます。
さて、例年と同じく若手の優れた口頭発表・ポスター発表を対象とした奨励賞を選考しました。対象者353名の中から39名を選出しました。受賞者を一覧にして以下に示します。ご関係の皆様のご尽力に感謝の意を表すとともに、受賞者の皆様にお祝い申し上げます。
■奨励賞受賞者一覧
・Session A: A1-O05樋口透、A1-P02-M中野一機、A1-P09-B上野梨紗子、A1-P16-D保科拓也
・Session B: B1-S01-G加藤徳剛、B1-P09-M畑裕道
・Session C: C1-O06中西周次、C1-P14-D富永亮二郎、C1-P21-M北村哲
・Session D: D1-P04-D楠本洋介
・Session E: E1-O18菅野勉
・Session F: F2-O12山室佐益、F2-P10-M山田博久、F2-P13-D大西胤生
・Session G: G1-O10-M金子幸広、G2-P07-B新井涼太
・Session H: H1-O02 Nihan Kosku、H2-O13谷口雅樹、H2-P05加藤俊顕
・Session I: I1-P06-G石崎貴裕、I1-P17-G宇田津満
・Session J: J1-P01-D古賀智之、J1-P25-G永野修作、J1-P31-D三崎雅裕、J1-P35-M諸石順幸
・Session K: K2-O17許健司、K2-P02-M中田由彦
・Session L: L1-O08-D池田信之、L1-O11-G中森裕子
・Session M: M1-P02-B松本仁美、M1-P14-M吉本絵美
・Session N: N1-P04-G有永健二、N1-P17-M木下賢史
・Session O: O1-O16田中真悟、O2-O22-D君塚肇
・Session Q: Q2-P06-M山中善臣、Q2-P16-M村田賢紀、Q2-P39-G横山信吾、Q2-P44-G飯田泰広
▽Session A:ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料
招待講演(8件)、口頭発表(22件)、ポスター発表(17件)
本セッションでは、ドメイン構造をキーワードに、セラミックス、粉体、単結晶、薄膜といった材料の違いを超えて、理論から応用まで実に幅広い内容の講演が行われた。本セッションは、2001年、2002年につづき3回目であり、当初より広範囲なドメイン研究者の交流を目標に掲げ、実際それを達成してきた。本セッションのこの多様性は掛け値なく貴重であり、今後もこの方針を継続できればと思う。
具体的な内容として、まず様々なドメイン観察法が報告された。ドメイン観察法は、ここ数年で非常に有効なものが提案、実用化されてきており、本セッションでも軟X線レーザースペックル、X線トポグラフィー、SNOM、圧電応答顕微鏡、電場変調分光法、電子線ホログラフィー、TEMといった方法によるドメイン観察法が議論された。さらに、こういった手法によるドメイン観察結果と誘電特性、圧電特性、相転移挙動の関係についても活発に議論された。ドメインエンジニアリングという視点からは、電界、熱、光などを用いたドメイン構造の制御が報告された。特に圧電特性については、少なくとも単結晶では、ドメインサイズをコントロールすることにより圧電特性を強化できることがほぼ確実といえる段階となり、今後この知見のセラミックスや薄膜への展開が注目
される。その他にも、サイトエンジニアリングや傾斜型材料など、ミクロな材料設計、制御による新機能材料への野心的な取り組みも多数報告された。
今回、ドメイン構造という、すぐには製品開発につながらなさそうなテーマであるにもかかわらず、少なからず企業からの参加者を得ることができた。しかし、産学官の垣根をうち払って活発な議論の場とするには、さらなる企業からの参加者が得られるよう、より魅力的なセッションにしなければならない。なかなか捉えどころがないドメインをエンジニアリングするという方向が見えてきている中、企業との連携は、本セッションに求められる重要な使命であると考えている。
最後に、事務局をはじめ、本セッションにご協力いただいたすべての皆様にこの場を借りて謝意を表します。
(松田弘文(産総研)、沖野裕丈(防衛大学校))
▽Session B:有機超薄膜の作製・評価と応用―高度な分子配列・配向制御を目指して―
本セッションでは有機超薄膜の作製と構造・機能評価ならびにその応用を視野に入れ、分子配列・配向制御の視点から活発な討論が行われた。発表は招待講演4件、オーラル17件、ポスター9件の合計30件で、2日間にわたり行われた。口頭発表の会場では一般講演20分と比較的時間的余裕もあり、突っ込んだ討論がなされたと思う。
初日午前には、まず招待講演として早大理工の加藤徳剛氏が「水面上のメロシアニンJ会合体単分子膜に対する斜入射X線回折による構造解析の有効性」をアピールし、続いて4件の主としてJ会合体LB膜に着目した精力的な研究成果が発表された。午後のポスターセッションに引き続き、はじめに八瀬清志氏(産総研)は「摩擦転写法によるπ共役高分子の配向制御」と題する招待講演で新しい有機配向膜形成プロセスへの取り組みを熱く語った。さらに6件の主としてLB膜の電気伝導性や光機能性についての発表がなされた。
2日目、午前から午後にかけて7件の有機超薄膜形成法、電子・化学反応性、理論計算等の発表がなされた。最後に2件の招待講演、産総研の池上敬一による「有機超薄膜の分光学的評価における最小二乗法の新しい応用」と日大生産工の長谷川健先生による「仮想光概念による薄膜の構造異方性解析」では質疑応答も活発で、分光学的評価に関する質の高いディスカッションが行われた。
今回、奨励賞対象となった17件の中から、若手一般として加藤徳剛氏(早大理工)、学生から畑裕道君(日大理工)の2名が選ばれた。(山本 寛(日大理工))
▽Session C:自己組織化材料とその機能VI
招待講演(3件)、口頭発表(18件)、ポスター発表(25件)
本セッションでは、自己組織化をキーワードに、新材料の創製とそれらの構造制御・機能発現に関する口頭発表とポスター発表が行われた。今回で6回目を迎えたが、自己組織化を活用する材料研究の重要性はますます高まっている。その対象は、有機系、無機系、生物系、さらにその複合・集積系と多岐にわたる。新しい自己組織化の科学として、分子認識を活用したらせん状無機結晶の創製、電気化学振動を利用した金属格子・薄膜の形成、有機/無機複合体からなるセンシングプレートの構築、水素結合性分子による導電性ナノファイバーやキラル分子集合体の配向制御に関する研究などが注目を集めた。その他の研究発表においても、非常にレベルの高い議論が展開されていた。3件の招待講演は、東大・米澤氏の「金属ナノ粒子の合成とその応用」、慶大・今井氏の「高分子を用いた炭酸カルシウムの結晶化制御」、東大・芹澤氏の「固相ナノ空間におけるテンプレート高分子合成」という、いずれも最先端のホットな話題に関するものであり、研究背景を含めて大変わかりやすくご講演をしていただいた。
セッションの運営に関しては、トラブル等はなく、スムーズに行われた。最後に、事務局をはじめとして、セッションの開催にご協力いただいた皆様に深くお礼申し上げます。
(加藤隆史(東大院工))
▽Session D:暮らしを豊かにする材料―環境・エネルギー・医療・福祉―
招待講演(2件)、口頭発表(24件)、ポスター発表(12件)
参加者数50名
「暮らしを豊かにする材料」と題し、環境材料・医用材料を中心としたセッションも3回目を迎え、新たな参加者も増えつつある。今回は、環境とエネルギーの深い関わりを考慮し、副題に「エネルギー」も加え、招待講演として、岡本健一先生に「燃料電池用スルホン化ポリイミド系高分子電解質膜」、溝田忠人先生に「ゼオライト-水系ヒートポンプ蓄熱材」に関する基調講演をお願いした。講演の内訳は、環境浄化材料に関連する研究7件、医用材料に関する研究9件、エネルギー材料に関する研究7件、高分子膜・気体分離膜に関する研究8件、無機機能材料の合成と結晶成長に関する研究7件であり、活発な議論が行われた。21世紀に予想されるエネルギー・環境・経済の3Eトリレンマを解消するための新しい材料の開拓をめざし、日頃、異分野と思われている研究者が一同に会し、相互交流出来たことに大きな意味があった。(中山則昭(山口大工))
▽Session E:熱電変換材料―ナノ構造制御による高効率化―
本セッションでは、熱電変換材料の高効率化に関連する最近のトピックス(材料プロセッシング・デバイス・理論など)について29件の一般口頭講演があり、常時30名以上(ピーク時43名)の聴衆が集まり終日活発な議論が行われた。酸化物系材料としては、ZnO(九大)、AgSbO3(千葉大)やSrTiO3(名大、阪大)などのn型酸化物材料、Ca-Co-O系(東北大、産総研、名大など)のp型酸化物材料の無次元性能指数ZTが、ナノレベルの微細構造制御、結晶配向制御や部分元素置換などにより着実に金属間化合物系材料の数値に近づきつつあり、高温でも安定な熱電変換材料として今後さらなる性能向上が期待できる。一方、ナノレベルでの微細構造制御やドーピング制御により、ホイスラー(阪大)やTe系化合物(阪大)、クラスレート化合物(山口大)などの材料も着実に性能が向上してきた。物性物理解析に基づくナノ構造制御などの材料プロセッシングにより熱電変換材料の変換効率は着実に向上してきた結果といえよう。その他、発表件数は少なかったが、中部大グループから、ペルチェ効果を利用して熱漏れを低減するペルチェ電流リード(PCL)をヘリウムフリー超伝導マグネットに適用した報告があり興味を引いた。また、スパッタリング法によりAxCoO2(A=Ca,Sr)およびCa3Co4O9エピタキシャル薄膜の結晶配向制御に成功し、その熱電特性の異方性を報告した菅野勉氏(松下先端技研)が講演奨励賞に選ばれた。(河本邦人(兵庫県立大院))
▽Session F:ファブリケーションを指向したナノスケール構造体の作製と性質
―ナノ粒子からミクロ組織体まで―
口頭発表14(内、招待講演2件)、ポスター発表20件の合計34件の発表を1日で行うかなりタイトな日程となった。参加者は発表者数に若干上乗せする50名程度で他会場からの出席者も見られ、出入りのある講演会となった。ナノテクノロジーの影響を受けタイトル中にまたはセッション説明にナノを冠したセッションが多かったための影響と思われる。内容はナノスケールの実触媒から始まりナノ物質系の電子状態理論、光電子分光法やラマン分光、トンネル分光法によるナノマテリアルの評価、磁性薄膜を意識した鉄や鉄合金系のナノ粒子など多彩であるが、やはりMRSの会議であり、物質、試料の作製法に関する報告が多かった。物質の観点からは金属、無機材料はもちろんのこととして、有機分子、ポリマーや生体物質など広範な拡がりを見せていることが印象的であった。本セッションとしては今後ともナノスケール物質に焦点を合わせたセッションを本学会内に維持していきたいとオーガナイザー一同の感想である。招待講演の内、1件は奥山喜久夫教授による「ナノ粒子の合成と自己組織化によるポーラス構造体の創製」で工業規模によるシングルナノ粒子を実際にキログラム~トンスケールで製造する話には聴衆が圧倒されていたようである。また他の1件は田中章順教授による「光電子分光で見た表面修飾金属ナノ粒子の量子物性」であり、金属/有機物界面での電荷の移動という真にナノ領域の先端研究の話は難しかった会員も多かったのではなかろうか。
口頭発表は全員が液晶プロジェクターを使用した発表でありトラブルが心配されたが、さしたる不都合もなく無事終了した。OHP使用に比較して圧倒的にプリゼンテーション枚数が多く、質疑応答時における図表示も効果的であり、今後はこの発表形態が主流になると思われる。(木村啓作(兵庫県立大院))
▽Session G:次世代電子デバイスのための誘電体薄膜技術
本セッションでは、次世代電子デバイスのための誘電体技術をテーマに高誘電率絶縁膜や強誘電体薄膜に関する材料・界面制御技術について、招待講演4件と一般講演27件が報告された。
Sub-100nm CMOS用のhigh-k絶縁体技術に関しては、ZrO2、HfO2あるいはHfAlOxと半導体との界面において生じるsub-nmスケールでの界面現象に関して活発な議論がなされた。一つの原子の移動によって生じる分子軌道や分極状態の変化など原子レベルでの議論が必須となり、理論計算との整合も重要となってきた。また、界面反応に関して議論するだけでなく、その誘電特性、デバイス特性さらにデバイスの信頼性との関係が詳細に議論されたところが大きな特徴であったように思われる。その最も顕著な例が鳥居氏(半導体テクノロジーズ)の招待講演であった。HfO2系絶縁膜の欠陥準位やその構造安定性を理論的に求め、そのデバイス特性との相関について議論するとともにデバイスの信頼性やその劣化の機構に関して詳細な議論がなされた。また、界面現象を理解するだけでなく、新しい界面制御技術も報告された。村岡氏(東芝)の招待講演では、界面劣化の抑制方法としてHeプロセスが提唱され、半導体/high-k界面におけるSiO2やシリサイドの形成を抑制する効果があることが示された。そのほか、今後重要となる電極との界面に関しても、NiGeなどの新しい材料の提案がなされた。
次世代のメモリデバイスとして、強誘電体メモリの現状に関する招待講演が大谷氏(富士通)からなされた。低消費電力であるという大きな特徴を背景に少しずつシェアをのばしてきており、特に携帯機器やRF-IC
tag、ICカードへの応用や論理回路との一体化などへの期待と集積化への問題点が指摘された。強誘電体メモリの集積化を進めるうえで重要となる強誘電体ゲートトランジスタに関して、半導体/強誘電体界面の電気的性質を評価するために、いくつかの新規な方法が提唱された。また、記憶保持特性に影響を及ぼす諸因子に関して様々な角度から議論された。そのほかにもいくつかの新規なメモリデバイスが報告された。長教授(東北大)が招待講演で報告した、非線形誘電率顕微鏡を用いたTbits/inch2以上の記憶密度を有する超強誘電体メモリは特に注目を集めた。強誘電体/圧電半導体界面を用いた新規なトランジスタなども提唱され、この分野の裾野が大きく広がってきたことを認識させられた。(財満鎭明(名古屋大院工))
▽Session H:先端プラズマ技術が拓くナノマテリアルズのフロンティア
本セッションでは、プラズマを用いたナノマテリアルプロセスをリードしている招待講演者10人(基調講演3人)の講演と58件の一般講演を基に、微結晶Si、ナノ結晶ダイヤモンド、c-BN、カーボンナノチューブなどの機能性ナノ材料の合成、その大面積形成や生態模擬プロセスをはじめとして、大気圧非平衡プラズマやマイクロプラズマ、ナノプラズマによる表面改質、機能性材料の超高速合成に関する先端応用技術が2日間に渡って紹介された。プラズマの材料プロセスに関してこれほどまとまったプログラムをアレンジできることは非常に稀であるため、300人収容のホールが連日多くの参加者でにぎわった。
特に、基調講演として講演した渡辺征夫教授(九州大学)の長年に渡って積み重ねられたシリコン微粒子の研究には心を打たれた。さらに、大気圧プラズマプロセス技術の生みの親である岡崎幸子名誉教授(上智大)は、壇上から参加者に研究者としての情熱を呼びかけられ、多くの参加者の感動を誘うものであった。岡崎先生の講演は、先端技術の紹介よりもむしろ普段の学会では、伺うことができない生の声、研究に対する姿勢を経験を基にして熱演され、基調講演として素晴らしいものであった。小松正二郎(物質・材料機構)は、独自の手法で新規ナノBN材料の開発に成功し、新しい材料の創成という点で興味深い講演であった。プラズマ技術は、材料プロセスやデバイス作製におけるキープロセスを担っており、今後は、日本MRS学術シンポジウムにおいて、プラズマが拓く最先端技術に関するセッションを継続して開催していくことが期待されている。(堀 勝(名古屋大院工))
▽Session I:ナノ構造と機能発現
「ナノ構造と機能発現」では中村智信(物質・材料機構)、米澤 徹(東大)、藤田大介(物質・材料機構)、齋藤永宏(名大)をチェアとし、「ナノ領域で高度に物質を制御し、新たな機能を物質に付与する」ことを主眼とした研究発表およびディスカッションが行われた。
招待講演については、「Mass Production of High-quality Single-wall Carbon
Nanotubes by Electric-arc Technique」(名城大学)安藤義則先生、「A molecular
recognition ion gating membrane and its multi-functions」(東大)山口猛央先生、Conversion
of a Cement Ingredient to Electro-active Material Utilizing Nanostructure」(東工大)細野秀雄先生の3人の方にお願いした。各講演とも、ナノ空間を自在に操り、材料への構造、機能の付与を実現した研究であった。また、一般講演およびポスター発表においても、レベルの高い講演が数多く見られた。若手研究者の中から選ばれる第15回日本MRS学術シンポジウム学術講演奨励賞には、石崎貴裕氏(名大)「原子間力顕微鏡による水素終端化シリコン上への金属の直接描画とその応用」、宇田津満氏(東工大)「中空ニッケル-リンマイクロファイバーの形態制御」の2件が当セッションより選出された。
本セッションでは、「ナノ」テクノロジーが、機能性材料を創製する真のツールとして利用していくうえでいくらかのマイルストーンを提示することができた。関係者各位、参加者各位の研究とその熱意にチェア一同より心をこめて感謝の意を表したい。(齋藤永宏(名古屋大院工))
▽Session J:次元規制高分子ナノ材料の構造制御と動的機能
高分子化合物はその大きな分子間力により、1次元の高分子鎖が集まり、3次元の高分子材料(物質)として使用されてきている。次世代の高分子材料設計やナノ材料の分野では、単に3次元的に形成される材料作成の「バルク材料科学」の概念でなく、次元性を意識し、一つ低い次元を精密に制御して、目的次元の材料を創製する次元規制材料の概念が求められている。しかし、その取り組みは必ずしも十分と言えない。そこで、今回の日本MRS学術シンポジウムではセッションJ「次元規制高分子ナノ材料の構造制御と動的機能」をオーガナイズした。本セッションでは4件の招待講演、15件の口頭発表、38件のポスター発表が行われた。一日目は主として「形状規制高分子鎖の合成」、「次元規制高分子組織体の自在構築」に関する招待講演と口頭発表が行われた。招待講演では高田十志和教授(東工大院理工)により「新しいポリロタキサンゲルの構築とトポロジー変化に基づく可逆的ポリマーネットワーク形成」、宮下徳治教授(東北大多元研)により「高分子ナノシートの自在集積とナノデバイス創製」に関する最新の研究成果が報告され、口頭発表もあわせて活発な議論が行われた。一日目の夕方はポスターセッションが行われ、若手を中心に活発な研究討議が懇親会直前まで続いた。二日目の午前中は「次元規制場における動的機能の解析」、午後は「多様な次元における構造・物性解析」に関する招待講演と口頭発表が行われた。二日目の午前中は木村俊作教授(京大院工)による「ヘリックスペプチドを用いたベクトル的長距離電子移動」、午後は陣内浩司助教授(京都工繊大繊維)による「透過型電子線トモグラフィー法による次元規制ナノ高分子の自己秩序化過程と構造」に関する招待講演が行われ、口頭発表も含めて活発な質疑応答が行われた。本セッションでは6件の口頭発表、31件のポスター発表を奨励賞の候補対象として10名の審査員により審査を行った。厳正に審査を行い、諸石順幸氏(筑波大物質工)、古賀智之氏(九大院工)、三崎雅裕氏(神戸大院自然)、永野修作氏(名大院工)の4名を奨励賞に選定した。(高原淳(九大先導物質化学研))
▽Session K:イオンビームを利用した革新的材料
参加者数:50名、口頭発表(18件)、ポスター発表(13件)
イオンビームを利用した技術は、半世紀近くの間に、材料科学の分野において、分析応用から材料創製に亘り著しい発展を遂げ、常に新技術の旗手として期待されてきた。イオンビームを用いた材料創製技術には、非平衡性や空間制御性等多くの特徴があるが、近年は競合する諸技術が現れてきた。本セッションでは、イオン工学的手法を用いたナノ材料、非平衡材料、バイオ材料等新材料の研究、あるいは新しいイオンビーム利用技術等を対象とし、革新的な材料技術を志向する研究発表を募り、横断的・学際的交流を行った。
発表論文は、イオン種については、大強度パルスイオン、高エネルギー重イオン、プラズマイオン、アークイオン、負イオン等、手法としては、イオン注入、プラズマ、PBII、イオンビーム蒸着、イオンビームスパッタリング、パルスレーザーの多様な技術にわたり、材料系については、C系(DLC膜、炭素膜)、合金系(Ti/TiC,
Fe/Si, ステンレス)、ナノ粒子系(純金属、Cu2O)、超伝導材料(YBCO,Bi2201,MgB2)、酸化膜(ITO,
ZnO)、ポリマー系(ポリイミド)、生体材料(タンパク質)等、新材料が勢揃いした感があった。様々な分野、領域でイオンビームを利用した技術の開発が進められていることを示すものである。
今回のセッションでは、マスターコースの学生の発表が非常に多く、また、ポスターセッションでの議論も予定時間を超過してまで続くなど、活気のあるシンポジウムとなった。しかし、一部の発表者に、発表内容に関する理解度、考察がやや不十分なものが見受けられたのが残念であった。(八井 浄(長岡技科大))
▽Session L:次世代エコマテリアル―環境調和型高機能エネルギー材料―
セッションLは「次世代エコマテリアル―環境調和型高機能エネルギー材料―」と題して、燃料電池・二次電池を始めとするクリーンエネルギー関連機器、デバイスで用いられる各種材料、すなわち環境調和型高機能エネルギー材料についての専門家を結集して、世界規模のエネルギー・資源需要の増大に対応するために、エネルギー供給、資源の利用等に対する画期的な技術の革新とそのための革新的な材料について議論の場とすることを目指して開催された。
「次世代エコマテリアルとは何か」という講演で原田幸明・物質・材料研究機構エコマテリアル研究センター長がセッションの口火を切った。21世紀の社会を持続的に発展させるためには、エネルギー材料の画期的な高性能化を、環境負荷を上げることなく達成する必要があるという内容に、すかさず参加者から、「材料研究者はひたすら高性能化を目指している。今の話の重要性はよく理解できる。普段、次世代エコマテリアルという考え方に接する機会はないので、今回の発表会では、貴重な講演を聞く機会が得られて良かった」という声が出た。このコメントが出た時点で本セッション企画が成功であったと言えよう。
全体として講演は、口頭とポスターを合わせて34件。内訳は、LCA等分析関係が6件、燃料電池関係がSOFC,
PEFCを合わせて6件、水素吸蔵材料・分離膜が合わせて13件、熱電材料が3件、太陽電池が2件、新カーボン材料が2件、リチウムイオン電池が2件であり、バラエティーに富むものであった。若手の発表が多く、また異分野間ゆえに素朴ながら本質的な質問が多く見られ、大変有意義な議論の場を提供できた。(西村睦(物質・材料研究機構))
▽Session M:ソフト・ナノ・マルチコンポーネントが織りなす多様性―横断的な展開を目指して―
セッションMでは、ナノレベルでの分子構造や分子間相互作用の変化等を利用して働くソフトナノ物質の高次機能構造体の構築とその物性・機能、さらにその利用に係わる研究を中心に口頭およびポスターで約40件発表があった。招待講演、依頼講演はそれぞれ大阪市立大学大学院の西成勝好先生に「シゾフィラン・キシログルカンのゲル化のレオロジー」、東京工業大学大学院の中野義夫先生に「ゲル触媒の創製」でご講演頂いた。今年度の特徴として、循環型社会の構築を目標とする、環境負荷の少ない環境適応性や制御可能な複合機能が求められる「21世紀型材料」構築のために必要な、ソフトナノ物質の解析・制御およびその原理を活用したソフトナノマシンの構築と利用に関する研究発表が多かった。活発な議論が交わされ、特にポスター発表ではコアタイムを過ぎ、懇親会がはじまっても活発な議論が行われていたのが印象的であった。(安中雅彦(九大院理学研究院化学部門))
▽Session N:生物資源利用技術の最近の進歩
1. 総論
昨年の15回シンポジウムは、お蔭様で、例年を上回る規模で成功裏に開催することができました。これもひとえに、皆様のご協力とご尽力の賜物と、心より御礼申し上げます。今年も当セッションでは「生物資源の有効利用、リサイクル、新素材の開発や評価技術、ナノオーダーでの高機能利用法等」を中心に最近の進歩について討論してまいります。今年もよろしくお願いします。
2. 招待講演
岡見吉郎先生の「微生物細胞膜から『覗いて見た』環境制御バイオテクノロジー」では、微生物の見方が変わる講演でした。魅力的で役に立つ微生物で、目から鱗が落ちたような刺激的な話題提供でした。山本忠道先生の「無公害型リンゴ産業の構築をめざして」では、リンゴの身近な話題から最先端の活用まで幅広い講演でした。我が家のリンゴの食べ方から変わりました。
3. オーラルセッション
朝9時から3時半過ぎまで、分単位のスケジュールにもかかわらず、十分な発表と討議が出来ました。白熱して時間超過が多々ありましたが、発表者と聞き手が一体となった充実した発表になりました。しかし、パソコンの調子が悪く何度か中断をしてしまいご迷惑をかけました。すぐにアフレコで対応したり、修理で集まって対応して頂き、優秀な方々が集まっている事を改めて実感しました。
4. ポスターセッション
3時半から6時近くまで、ポスター掲載後は広々としていましたが、発表が始まった途端にすれ違いも出来なくなりました。質問も討論も多く、休む時間がないのではと心配するほどでした。発表者の方はご苦労様でした。ポスターのデザインも内容も良く苦労が分かりました。しかし、板のサイズを誤っていて、ご迷惑をおかけしました。次回は事前検証します。
5. 奨励賞
研究内容も発表姿勢も甲乙付けがたい優秀な発表ばかりでした。厳正なる審査のうえ、P04有永健二(熊本大工)、P17木下賢史(東京工芸大院工)の2名とします。僅差だった、P14中村勝俊(神奈川大理)、P18小笠原康雄(弘前大地域)の2名の方に審査委員特別賞を贈ります。(岡部敏広(青森県工業総合研)、辻純一郎(ポリテクセンター群馬))
▽Session O:計算材料科学の最近の進歩
基礎的な物性の理解と新機能の創成、効率的な材料設計やプロセス設計を目指して、計算機モデリングを活用した材料研究の重要性がますます増大している。その対象も、従来のバルク材料から、表面、界面、ナノ材料へと広がるとともに、金属ガラス、触媒、燃料電池、などの機能特性評価へと大きな展開を見せている。今回のシンポジウムでは、これらのトピックスに重点的をおきつつ、その基盤となる計算材料科学の基礎から応用にわたる最近の話題を広く集めることにした。12月23~24日の2日間で33件の発表(口頭:26件、ポスター:7件)が行われた。「組織形成、フェーズフィールド法」のセッションでは、効率的な材料設計やプロセス設計の基礎手法として注目されているフェーズフィールド法による組織形成モデリングが使える状況になりつつあることが示された。「金属ガラス」のセッションは、「金属ガラスの材料科学」の確立を目指した科研費特定領域研究の計算科学担当班における最新の成果発表として企画されたもので、新材料の開発へ向けた実験と計算科学の連携が進みつつあることが分かった。「エネルギー環境材料、機能材料」のセッションでは、産総研の池庄司氏による招待講演「電極反応の観点からみた燃料電池用材料のシミュレーション」が行われ、NEDOの燃料電池開発プロジェクトにおける計算科学アプローチの最前線が紹介された。本セッションでは相転移、酸化、拡散、磁性などの第一原理計算に関する報告がなされ、構造安定性評価から機能特性の解析へと進展している状況が分かった。また、「機械的性質、新計算手法」のセッションでは、分子動力学法による機械的性質の解析、電荷移動原子間ポテンシャルの開発、第一原理計算プログラムの並列化などに関する報告が行われた。計算材料科学に関する研究発表は、機械、化学、物理、材料、金属などの各分野ごとに行われており、異分野間の交流の機会はそれほど多くないのが現状である。MRS-Jのシンポジウムは、このような異分野の計算科学研究者が一同に会して交流し情報交換する場として最適であり、計算材料科学分野の更なる活性化に繋がると思われる。最後に、36才未満の若手研究者を対象とした「若手奨励賞」の受賞者として、君塚肇氏(大阪大学大学院、講演「Atomistic
studies on high-temperature elasticity and auxectic behavior in SiO2 polymorphs」)と田中真悟氏(産総研、発表「Ab
initio calculations of Si-rich 6H-SiC(0001●)2●×2 surface structure
and its oxidation process」)の2名が選ばれたことを報告して本セッションの総括とする。(小野寺秀博(物質・材料機構))
▽Session P:エアロゾルデポジション法の現状とその展開
セッションPは、産業技術総合研究所で開発されたエアロゾルデポジション法(AD法)という、一つのプロセスにフォーカスを当てたセッションであった。AD法は、数ミクロン以上の厚さのセラミックス膜を熱処理なしに作成できるため、これまでにないアプリケーションが期待されている。特に、電子セラミックスへの応用が期待され、現在NEDOのナノテクロノジプログラムにおいて、「ナノレベル電子セラミクス低温成形・集積化技術」プロジェクトが現在進行中である。本セッションは、このプロジェクトのワークショップを兼ね、その成果発表を中心に行われた。
AD法の応用として、電波吸収体などのための磁性材料への応用、高周波デバイスなどのための誘電体材料への応用、電気光学効果を利用した光学デバイスへの応用、圧電材料に適用して、アクチュエータやスキャナや光スイッチなどを目指した、研究発表がなされた。
また、AD法の基礎や、プロセスの高度化を目指す研究発表もなされ、AD法を想定した分子動力学シミュレーションや、粉体処理、粉体の機械物性計測など、プロセスメカニズムの解明をめざした研究や、イットリア、窒化アルミニウム、YIG、酸化チタンなど、様々な組成の成膜やその特性が紹介された。プロセスの高度化については、おもにAD膜の圧電特性の向上のための、レーザー処理などの発表がなされた。
AD法は、新規なプロセスではあるが、他のプロセスでは困難であった、厚膜の作成が可能である事や熱処理が必要なく基板を広く選択できるなどユニークな特徴をもつことから、幅広い応用が期待されており注目度が高く、このセッションは1プロセスだけのセッションにもかかわらず、会場においては、常に50~70名程度の聴衆があった。(明渡純(産総研先進製造プロセス研究部門))
▽Session Q:マテリアルズ・フロンティア・ポスター
本セッションでは、金属、半導体、無機、有機の全ての材料とそれらの複合材料に関する新しい合成法、優れた特性を有する材料の開発や実用化の展開についてのポスターによる研究発表が行われた。発表件数は47件であった。発表者は学部学生が4名、修士課程の学生が21名、博士課程の学生が7名、一般が15名であった。例年と同様に学生が多かったが、活発な討論が行われた。ただ、種々の都合で3階と4階の二箇所に分かれて同時に開催されたため、他の階の雰囲気を味わえなかった人もあったようだ。
奨励賞の対象者は38名で、対象者1名当たり3名の審査員が審査するので、全体で12名の審査員による審査が行われた。1人の審査員は9~10のポスターを審査した。本セッションではポスターのコア時間を他のセッションより多く取って1時間半としたが、時間内に9~10のポスターを見て、説明を聞き、評価するのは大変な作業であった。特に、ポスターのレベルは高く、よく洗練された説明をされるので、甲乙つけがたい発表が多かった。最終的には4名の方に奨励賞が授与されたが、多くの方々が良いポスター発表をなされていた。
最後にチェアを代表して、発表者の方、審査の先生方、その他の参加者などの方々に感謝したい。(伊熊泰郎(神奈川工科大学))

写真:ポスターセッションの様子
■IUMRS-ICA2004報告
日本MRS副会長、日本大学理工学部教授 山 本 寛

ICA2004は台湾、新竹のIndustrial Technology Research Institute(ITRI)にて開催された。会議は11月16日~18日の3日間であったが、2日目からは同じ会場にて中国材料学会も同時開催された。
初日、チェアマンのDr. Jong-Min Liuのオープニング挨拶、ITRI所長、Dr. Johnsee
Leeの挨拶に続き、AUO社の代表がプレナリートークを行った。台湾において急激に立ち上がるディスプレイ産業のトップとして、液晶、有機ELを取り上げながらの自信に溢れる語り口が印象的であった。
主催者からは13ヵ国、500名以上の参加者があったと報告されたが、会場は比較的ゆったりとしていた。我が国からの参加者はやや少なく、30名程度であったろう。次の10セッションに対して、全登録論文件数は381編にのぼった。セッション名を概観するとナノマテリアル一色の感がある。
・Science and Technology of Nanomaterials
・Nanoscale Surface Science
・Nanoscale Imaging and Characterization
・Nanostructured Materials in Alternative Energy Devices
・Nanomagnetism and Spintronics
・New Materials for Electronic and Photonic Devices
・Materials for Flat Panel Display
・Hybrid and Soft Materials
・Theory, Modeling and Simulation
・Education Program of Nanomaterials
新竹市は台湾の科学技術を支える研究センターであるIRTIをはじめ、清華大学や交通大学といった台湾を代表する優れた研究者・学生が集まる活気溢れる学園都市である。急激に研究者達が集まり、ここ十数年で人口は倍増し、一部インフラストラクチュアの遅れも指摘されているそうである。
2日目の夜、会場から少し離れたホテルでバンケットが開催された。十数テーブル、百名以上の参加者が集まった。IRTIの伝統音楽や奇術の同好会メンバーによるアトラクションで盛り上がり、アットホームで和やかな雰囲気であった。
会議開催中、IUMRSのアジア代表メンバーの会議も開かれた。今後のアジア地区のMRSメンバー間の活発な活動へ向けて、幾つかの提言と具体的な施策について討議がなされた。この会議において、次回ICA2006年は韓国で開催されることが承認された。我が国からの多くの参加者が集まるように、当学会からも今後積極的に呼びかけて行きたいと思っている。また、会員の皆様からの積極的なセッション等への提案も歓迎しているので、本学会へお問合わせ頂ければ幸いである。
■IUMRSメンバーの会合
◇3rd International Conference on Materials for Advanced Technology (ICMAT2005)&9th
International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM2005), July 3-8,
2005, Singapore、連絡先 www.mrs.org.sgまたはchowdari@imre.a-star.edu.sg
■会員動静
東京大学生産技術研究所・山本良一教授はエコデザイン(環境適合設計)への長年の貢献に対して2004年9月にベルリン市にてElectronics
Goes Green Award 2004を受賞されました。山本教授はまた日本環境効率フォーラム、日本LCA学会の初代会長に就任されました。
To the Overseas Members of MRS-J
■ Low Energy Industry Using Micro-Liquid Process…p.1
Dr. Tatsuya SHIMODA, Vice President of the MRS-J, Fellow, Director, Technology
Platform Research Center, Seiko Epson Corporation.
■Report of the 15th Annual Symposium of the MRS-J …p.2
■Report of IUMRS-ICA2004…p.7
Prof. Dr. Hiroshi YAMAMOTO, Vice President of the MRS-J, Nihon Univ.
編集後記
この後記が掲載されたということは、第15回日本MRSシンポジウムが無事に幕をおろしたことでもあり、ホッと胸を撫で下ろしています。今回の会場は日本大学理工学部であったため、現地責任者として企画運営に関わりました。また、セッションBの連絡チェアならびにニュース編集委員として本号発行に携わりました。我ながらMRS-Jにどっぷりつかっているように感じます。これからも微力ではありますが、本学会のお手伝いが出来ればと思っています。さて、科学技術の横断的学術交流がますます重要となるこの時代にあって、MRS-Jシンポジウムは非常に有用な情報を与えてくれます。我々の研究室では、超伝導・ディスプレイ・ナノデバイスといった分野をターゲットにしており、材料もフラーレン、ナノチューブ、フタロシアニンなどの有機物、磁性酸化物、超伝導酸化物などの無機物を扱っています。作製プロセスも真空蒸着からウェット法まで様々です。このように手広く研究を行っていると思わぬところで手法・技術の交換が可能となり、思った以上に研究の展開に効果的な場合があります。同じことがMRS-Jシンポジウムの横断的学術交流でも言えるように思います。これからもさらに有益で面白いセッションからなる学術シンポジウムとなって欲しいと願っています。(岩田展幸)