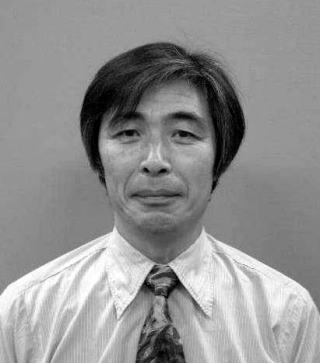
�Y�ƋZ�p�����������G�l���M�[�Z�p�������呍�����������R���d�r�O���[�v���[�_�[�@�@����@����
���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.18 No.1 February 2006
�M�͊w�͍ޗ��Ȋw�̋��ʌ���
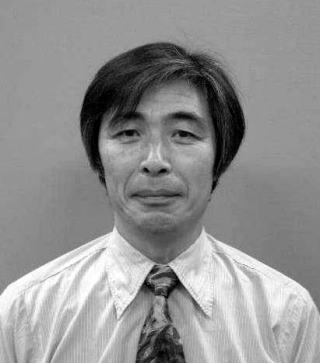
�Y�ƋZ�p�����������G�l���M�[�Z�p�������呍�����������R���d�r�O���[�v���[�_�[�@�@����@����
�@��������b�������߂Đ\����Ȃ����A2000�N�ɉȊw�Z�p�����܂��A2002�N��The
Electrochemical Society High Temperature Materials Division ����Outstanding
Achievement Award�Ղ������ɁA���������ǂ��ė������̂��U��Ԃ�A�ǂ̂悤�ȍޗ��Ȋw�̓W�J�����肦��̂�������l����@����B���̂Ƃ��̎v���̈�[�ł������L���Ă݂悤�Ǝv���B
�@�Ȋw�Z�p�����܂͔M�͊w�f�[�^�x�[�X�Ɋւ��Ă�������̂ŁA�M�͊w�f�[�^��@���Ɏg�����ɂ��Ďv�������炵���B�M�͊w�I�����������I�Ɍ��߂�w��̌n�����w�M�͊w�Ƃ����B�M�͊w���͏�ԁi�|�e���V�����j���Ƃ��Ē�`����A���̒l�����肷��ɂ́A�Q��ԊԂ̍��Ƃ��čs���K�v������B���̂��߁A���w�M�͊w�ł́A�l����Ɏ��������邱�Ƃ����A���̃f�[�^�Ƃ̐����������邩�ǂ����̕����d�v�ŏ�ɋᖡ���ׂ��_�Ƃ����B��J���������ɂ͑��l�i�]���ҁj���當��i���ȕ]���Ƃ͈Ⴄ�]���j��������B���̃X�^�C���͍��ł͂͂��Ȃ��B�����̗L�͂Ȍ���������p�҂�{�����邱�ƂȂ������Ă������B��Ɏc���ꂽ�M�͊w�f�[�^�̎R������B���̃f�[�^�i�����f�[�^����łȂ��]���l���܂߂āj�Q�͕�̎R�ł���B���̂܂܂ɂ��Ēu���ɂ͂��������Ȃ��B�M�͊w�v�Z�����ׂ��l�ɗǎ��̃f�[�^����邱�Ƃ�ڎw���ĔM�͊w�f�[�^�x�[�X��������B�����E�ȒP�Ȍv�Z�͂ł���̂ŁA���������܂Ƃ��Ɏg���C�ɂȂ��ĉ��w�|�e���V�����}�̍�}���n�߂��B������_�@�ɍޗ��Ԃ̊E�ʔ������ɂ߂Ď��R�Ɍ��ʂ��邱�ƂɂȂ����B������ő̎_�����`�R���d�r�iSOFC�j�̍ޗ����ɓK�p���āA��q�̂悤�ɍ��ۓI�ȏ܂����炤�Ƃ���܂ł����B
�@���̂���A���c�x�Y�̖Ɖu�̖{��ǂ�ł��āA�ނ������Ƃ���̃X�[�p�[�V�X�e���i���ȑ��B�@�\���������V�X�e���j�̘b�����炭�C�ɂȂ����B�M�͊w�f�[�^�x�[�X�ƁA���������ϊ��V�X�e�����ǂ����Ă����̂ŁA���p�@�Ƃ��Ă͉����Q�l�ɂȂ�Ȃ����ƍl���Ă������߂ł���B���c�ɂ��A����̓X�[�p�[�V�X�e���Ƃ��Ď�舵����Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�ł͔M�͊w�́H�Ƃ����^�₪�킭�B���ꂱ��l���Ă���ԂɁA���������ϊ��V�X�e���̕��́A�p�\�R�������z���A�g�ѓd�b�ɔ�шڂ�A�V���Ȏ��ȑ��B�����Ă���l�q�B
�@�M�͊w�Ɛ��w�́A�ޗ��Ȋw�̋��ʌ���Ƃ悭������B����ł���ȏ�g�����Ƃ���O��ł���B�f�[�^��n�����鑤�ł̐��͑ޒ��͂�ނȂ��Ƃ͎v�����A��w�̍u�`�ł��M�͊w���ɂȂ��Ă���Ƃ̂��ƁB�c�O�ł���B�u���ʌ���v�Ƃ������t�́A���[�����t���Ǝv���B�ޗ��Ȋw�̑��̗̈�̌����҂ƍl������������ɂ́A�ł��d�v�Ȓm�̑̌n�ł��낤�B�܂��A�G�l���M�[�Ƃ����T�O�������I�Ȏ��_���狐���I�Ȃ��̂܂œ�����`�œK�p�ł���Ƃ����̂����炵���Ǝv���B���̈Ӗ��ŁA�ޗ������҂��u�ޗ����̂��́v�Ɖ�b������ɂ��M�͊w�͋��ʌ������Ă���Ƃ����v���������B�ŋ߂ł͂��̑��ʂ��X�ɒNj����Ă���B�@���ɑ����t�ȂǂɊ֘A����M�͊w�I�������A�����w�I�ɂ��d�v�ł���A�����̕����𑍍��I�ɗ������鑫���������Ă���ƍl���Ă���B�]�����玎�݂Ă������@�Ƒg�ݍ��킹�āA���āA���ȑ��B�̂悤�ȓW�J���ł��Ă��邩�H
�@���̓i�m���ł���B�䂪�O���[�v�����̈�p��S���Ă���B�����̘J�͂��₵�čs�����C�x���g�ƌ�����̂ŁA���̐��ʂ��A�P�Ȃ�������x�ɏI��炸�ɑ傫�Ȑ��ʂ��グ�Ăق����B���ɁA�o���N�̔M�͊w�́A�ӊO�Ɣ����I�ȋL�q�ɂ��D��Ă��đΏۂ��i�m�ł����ʌ���Ƃ��Ă̓����͎����Ă��Ȃ��Ǝ������Ă���B����A�傫�Ȓm�̑̌n�̒��ňʒu�Â��邱�ƂŁA�X�ɑ傫�ȑ̌n�֎��鎩�ȑ��B�̗l�Ȕ��W�����҂������B
�@�Ō�ɁA����o���N�̔M�͊w�ɋ������������l���X�Ƀo���N�̔M�͊w�{�̂̑��B��S���Ăق����A���������l������Ă����Ɗ��҂��Ă���̂����A���Ă�����̗\�z�͔@���ɁH
��16����{MRS�w�p�V���|�W�E��
�|�����\�Љ��n��擱�I�ޗ������|
2005�N12��9���`11���C���{��w���H�w���x�͑�Z�Ɂi�����s���c��j
�@��16����{MRS�w�p�V���|�W�E���́A2005�N12��9���i���j����11���i���j�̂R���ԁA��N���l�A�����E�䒃�m���ɂ���A���{��w���H�w���E�x�͑�Z��1���قōs���܂����B���ƂȂ����Z�ɂ�2003�N�ɗ��Ē����ꂽ���߁A�@��E�ݔ��͐V�����[�����Ă���A�䒃�m���w����߂����Ƃ������Ĕ��ɍD�]�ł������悤�Ɏv���܂��B
�@���N����V���ɍ��ۃZ�b�V�������R�Z�b�V�����i�Z�b�V�����`�A�f�y�тg�j�݂��܂����B���̎��݂́A�l�q�r�|�i�Ŕ��\������[�����𐢊E�ɔ��M����ƂƂ��ɁA���{�̊w�����茤���҂��A���E�Ŋ��錤���҂ƌ𗬂����@�����邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���܂��B���N�����葽���̃Z�b�V�����̂����͂����������A���ۃZ�b�V�������𑝂₵�Ă��������ƍl���Ă���܂��B�������������ɁA�č��ɖ{�������l�q�r������傫�Ȋ��҂��Ă��������A��N�s���Ă���܂���菧���҃��X�g�₻�̌������e���A�č��l�q�r�̃z�[���y�[�W��Ō��J�������Ƃ�����Ă����������Ă���܂��B
�@�{�V���|�W�E����17�̃Z�b�V��������Ȃ蕝�L��������J�o�[���A���{MRS�̗��O�u��i�ޗ��Ɋւ���Ȋw�E�Z�p�̐��Ƃ̉��f�I�E�w�ۓI�����𗬂�ʂ��āA���̊w�p�E���p��������ю��p���̈�w�̔��W��}��v���܂��ɍČ����Ă����Ǝv���܂��B


�@�{�N�x�́A�u�����\�Љ��n��擱�I�ޗ������v���e�[�}�ɁA�������\�i���ҍu���܂ށj320��(���ۃZ�b�V����38���A�������\282��)�A�|�X�^�[���\331���A���v651���̔��\���s���A��N���l�i��N���v658���j���Ɋ��C�ɂ��ӂ��V���|�W�E���ɂȂ�܂����B�e�Z�b�V�����̔��\�̗l�q�A�g�s�b�N�X�Ȃǂ́A�`�F�A�̊F�l�ɂ܂Ƃ߂Ē������ȉ��̕��Q�Ƃ��Ă��������B�܂��A���Q���������������\�Ҋe�ʁA�Z�b�V�����`�F�A�Ȃ�тɃV���|�W�E�����E�^�c�ɂ�����ꂽ�F�l���ɂ��炽�߂Ċ��ӂ�\���グ�܂��B
�@�����ɂ��G��܂������A���N���A���̗D�ꂽ�������\�E�|�X�^�[���\��ΏۂƂ�������܂�I�l���܂����B�Ώێ�423���̒�����46����I�o���܂����B��҂��ꗗ�ɂ��Ĉȉ��Ɏ����܂��B���W�̊F�l�̂��s�͂Ɋ��ӂ̈ӂ�\���ƂƂ��ɁA��҂̊F�l�ɂ��j���\���グ�܂��B
�@
�������҈ꗗ
�ESession A�F�J������(�k��)�A���ԗT��(������)�A�����F�q(���H��), �؍�z��(����)
�ESession B�F��������(����),�@�n糒q(������)�A�R�{�N��(���H��), B1-P20-M �ЎR�v����(����)
�ESession C�F������� (�R�`��), �����C�� (�c��)�A�������u (���ދ@�\)
�ESession D�F����N�_(���\�[), �~�ؐ�^(���k��)�A�ۉ��p��(�F���O�H�Z����)
�ESession E�F����M�v (���k��),�@�k�����M�j(����)
�ESession F�F���͉p�I (�k��), ��茒���Y (�k��)�A�ؑ�� (���H��)
�ESession G�F�~�V���l (���ދ@�\), �����T(�L��), �i�䕐�u(�L��), �֖ؔ��a(���H��)
�ESession H�F�����r��(���k��), ���T�V(����)�A�|���O�S(���), �R���c�S(���)
�ESession I�F�p�R���K(���q��), �g�c�p�O(���ދ@�\)�A���э_�a(���)
�ESession J�F������(����),
�ESession K�F P.Sommani(����), ���ߓ�(�Y����)
�ESession L�F������(���ދ@�\)
�ESession M�F�Ԉ����(����), ���r猗�(�Q�n��)�A�ґ���q(�c��), ��⏮�i(����)
�ESession N�F���˓���(�R�`��), �@���T�Y(�ߑ�)
�ESession O�F�c���^��(�Y����), �����K��(����)
�ESession P�F�p�ڊq(�Y����)
�ESession Q�F B. R. Sankapal (��), ����(����), ���O(����)
���Z�b�V����A�F�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ� Domain Structure-related Ferraic Properties and New Functional Materials
�@�{�Z�b�V�����́C���ҍu�������i9���j�C�������\�����i12���j�C�|�X�^�[���\�i28���j�ō\������C���U�d�̕����̃h���C���\�����L�[���[�h�ɁC�Z���~�b�N�X�C���́C�P�����C�����Ȃǂ̍ޗ��`�Ԃ̈Ⴂ���āC���_���牞�p�܂Ŏ��ɕ��L�����e�̍u�����s�Ȃ�ꂽ�B����܂Ŗ��N�p�����ĊJ�Â���C���N��4�N�ڂł���B1���ځi12/10�j�̌ߑO�E�ߌ�2��ɕ����ă|�X�^�[�Z�b�V�������s�Ȃ�����Ɍ����u���̃Z�b�V�������s���C2���ځi12/11�j�ɂ͊C�O�E��������̒����Ȍ����҂���̔��\�ɂ�鍑�ۃZ�b�V�����i���p��F�p��j���J�Â����B������̔��\�ɑ��Ă����Ɋ����ȓ��_���s�Ȃ��C��ϐ����ł������B
�@��̓I�ȓ��e�Ƃ��āC�܂��l�X�ȃh���C���ώ@�@�����ꂽ�B�h���C���ώ@�@�́C�ŋߔ��ɗL���Ȃ��̂���āC���p������Ă��Ă���C�{�Z�b�V�����ł�SNOM�C���d�����������ȂǗl�X�ȕ��@�ɂ��h���C���ώ@�@���c�_���ꂽ�B����ɁC������������@�ɂ��h���C���ώ@���ʂƋ��U�d�����C���d�����C���]�ڋ����̊W�ɂ��Ă������ɋc�_���ꂽ�B�h���C���G���W�j�A�����O�Ƃ������_����́C�d�E�C�M�Ȃǂ�p�����h���C���\���̐��䂪���ꂽ�B���Ɉ��d�����ɂ��ẮC���Ȃ��Ƃ��P�����ł́C�h���C���T�C�Y���R���g���[�����邱�Ƃɂ�舳�d����������ł��邱�Ƃ��قڊm���Ƃ�����i�K�ƂȂ�C���̂悤�Ȓm���̃Z���~�b�N�X�┖���Ȃǂւ̍���̓W�J�����ڂ����B���̑��ɂ��C�T�C�g�i���ׁj�G���W�j�A�����O�ȂǁC�~�N���ȍޗ��v�C����ɂ��V�@�\�ޗ��ւ̗l�X�Ȏ��g�݂��������ꂽ�B
�@�܂��C�h���C���\���ɗR�����镨���Ɋւ��錤�����\�����S�ŁC�H�Ɛ��i�̊J���ɂ͂����Ɍ��т��Ȃ����ȃe�[�}�ł���ɂ�������炸�C��N�ɑ�����������Ȃ��炸��Ƃ���̎Q���҂邱�Ƃ��ł����B�������C�Y�w���̊_�������������Ċ����ȋc�_�̏�Ƃ���ɂ́C����Ȃ��Ƃ���̎Q���҂�������悤�C��薣�͓I�ȃZ�b�V�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ������ǂ��낪�Ȃ�"�h���C��"��"�G���W�j�A�����O"����Ƃ��������������Ă��Ă��钆�Ŋ�ƂƂ̘A�g�́C�{�Z�b�V�����ɋ��߂���܂��܂��d�v�Ȏg���ł���ƍl���Ă���B
�i��{�@�@���É���w�G�R�g�s�A�Ȋw�������j
�� �Z�b�V�����a�F���q�������̍쐻�E�]���E���p�\���x�Ȕz������A�z����͂���ы@�\������ڎw����Fabrication, characterization and application of molecular thin films-structural analysis and control toward the realization of novel functions
�@�{�Z�b�V�����ł́A�L�@EL�f�q��L�@FET�ȂǁA���p���̏o���ɋ߂����q�����f�o�C�X�̌����҂ƕ��q�����̍\���]���Ɏ��g�ފ�b��������̌����҂��𗬂�[�߁A���q�����n�̊�b�E���p�������X�ɔ��W���邱�Ƃ����҂��Ċ�悳�ꂽ�B���\�͏��ҍu��4���A��ʍu��9���A�|�X�^�[���\21���̍��v34���ŁA�����i12/10(�y)�j���A�|�X�^�[���\�A����ځi12/11(��)�j����ʍu���E���ҍu���Ƃ����X�P�W���[���ł������B
�@�����ɂ́A�ߑO��11���A�ߌ��10���̃|�X�^�[���\���������B���Z�b�V�����ƍ����ł��������߁A�Q���҂��A���Z�b�V�����̔��\�҂Ɠ��_����ȂǁAMRS-J�̓�������������A�����M�C�Ɉ�ꂽ�B
�@����ڂ̌ߑO���ɁA�悸�A�u���q�f�o�C�X�̊�b�Ɖ��p�v�Ƒ肳�ꂽ�T�u�Z�b�V�������s��ꂽ�B�����ł́A���d��LB���A�L�@EL�f�q�A����їL�@FET�Ɋւ���ŐV�̐��ʂ����\����A�����ȓ��_���s��ꂽ�B�ߑO�̍Ō�́A���ҍu���Ƃ��āA���H��̊Ԓ��F���搶�ɂ��A�u�V�K���w�I��@�ɂ��L�@FET�̓���]���v�Ƒ肳�ꂽ�u���ŁA������ɂ��A���w�I�Q�������g�iSHG�j��p���āA�L�@FET��ON-OFF��Ԃ��j��I�Ƀv���[�u����V�������@�Ɋւ���ڍׂȃ��r���[���Ȃ���A�����ȋc�_���W�J���ꂽ�B
�ߌ�́A�u���ȑg�D���Ƃ��̉��p�v�Ƒ肳�ꂽ�T�u�Z�b�V�������A�k��E�������k�搶�̏��ҍu���ɂ��n�܂����B�^�C�g���́A�u���ȑg�D���ɂ���ăp�^�[�������ꂽ�����q�����̃o�C�I���f�B�J�����p�v�ŁA�n�j�J���\���p�^�[�����������q���̍\������Ƃ��̃o�C�I���f�B�J������ւ̉��p�Ɋւ���A��b�E���p�̗����̊ϓ_����̋����[�����\���Ȃ���A�����̒��O�̋������䂢���B���̌�ALB����Q���̉�́E�\������Ɋւ����ʍu����4�������A���̌�A�R�`��E���X���T�搶�ɂ��A�u���^�����q�������̑g�D���q�����ɂ�����\������Ƃ��̕]���v�Ƒ肳�ꂽ���ҍu��������A�����ł́A�ŋ߂̐��ʂ��A�����̃t�B���\�t�B�[�Ƌ��ɔM�����ꂽ�B�����āA�Ō�́A�W���[�W�A��E���c�L��搶�ɂ��A�u�ԊO�X�y�N�g����2�����I�ɓW�J����A�v���[�`��p�����@�\��LB���̍\����́v�Ƒ肵�����ҍu���ŁA������ɂ���@���A�L���l�X�ȕ��q�����n�̍\���]���ɓK�p�ł��邱�Ƃ��킩��Ղ�������A���̍����f�B�X�J�b�V�������s��ꂽ�B�i�O�Y�N�O�@�ˈ����l��@�H�j
���Z�b�V�����b�F���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\�@�Z�@Self-Assembled Materials
: Synthesis and Applications VII
�@���ȑg�D���𗘗p�������x�ȑg�D�̂̌`���́A�]���ɂ͖����v�V�I�Ȏ�@�ł���B�{�Z�b�V�����́A�L�@�n�A���@�n�A�����n�A�X�ɂ��̕����E�W�όn�ɂ�����A���ȑg�D�����ۂɊւ���V�ޗ��E�\���̂̑n���A�����̍\���Ƌ@�\�̉𖾓��̍L�͂Ȍ������܂݁A���ҍu��2���A�I�[����8���A�|�X�^�[23���̍��v33���̔��\�ŁA�����ȓ��_���s�Ȃ�ꂽ�B
�@�ߑO�ƌߌ�ɕ����ꂽ�|�X�^�[�Z�b�V�����̌�ɁA���ҍu�����܂ތ������\���s�Ȃ�ꂽ�B3���̈�ʍu���̌�ɍŏ��ɍs�Ȃ�ꂽ���ҍu���ł́A���H��@���H�̍��c�\�u�a�搶�ɂ��u�g�|���W�[�ω������Ƃ���t�I�ˋ��E�ˋ��_���^�Q���̑n���v�̑�ڂŁA�|�����^�L�T���Q���̑n���₻�̎O�����\������ȂǁA���q���x���œW�J�����@�\���̏Љ�s�Ȃ��A���l�Ȏ��_����̊����Ȏ��^�������Ȃ��ꂽ�B4���̈�ʍu�����͂���2���ڂ̏��ҍu���́A���{�i�搶�i����@�H�j�ɂ��u�T�C�Y�I��I���G�b�`���O�ɂ��V�K�R�A�[�V�F���\���i�m�����̂̍쐻�Ƃ��̌����w�����v�Ƒ肷��u���ŁA�i�m�T�C�Y�̋�Ԃ�L����u�W���O���x���v�^�i�m�\���̂̑n���ɂ��ċ�Ԑ���Ȃǂ̏ڍׂȏЉ����A�����Ȏ��^�������s��ꂽ�B
�ȏ�̂悤�ɖ{�Z�b�V�����ł́A�L�����ȑg�D���Ɋ֘A���ėl�X�Ȋw��Ŋ������Ă���{����̌����ҁE�w���Ԃ̌𗬂����i����A�{����̈�w�̓W�J�Ɛ[�����}�ꂽ�B�@�i����J�p�K�@�R�`��H�j
��Session D�F��炵��L���ɂ���ޗ��\���E�G�l���M�[�E���Materials for Living - Environment, Energy, and Medicine
�@�{�Z�b�V�����ł͕�炵��L���ɂ���ޗ����̉��p�̗��ꂩ��A�����ȍu���Ɠ��_���s�Ȃ�ꂽ�B���\�͏��ҍu���Q���A�I�[����22���A�|�X�^�[15���̍��v39���ŁA�Q���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�������\�̉��ł͍u���̓��e���L������ł��������A�����ȓ��_���s���A�u�����Ԃ��I�[�o�[������̂��������B
10���́A�܂��l���_�����A�[�I���C�g�����\���A�[�I���C�g���̍�������6���̌������ʂ����\���ꂽ�B���̃Z�b�V�����ł́A�y���u�X�J�C�g�R�o���g�_�����A�`��L��������p�����A�N�`���G�[�^�[�̈ʒu���߁AAl�����쐻�A�l�ق��_���`�E���P�����琬����4���̐��ʂ����\���ꂽ�B
11���́A�}�C�N���g�U�����M�ɂ��≻�����Ҍ��ACdSe�i�m���q�̍����Ɖ��p�A�A�p�^�C�g�R���|�W�b�g�Ɣz���ǃX�P�[���̏������@�̔��\���������B���̌�15���̃|�X�^�[�Z�b�V�������Ȃ��ꂽ�B�ߌ�͂Q���̏��ҍu���A�R����̏��Y�������ɂ��u�M�d���p�Ɍ�������ꌴ���d�q��Ԍv�Z�ɂ��ޗ��v�v�ƎR���� �r�c�U�����ɂ��u�ŋ߂ɂ�����W�I�|���}�|�Z�p�̐i���v���s��ꂽ�B���ꂼ��̏��ҍu���ł͂��̌�4�����̊֘A����u�����s���A���^�����������ɂȂ��ꂽ�B
�@2���Ԃɂ킽����E�G�l���M�[�E��ÂɊւ���L������ł̌������\�ł��������A���̍����u�����тɊ����Ȏ��^�������s��ꂽ�B
�i��������@�R����H�j
���Z�b�V����E�F�M�d�ϊ��ޗ��̐V�W�J?�ޗ��E�f�o�C�X�E���_Progress in new thermoelectric materials - material, device and theory
�@�{�Z�b�V�����ł́A�M�d�ϊ��ޗ��̍��������Ɋ֘A����ŋ߂̃g�s�b�N�X�i�ޗ��v���Z�b�V���O�E�f�o�C�X�E���_�Ȃǁj�ɂ���26���̈�ʌ����u��������A12��11���̒�����[���܂ŔM�S�ȓ��_���s��ꂽ�B
���\���e�͎_�����M�d�ϊ��ޗ��Ɋւ�����̂������������C�z�E������N���X���[�g�CAl��ߎ������ȂǃG�L�]�`�b�N�ȐV�����̔��\���������B���ɐX�F�Y���i���ދ@�\�j�̔��������z�E�����́C�M�N�d�͂��}�C�i�X�ɂȂ�N�^�ł���B�悭�m���Ă���悤�ɔM�d�ϊ��ޗ���P�^�CN�^��g�ݍ��킹�đf�q�ɂ���B����̔����ɂ��I�[���z�E�����̔��d�f�q�����ւ̓����J���ꂽ�B
�@���\�̒��S�ƂȂ����w��R�o���g�_�����̌����͂��������L����Ɛ[�݂𑝂�����B���䕐�����i����ቷ�Z���^�[�j�́C�l�X�ȑw��R�o���g�_�����̒P�������쐻���C���̓d�q���}���n���I�ɒ��ׂ��B����ɂ��C�����́CCoO2�ʂ̑w�Ԃɑ}�������A���J���C�I���̎�ނɊW�Ȃ��C�Z�x�݂̂Ō��܂�Ƃ����B���c�T�����i����H�j�͑w��R�o���g�_�����̋����[�������v���Z�X�ɂ��ĕ����B���̕����̕s�����Na��Sr��Ca�ŃC�I���������邱�Ƃɂ�����ō����\�ȔM�d�ޗ��������쐻�ł���B
�i�͖{�M�m�@����H�j
���Z�b�V�����e�F��i�i�m�X�P�[���\����?�\���Ɛ����̑��ց@Advanced Nanostructured Materials -Correlation between Structure and Property
�@�{�Z�b�V�����ł́A�i�m�T�C�Y��������т���炪��Ԕz���\���̂̑n���A�Ȃ�тɁA�\���̂��L����\�����قȐ����Ɋւ��Ċ����ȓ��_���s�Ȃ�ꂽ�B���\�͏��ҍu��2���A�������\12���A�|�X�^�[���\22���̍��v36���ł���A�ŏI��1���ōs��ꂽ�B�������\�̉��ł͎��⎞�Ԃ�����Ȃ��Ȃ�قǁA���ɓ˂������̂��铢�_���Ȃ��ꂽ�B
�@���e�Ƃ��ẮA�����E�_�����E�Y�f�ޗ��Ȃǂ̖��@�ޗ��̑n���ƕ����I�E���w�I�����Ɋւ��錤�������S�ł��������A�l�HDNA��|���}�[�Ȃǂ̗L�@���̐��������܂����p�������@�ޗ��̋@�\���Ɋւ���������Ȃ�����ۂ�����A�L�@?���@�����ޗ��̏d�v��������܂��܂������Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B���ҍu���ł́A�ߑO���ɖk��G�����i���@���j�ɂ��u�i�m��Ԃɂ�����ő̃v���g�j�N�X�v�Ɋւ���ŐV�̌������ʂ�����A�����i�m�X�P�[���ޗ��ɓ��L�̐��f�z�������⑊�\���ω��Ȃǂɂ��ĕ�����₷���Љ�Ē������B�i�m�Ƃ����傫���́A�ޗ��̕����I�E���w�I�����݂̂Ȃ炸�\�����g�ɂ��o���N�ł͗\�z�ł��Ȃ��ω����y�ڂ����Ƃ����߂ĔF��������ꂽ�B�����Čߌ�ɂ́A�͍��ዳ���i�ޗǐ�[�啨���n���j�ɂ��u�C�I�����t�̔}�����ɂ����锼���̃i�m�����̍��������v�Ɋւ��鏵�ҍu�����s��ꂽ�B���n��II-VI�������̃i�m���q�i���CdTe�j�̃C�I�����t�̂ւ̒��o�ɂ��啝�Ȕ��������̑���ɂ��ďЉ�Ē����A���������ɑ���i�m���q���͂̃}�g���b�N�X�\���̏d�v���Ƃ����_�Ŕ��ɋ����[���u���ł������B�{�Z�b�V�����ł́A�����A�|�X�^�[�Ɋւ�炸�A�V�K�ȃi�m�X�P�[���\���̂̑n���ƍ\�����ٓI�Ȑ����ɂ��ċɂ߂Ďh���I�Ȍ������ʂ���������Ă���A����Ƃ��i�m�X�P�[���ޗ��Ƃ��̐����ɏœ_�Ă��Z�b�V�����Ƃ��Čp�����Ă�����Ǝv���B�@�@�@
�i���������@�}�g��@���������Ȋw�j
��Session G�F������d�q�f�o�C�X�̂��߂̗U�d�̔����Z�pTechnology of Dielectric Thin Films for Future Electronic Devices - Control of the interface and the Nano-Structure
�@�{�Z�b�V�����ł́A������d�q�f�o�C�X�̂��߂̗U�d�̋Z�p���e�[�}�ɍ��U�d���≏���⋭�U�d�̔����Ɋւ���ޗ��E�E�ʐ���Z�p�ɂ��āA���ҍu��3���ƈ�ʍu��27���i���|�X�^�[���\17���j�̌v30���̔��\���������B���̗����i12��11���j�ɂ́AMRS-Korea�Ƃ̘A�g��[�߂�ŏ��̎��݂Ƃ��āA�uJapan-Korea Special Session on "Evolution and Outlook of Oxide Nonvolatile Memories"�v���J�ÁiMRS-Korea����ѕ����ޗ������@�\�Ƃ̋��Áj���A�������炻�ꂼ��7���v14���̒����Ȍ����҂����ق��A���ҍu�����x�[�X�ɓ��e�̔Z�����_���s�Ȃ����B
�@���U�d���Q�[�g�≏���֘A�̔��\�ł́AHf��Pr�V���P�[�g�A�����Y2O3 ��La2O3-Al2O3 �������ɂ����āA�\�����͂⌇�v���Ɋւ��������ASi��Ƃ̊E�ʔ����⌇�א���ɂ��Ă̋c�_���Ȃ��ꂽ�B���R���i���Łj�̏��ҍu���ł́A���U�d���≏���̃Q�[�g�≏�����p�ɂ����ă{�g���l�b�N�Ƃ��Č��O����Ă���`���l���ړ��x���ۂɏœ_���i���ďڍׂȋc�_���Ȃ��ꂽ�B��ʍu���ɂ����Ă��AHfO2��V���P�[�g�ւ̒��f���������w�\���A�d�q��Ԃ�_�f��E�����ɋy�ڂ��e�����A���_�E�������ʂ���c�_���ꂽ�B�܂��A������Q�[�g�X�^�b�N�Z�p�Ƃ��ĕK�{�ƂȂ郁�^���Q�[�g�AAl2O3/SiC�E�ʂ�Al2O3/SiN/poly-Si�E�ʂ̔M�I���萫�̋c�_�AGe�\�ʂ̌�������Si�\�ʂ̃v���Y�}�����ߒ��ɂ��Ă̔��\������A��N�ȏ�ɕ��L���c�_�̏�ƂȂ����B
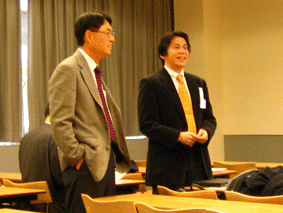
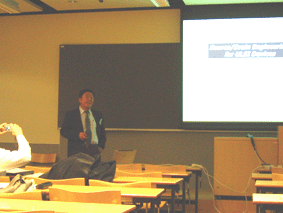 �@���U�d�̔����֘A�ł́APZTN�APZT�A(Ba, Sr)TiO3�A(Bi, La)4Ti3O12�ABa(Ti, Zr)O3�A(Pb, Ba)TiO3�ASBT�����ɂ��Ă̔��\������A�����ȋc�_���s��ꂽ�B���ɁA�ؓ����i�Z�C�R�[�G�v�\���j�́A���ҍu���ɂ����āANb�Y��PZT�iPZTN�j�����̊J���o�܂��Љ�ANb�Y���ɂ���Ď_�f��E�̐������������}���ł��錋�ʁA��[�N�d�������ێ������������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���Ƌ��ɁA�����M������L����64k-bits FeRAM�̊J���ɐ����������Ƃ���A���ڂ��W�߂��B
�@���U�d�̔����֘A�ł́APZTN�APZT�A(Ba, Sr)TiO3�A(Bi, La)4Ti3O12�ABa(Ti, Zr)O3�A(Pb, Ba)TiO3�ASBT�����ɂ��Ă̔��\������A�����ȋc�_���s��ꂽ�B���ɁA�ؓ����i�Z�C�R�[�G�v�\���j�́A���ҍu���ɂ����āANb�Y��PZT�iPZTN�j�����̊J���o�܂��Љ�ANb�Y���ɂ���Ď_�f��E�̐������������}���ł��錋�ʁA��[�N�d�������ێ������������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���Ƌ��ɁA�����M������L����64k-bits FeRAM�̊J���ɐ����������Ƃ���A���ڂ��W�߂��B
�@�V���R���i�m�����𗘗p�����t���[�e�B���O�Q�[�gMOS�������֘A�̔��\���A���{�����i����j�̏��ҍu�����܂߂ĂT���������B���{�����̓f�o�C�X�\���ɂ����āA�V���R���i�m�����t���[�e�B���O�Q�[�g�Ƌɍא��`���l���\���A�_�u���Q�[�g�\���A�Z�`���l���\����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�t���[�e�B���O�Q�[�g�f�o�C�X�̋@�\�����i�i�Ɍ��シ�邱�Ƃ𖾂炩�����B�������E�A���\���E���뜜����錻��ɂ����Ă��A�܂��܂��H�v����]�n�����邱�Ƃ��ĔF�����ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{�� ����@�L����j
�@
���Z�b�V�����g�F��[�v���Y�}�Z�p���i�m�}�e���A���Y�t�����e�B�A�@Frontier of Nano-Materials Based on Advanced Plasma Technologies
�@�{�Z�b�V�����́A��N�x����J�Â��Ă���A�v���Y�}��p�����i�m�}�e���A���n���ɏœ_���i��A�v���Y�}����ȊO�̕��X�ɂ��L���Q�����Ăт����āA�O��I�ɋc�_������n���Ă������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��2��ڂƂȂ鍡��́A���{MRS�ł͏��߂Ă̎��݂Ƃ��ď�����12��9���ɍ��ۃZ�b�V�����݂��A����2���Ԃ̊w�p�V���|�W�E�����܂߁A3���Ԃɂ킽�銈���ȓ��_���s��ꂽ�B���\�́A���ҍu��12���A��ʂ̌������\29���A�|�X�^�[���\36���ŁA����3���Ԃ̍��v77���̐���ł������B
�@�����̍��ۃV���|�W�E���́AIUMRS�����Prof. R.P.H. Chan �搶�iNorthwestern Univ.�j��荑�ۃV���|�W�E���J�Âɑ����j����Ղ��Ă̊J��ɑ����āA�Z�b�V����"Biomimetic Process and Biological Applications"�ł̍��� ���搶�ɂ��Plenary�u������ɃX�^�[�g�����B�����ߌ�ɂ́A "Based Materials, Oxides and Nitrides"��"Carbon Based Coatings and Nanostructures"�Ɋւ���Z�b�V�������J�݂��A�`�F�R��Prof. Vlcek�搶�A�؍���Prof. J.G. Han�搶�ɂ��Plenary�u�����܂߁A���͓I�Ȕ��\�Ƌc�_���Ȃ��ꂽ�B�܂��A���ۃV���|�W�E�����L�O���ĊJ�Â���Reception���A���C���Ў�ɐ��������B
�@2���ڂ́A�ߑO������ߌ�ɂ����Ẵ|�X�^�[���\�ɑ����āA"�G�l���M�[�֘A�A�V���R���v���Z�X"�Ɋւ���I�[�����Z�b�V�����A�ŏI����3���ڂ́A�}�C�N���v���Y�}�A���q�ÏW�́E�i�m���q�v���Z�X�A�Y�f�n�i�m�\���A�v���Z�X���u�E�v���f�f�Z�p�Ɋւ���I�[�����Z�b�V�������J�݂��A����������Ԃ߂��Ă̓˂������_���Ȃ��ꂽ�B�Ō�ɁA���ۃZ�b�V�����J�Âɂ����z���������R�{�搶�A��c�搶�A�Ɉ�l�͂��߁A�W�e�ʂɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ߌ��T��@���ڍ����j
���Z�b�V����I�F�i�m�\���ƕ����@�\����Nanostructure of Materials and Their Function and Property
�@�{�Z�b�V�����ł̓i�m���x���̍\���Ƃ��̕��������Ȃ�тɂ��������i�m�\���̉��p������ɓ��ꊈ���ȓ��_���s�Ȃ�ꂽ�B���\�͂��ׂă|�X�^�[�i21���j�Ƃ��A���ҍu����5�����肢�����B�Z�b�V������1���݂̂ł��������A���ҍu����50���Ƃ��Ď��ԓI�ɗ]�T���������Ă����������̂ŁA���ɐ[���u�����e�Ղ��A���^�����ł͓˂������_���Ȃ��ꂽ�Ǝv���B
�@10���ߑO�ɂ̓|�X�^�[�ɂ�锭�\���s��ꂽ�B�i�m����̍L�͈͂���̔��\���s��ꂽ�B�L�[���[�h�͕\�ʁE�E�ʂƂȂ��Ă���悤�Ɍ���ꂽ�B�����A�\���A�@�\�̏ڍׂȉ�͂̌��ʂ�������A���̕���ɂ�������{�̒�͂������ꂽ�Ǝv����B������������͐����ŁA�����Ɗ���������قǂł������B
�@�ߌ�ɂ͏��ҍu���������������B�܂����E�ދ@�\�̔�����F�����u�L�@�^�����n�C�u���b�h�i�m�����̍\������Ƌ@�\�v�Ƒ肷��u���ŁA�A�]���`���f���h���}�Ƌ����̐��䂳�ꂽ�z�ʍ\���̌`���Ƃ��̉��p�ɂ��ču������A���q���x���̒����\���`���ɂ��ĔM�����ꂽ�B���������ANICT�̉��R�m�g���Ɂu�L�@�ő̃��[�U�[��ڎw�����f���h���}�[�̌��G���N�g���j�N�X�v�Ƃ�����ŁA�f���h���}�[���`�������𗘗p�����F�f���m�̑��ݍ�p����ɂ��ő̃��[�U�[����̎��݂ɂ��Ęb���ꂽ�B�R��������̌˓��������ɂ́u�����i�m���q�̋@�\�����v�Ƃ�����ŁA�i�m���q�̋@�\�A���ɉt���Ƀh�[�v���ꂽ�i�m���q�̉e���ɂ��Đ[���c�_�����������B����@���̓n�ӖF�l���ɂ́A�uMolecular Design of Organometalloenzymes�v�Ƃ��āA�l�H�y�f�Ƃ��Ă�Pd-�t�F���`���n�̍\�z�ƑN�₩��X����@�ɂ�邻�̔��\����͂ɂ��Ă��b���������A�Ō�ɁA�k����[��̑�J�����ɂ́A�Ő�[��DDS�Ɋւ��鉞�p�Ƃ��āuHydrotropic Dendrimers and Reducible Polyrotaxanes Toward Drug and Gene Delivery Systems�v�Ƃ�����ł̂��u���Ղ����B������̍u���Ɋւ��鎿�^�����������ŁA���̍����f�B�X�J�b�V�������s��ꂽ�B�@�i���V�@�O�@����@���j
���Z�b�V����J �擱�I�o�C�I�C���^�[�t�F�C�X�̊m�� Frontier of Biointerfaces �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�֓��i�G�@���É���w�H�w���j
���Z�b�V���� K�F�C�I���r�[���𗘗p�����v�V�I�ޗ�Innovative Material Technologies Utilizing Ion Beam
�@�{�Z�b�V�����̎Q���Ґ���40���A�|�X�^�[���\�i17���j�A�������\�i17���j�ł������B
�@�C�I���r�[���𗘗p�����Z�p�́A�ޗ��Ȋw�̕���ɂ����āA���͉��p����ޗ��n���ɘj�蒘�������W�𐋂��ė����B�C�I���r�[����p�����ޗ��n���Z�p�ɂ́A�t���A��N�E�������i���ʂ��Ԑ��䐫�������̓���������A�����������v�V�I�ޗ��̑n�������҂����B�{�Z�b�V�����ł́A�C�I���H�w�I��@��p�����i�m�ޗ��A�����ޗ��A�o�C�I�ޗ����V�ޗ��̌����A���邢�͐V�����C�I���r�[���Z�p����ΏۂƂ��A�v�V�I�ȍޗ��Z�p���u�����錤�����\����A���f�I�E�w�ۓI�𗬂��s�����B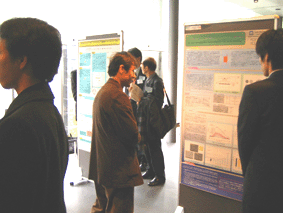
�@���\�_���́A�C�I����ɂ��ẮA���G�l���M�[�d�C�I���A�v���Y�}�A�A�[�N�C�I���A���C�I�����A��@�Ƃ��ẮA�C�I�������A�v���Y�}�APBII�A�C�I���r�[�������A�C�I���r�[���X�p�b�^�����O�A���d���Z�p���̑��l�ȋZ�p�ɘj��A�ޗ��n�ɂ��ẮA���`���ޗ��iYBCO�ALSMO, LBMO�j�A�����̌n�iGe�j�AC�n�iDLC���AC���A�������j�A�������n�iTiN�j�A�i�m���q�n�i�������A�_�����j�A�_�����iTiO2�AZnO�j�A�|���}�[�n�i�|���C�~�h�APET�A�A�r�W���j�A���̍ޗ��i�|���X�`�����j���A���l�ȐV�ޗ��ɂ��čŋ߂̌��ʂ����ꂽ�B�ŋ߂̌X���Ƃ��ẮA�C�I�������ŁA�ޗ��\�ʂ̌��w�����E�����A�g���C�{���W�[���̉������ʂ�_���������A���̓K���������P���錤���ɉ����āA�C�I���̌��ʂ�p���������`���Z�p���L�тĂ���B�����͖{�V���|�W�E���̑_���ł���w�ە���ɑ�������̂ł���A�C�I���Ȃ�ł͂̌��ʂ������Ă���ꍇ���������̂́A�K�������@�\�����炩�łȂ��ꍇ�������B���f�I�ȓ��_�ɂ��@�\���𖾂���A�v�V�I�ޗ��̌������i�W���邱�Ƃ��]�܂��B
�@����̃Z�b�V�����ł́A�w���y�яC�m�̊w���̔��\�����ɑ����A�܂��A�|�X�^�[�Z�b�V�����͌ߑO���ł������ɂ��ւ�炸�A�����̗����҂��K��A���C���锭�\�Ɠ��_���s��ꂽ�B
�i�r�R����@�Y�ƋZ�p�����������j
���Z�b�V����L�F������G�R�}�e���A���[�����a�^���@�\�G�l���M�[�ޗ� Ecomaterials Next Generation -Environment-conscious Advanced Materials for Energy System
�@�{�Z�b�V�����ł́A�����a�^�ޗ��ɂ��āA���ɍ��@�\�G�l���M�[�ޗ��̍����ƍ\���E�@�\�]���Ȃ�тɂ��̉��p�𒆐S�Ƃ��āA���e���A�i�m��}�N���\������A��������̎��_���犈���ȓ��_���s�Ȃ�ꂽ�B���\�͏��ҍu��2���i�v���O�����ł�3���ł��������A1���L�����Z���j�A�I�[����12���A�|�X�^�[9���̍��v23���ŁA2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B���ҍu������20���A��ʍu��15���Ɣ�r�I���Ԃ��Z���������߂��A���^�ōu�����Ԃ��I�[�o�[������̂����������B
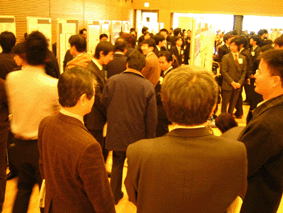 �@������12:30�`14:00�ɂ́A�|�X�^�[�Z�b�V�������s��ꂽ�B�R���d�r�A�M�d�ϊ��ȂǂɊ֘A�������\�������������ŁA�Ԕ��ނ�Ȃǂ̃o�C�I�}�e���A�������̋�̓I�L�����p�Ɋւ��锭�\�������[�������B15:00����̌������\�ł́A�܂����ҍu���Ƃ��Ė��É���w�̍��c�����Y�����u�ޗ��̊����w�W�̍��ۊJ���ƕW�����v�Ɋւ���u�����s���A����NEDO�O�����g�Ő��i���Ă���v���W�F�N�g�̏Љ�������B���ɏ��ҍu���Ƃ��āA�`���[���Y��w�̃}�g����������uPdSn�����G�}��̒ቷCO�_�������v�Ɋւ���u�����������B�����Ĉ�ʍu���Ƃ��āA�����\�[�d�r�p�ޗ��Ɋւ���h���I�Ȕ��\�̌�A5���̎�Ƃ��ĔR���d�r�V�X�e���p�̍ޗ��Ɋւ��锭�\���s��ꂽ�B
�@������12:30�`14:00�ɂ́A�|�X�^�[�Z�b�V�������s��ꂽ�B�R���d�r�A�M�d�ϊ��ȂǂɊ֘A�������\�������������ŁA�Ԕ��ނ�Ȃǂ̃o�C�I�}�e���A�������̋�̓I�L�����p�Ɋւ��锭�\�������[�������B15:00����̌������\�ł́A�܂����ҍu���Ƃ��Ė��É���w�̍��c�����Y�����u�ޗ��̊����w�W�̍��ۊJ���ƕW�����v�Ɋւ���u�����s���A����NEDO�O�����g�Ő��i���Ă���v���W�F�N�g�̏Љ�������B���ɏ��ҍu���Ƃ��āA�`���[���Y��w�̃}�g����������uPdSn�����G�}��̒ቷCO�_�������v�Ɋւ���u�����������B�����Ĉ�ʍu���Ƃ��āA�����\�[�d�r�p�ޗ��Ɋւ���h���I�Ȕ��\�̌�A5���̎�Ƃ��ĔR���d�r�V�X�e���p�̍ޗ��Ɋւ��锭�\���s��ꂽ�B
�@2���ځA9:15����6���̈�ʍu�����������B�M�d�ϊ��Ɋւ��锭�\��3���A�J�[�{���A�}�O�l�V�E���A�Ԕ��ޗ��p�Ɋւ��锭�\�����ꂼ��P���s��ꂽ�B�ޗ��Ɗ��̌W��荇���ɂ͑��l�ȑ��ʂ�����A�G�R�}�e���A���Ƃ��Ẵ`�������W���O�Ȍ����̏Љ���ڗ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���È�@���ދ@�\�j
���Z�b�V�����l�F�@�\���\�t�g�}�e���A���Ƃ��Ă̍����q�Q��Polymer Gels as Functional Soft Materials
�@�{�Z�b�V�����́A�����q�Q�����@�\���\�t�g�}�e���A���Ƃ��������𑽕��ʂɊ������Ă��������\�z���Ă������߂́A���̌����𖾂�V�K�ȉ��p�Ȃǂɂ��Ă̕��쉡�f�I�ȋc�_���s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Đݒ肳�ꂽ�B���\�͏��ҍu��3���A�˗��u��1���A�I�[����14���A�|�X�^�[34���̍��v52���ŁA2���Ԃɂ킽�芈���ȓ��_���s��ꂽ�B
�@�����ɂ́A���ҍu���Ƃ��đ��s����̐������`�D�����u�����ނ̃Q���ƃQ�����ߒ��v�Ƒ肵�āA�H�i�Ȃǂɗ��p����Ă��鍂���q�����ނ̃Q���ɂ��āA����܂ł̌����̑����ƌ���ɂ��đ���ɂ킽����s�����B���̒��ŁA����̌����̕����ɂ��đ����̎�����^����ꂽ�B���ɁA�����Q���ɂ����ẮA���̂������̌��ʂɂ��Ă̌����̕K�v�����w�E���ꂽ�B�˗��u���Ƃ��āA��B��̍��X�ؖΒj�����u�����q�Q���̒e���ɘa�v�Ƒ肵�āA�e�������𗝉������ł̗��_�I�g�g�݂ɂ��ďЉ����A�����ȓ��c���s��ꂽ�B2���ڂɂ́A���ҍu���Ƃ��āA���s��̌É�B���ɂ��u�g�ݑւ��Ԗڂ̃V�A�|�V�b�N�j���O�̕��q�@�\�v�Ƒ肵���A�ŐV�̃R���s���[�^�[�V�~�����[�V�����̌��ʂ̕��������B��������q���Ԗڂ��\���^�č\������ߒ��Ŏ����A���@�\���o�Ȃ��V�A�[�V�b�N�j���O�@�\���A�j���|�V�����Ńr�r�h�ɏЉ��A�V�A�|�V���j���O�ւ̂̂肤��ȂNj����[�����ʂɑ��Ċ����ȓ��c���s��ꂽ�B3�Ԗڂ̏��ҍu���Ƃ��āA��������V���p�����ɂ��u���̃\�t�g�}�^�|�ɂ�����]�ڂ�1/f�G���v�Ƒ肵���A�������̐A�����ނƂ��������[�������̕��������B��c�̓r���ł́A���N�x�Œ�N�ފ����}�����邨��l�̐搶�ɑ��A�ԑ��̑���ƋL�O�ʐ^�̎B�e������A�Q���҈ꓯ�̘A�ъ�����w���߂�ꖋ���������B
�@�|�X�^�|���\�A�������\�Ƃ��Ɋ����Ȏ��^����������Ԃ���A�����Q���Ƃ������V��������̑n���ɂȂ��錤�����\������A���̍����f�B�X�J�b�V�������s��ꂽ�B�@�@�@�i�E�c����@�Q�n��H�j
���Z�b�V����N�F�����n�����̍ŋ߂̐i��Advances in the Application of Biological Resources
�@�{�Z�b�V�����́A���j���J�Âɂ�������炸�A��N������K�͂Ő������ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɁA�F�l�̂����͂Ƃ��s�͂̎����ƁA�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�{�N�����Z�b�V�����ł́u���������̗L�����p�A���T�C�N���A�V�f�ނ̊J����]���Z�p�A�i�m�I�[�_�[�ł̍��@�\���p�@�v�𒆐S�ɍŋ߂̐i���ɂ��ē��_���Ă܂���܂��B�{�N����낵�����肢���܂��B
�@���ҍu�������ꂽ�������搶(�ߋE��w����q�H�w��)�́u�Y�_�K�X�̌Œ艻�Ɣ������ޗ��̉��p�v�ł́A���������Ȃ��������g����������q�ޗ��։��p����M�̂��������u���ł����B�����q�̖��͂Ɖ��w�̉��̐[���Ɋ������܂����B�ԓc�K���Y��(�Y����)�́u�i�m�_�C�������h�̐����Ɖ��p�J���v�ł́A�������@����Ő�[�̊��p�܂Ő��͓I�Ȍ������ʂ����\����܂����B���^�����������ŁA���̍����f�B�X�J�b�V�������s���܂����B
�@�I�[�����Z�b�V�����́A�ߑO4���ƌߌ�10����2���ɕ�����āA��9�����߂�����5���܂ōs���܂����B�čf������Y���̐V�f�ފJ���A�q�o���␅���Ռ��g�̗��p�����A�Y�f�̔R���d�r�d�ɂւ̉��p�������ƕ��L������ɂ킽�荂�x�Ȍ������\����ł����B���P�ʂ̃X�P�W���[���ɂ�������炸�A�\���Ȕ��\�Ɠ��c���o���܂����B���M���Ď��Ԓ��߂����X����܂������A���\�҂ƕ����肪��̂ƂȂ����[���������\�ɂȂ�܂����B�ꕔ�A�f�[�^�ƃp�\�R���̑�������������f�������܂����B�@�]�ǂ��x�ݎ��Ԃɂ��Ă�������������܂����B
�@�|�X�^�[�Z�b�V�����̔��\������27���ŁA10��������12���܂ŁA�c��o�Z�b�V�����ƍ����ŊJ�Â��܂����B�|�Y��I�J���A��c�Ԃ̐V�ޗ��J���A���\�|�[���X���T�C�N���Z���~�b�N�X��q�m�L�`�I�[���̗��p�����A�{���̗��p�����⑽�E�̂̐��f�����ޗ��ւ̉��p�������Ə����̔��W���y���݂ȕ������ł����B����ⓢ�_�������ŁA������Ƃ���ŏ��ԑ҂����o���Ă��܂����B���\�҂̕��́A�܂������x�ގ��Ԃ����������Ǝv���܂��A����J�l�ł����B�|�X�^�[�̃f�U�C�������e���ǂ���J�Ɗ�т��`����Ă��܂����B
�i�����q�O�@�X���H�Ƒ��������Z���^�[�j
���Z�b�V����O�F�i�m�E�ʂ̐V�@�\�|���w�I�E�@�B�I�E�d�q�I�@�\�̉𖾂ƐvNovel Functions of Nano-Interfaces: Understanding and Design of Their Chemical, Mechanical and Electronic Properties
�@�{�Z�b�V�����́A�����E�����́E�Z���~�b�N�X�E�L�@�����q�E���̍ޗ����̗l�X�Ȉَ�E���함���Ԃ̊E�ʂ�ΏۂɁA�i�m���x������̉𖾂Ɛv�E����E�n���Z�p�̊m����ڎw�������̊w�ۓI�Ȍ𗬂�}�邱�Ƃ�ړI�ɊJ�Â��ꂽ�B12��11����19���̌������\��7���̃|�X�^�[���\���s���A������[���܂Ŋ����ȓ��_���s��ꂽ�B
�@�ŏ��́u�������E�v�Z�b�V�����ŁA�Z���~�b�N���E�ΐ̓V�~�����[�V�����i������E����A�g���E���j�ASi���E�̃|�e���V������Ǒ���i�A���E���k��j�AZnO���E�̍�����\�d���ώ@�i����E����j�����\���ꂽ�B�����āu���E�E�ّ��E�ʁv�Z�b�V�����ŁAZnO�o���X�^�@�\�𗱊E�̓d���ώ@�E���_�v�Z�E�d�C���������g�ݍ��킹�ĉ𖾂��鎎�݁i������E����j�AZnO��ł̒����������̐����i�勴��E���ދ@�\�j�AAlN/Al2O3�E�ʂ̓d���ώ@�i���{��E����j�����\���ꂽ�B�ߌ�́u�@�B�I�����Eadhesion�v�Z�b�V�����ł́A�E�ʋǏ����͂̌u���g���V�t�g����̑���i�y����E����j�A�j��̓d�����̏�ώ@�i�c����E����j�AAl2O3�^Ni�E�ʂ̑�ꌴ���v�Z�i�{��E�Y�����j�A���̗p�|���}�[�^�Z���~�b�N�ڍ��i�����E����j�����\���ꂽ�B�u�����^���q�E�ʁA�i�m�����v�Z�b�V�����ł́A���q�^�����E�ʂ̑�ꌴ���v�Z�iBelkada��E���u�Ёj�A�J�[�{���i�m�`���[�u�̓d�ɓ��������i�q��E�c���j�A�S�������E�̎��C�����ώ@�i�����E���k��j�APt�����\�ʓd�q��Ԃ̑�ꌴ���v�Z�i�����EJST�E�Y�����j�����\���ꂽ�B�Ō�́u�����^���@�E�ʁv�Z�b�V�����ł́A�����^�_�����i�m�E�ʐG�}�̓d���ώ@�i�H�c��E�Y�����j�APd�^�_���^���O�X�e�����K�X�N���~�b�N�Z���T�[�J���i�����E�����j�AAu/TiC�n�i�m�E�ʐG�}�̓d���ώ@�i�s���E���j�ASiC�^�����E�_�����E�ʂ̑�ꌴ���v�Z�i�c����E�Y�����j�����\���ꂽ�B�܂��A�|�X�^�[�ł́A�_�C�A�����h��Ni���ׂ̋������ߎ��v�Z�i�]�{��E����j�A�t���[�����E�x�A�����O�̕��q���͊w�v�Z�i�I�R��E����j�A�_���^���O�X�e�����̃K�X�N���~�b�N�����i����E���k��j�AZnO�Č����������A�y�сAGaN��MBE�����Ɠ��ʑ̂ɂ��g�U�W������i�勴��E���ދ@�\�j�AAl2O3�^Cu�E�ʁA�y�сAAi���E�s�����Ɖ��̑�ꌴ���v�Z�i���R��E�Y�����j�����\���ꂽ�B�ȏ�̔��\�Ƌc�_��ʂ��ăi�m�E�ʂ̖L���ȋ@�\�Ƒ傫�ȏ������������ł��A����I�ɑ����ċc�_���邱�Ƃ̏d�v�����Ɋ����ꂽ�B
�i���R�����@�Y�����E���r�L�^�X�j
���Z�b�V����P�F�G�A���]���f�|�W�V�����@�^�R�[���h�X�v���[�@�̐V�W�J�@Recent Developments and Future Trend of Aerosol Deposition Method and Conld Spray Method
�{�Z�b�V�����ł́A�G�A���]���f�|�W�V�����iAD�j�@�ƃR�[���h�X�v���[�iCS�j�@�̊�b���牞�p�ɂ܂�����c�_�������ɂȂ��ꂽ�B���ҍu��1���A�I�[����13���A�|�X�^�[6���̍��v20���̔��\���Ȃ��ꂽ�BAD�@��CS�@�́A���q�𐁂��t����Ƃ����_�ŗގ��������@�ł���B�������Ȃ���A����܂ł́A�z�肳���A�v���P�[�V�����̈Ⴂ�Ȃǂɂ��A���v���Z�X�̐��Ƃ��W�܂��čs����Z�b�V�����͍����߂Ă̎��ł���A���̈Ӗ��Ŏh���̂���c�_���ł����Ǝv����B
�@���ҍu���Ƃ��ĐM�B��w�̍�@�a�F�����u�R�[���h�X�v���[�̔疌�����ɋy�ڂ��v���Z�X�p�����[�^�̉e��J�Ƃ����^�C�g���ŁACS�@�ɂ������X�̐��������ƁA�`�����ꂽ���̐����Ƃ̊W��̌n�I�ɏq�ׂ�ꂽ�B����Ɉ��������āA�G�A���]���̗����́A�������ꂽ���q�̑��x�]���A�����q�̔j�x�A�쐬���ꂽ���\����A�������q�𗘗p���������Ȃǂ́A��b�I�Ȍ������\���Ȃ��ꂽ�B�����́A���v���Z�X�̐��ł�������q�̉����̕�������A�쉺�ł��閌�����܂Ŋ܂�ł���A���L���c�_���ł����Ǝv����B
�v���Z�X�̉��p�Ɋւ��ẮAAD�@�̈��d�ޗ��⍂���g���p�̃f�o�C�X�̓d�q�Z���~�N�X�ޗ��ւ̉��p�ȊO�ɁA���̍ޗ��⑾�z�d�r�ւ̉��p�Ȃǂ̔��\���Ȃ���A���p�͈͂̍L�����������������e�ƂȂ��Ă����B���ɁA�Y�����̖p�ڊq����ɂ��AAD�@���ቷ�ŋ����ɒ��ڐ����ł��鎖�𗘗p�������^���x�[�X���X�L���i�[�̌������A���̃R���Z�v�g�Ǝ���f�o�C�X�̊����x�̍����Œ��ڂ��W�߁A�����͏���܂���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�@���@�Y�����j
���Z�b�V����Q�F�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�@Materials Frontier
�{�Z�b�V�����ł͉ߋ����N�ɂ��킽���ĕ��L�����@�ޗ��A�L�@�ޗ��A�����ޗ��A�����̍ޗ��A�����̍ޗ��̍ŋ߂̐i���Ɋւ��锭�\���W���Ă����B������A�������j�ŊJ�Â��A����̍ޗ��W�̔��\�����ꂽ�B�����q�W�̑��̊w��Əd�Ȃ������Ƃ�����A�L�@�ޗ��Ɋւ��錤�����\����N��菭�Ȃ��������Ƃ��ڂɕt�����B
�@�ߋ��̂��̃Z�b�V�����ł̓|�X�^�[���\�݂̂��s���Ă������A����������\���܂߂ĊJ�Â��A�|�X�^�[���\31���A�������\10���i���ҍu��1�����܂ށj�ł������B���ҍu���ł͐É���w�̈Ȑ��搶����u�������������ꂽMn�_���������Ɋւ��錤���̔�Ձv�Ƃ�����ڂ�Mn�_�����������쐻���錤���̏ڍׁA���Ɏ_�f�ʂ̉e���Ƃ��̐���Ɋւ��āA�u�����Ă����������B���̔��\�ł́A���������q�Ǝ_�����̕����ށA�_�����ƗL�@�ޗ��̕����ށA�e�픖���̍쐻�A���ɗp����ޗ��̔��\�Ȃǂ��������B�@
�i�ɌF�טY�@�_�ސ�H�ȑ�j
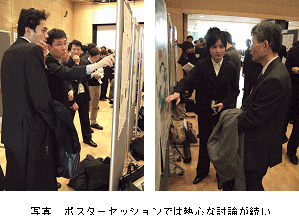
�x�c��勳����Langdon��J���t�H���j�A�勳���Ɂu�@�{�܁v����
�@International Union of Materials Research Society (IUMRS) ��2005�N�@�{�܂�x�c�P����B��w������Terence
G. Langdon ��J���t�H���j�A�勳���́u����Ђ��݉��H�v���Z�X�ƍޗ��J���v�Ɋւ��鍑�ۋ��������ɑ��đ��悷��Ɣ��\�����B������2005�N7��5���C3rd
International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT
2005) & 9th International Conference on Advanced Materials (IUMRS ICAM
2005)�̉�����ɍs�Ȃ�ꂽ�B
�@����Ђ��݉��H�iSevere Pastic Deformation: SPD�j�v���Z�X�Ƃ́C���H���Ă��ޗ��`�ς�炸�������ɔ��ɑ傫�ȂЂ��݂������ł�����@�ł���B�����ޗ��̌������a���T�u�~�N�������邢�̓i�m���x���ɔ��������邱�Ƃ��ł��C�܂��C��2�����q�̑傫���╪�z���i�m���x���Ő���ł���V�����ޗ��g�D����@�ł���B�x�c������Langdon�����́C����Ђ��݉��H�@�̂ЂƂł���ECAP�iEqual-Channel Angular Pressing�j�@��p���Č����������̍œK�������I�ȕ��@���m�������B����ɁC����ECAP�@�Œ����בg�D�ޗ��𑽊�ɂ킽���č쐻���C���̗͊w�������ڍׂɌ��������BECAP�@���܂߂�����Ђ��݉��H�v���Z�X�@�́C���݂ł͑����̌����҂ɒ��ڂ���Ă��āC2005�N9��22���`26���ɂ͖x�c����������s�ψ����Ƃ��ĕ����s�Łu��3�Ђ��݉��H�ɂ��i�m�ޗ����ۉ�c�v(THe 3rd International Conference on Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD 3)���J�Â��ꂽ�B�Q���ґ���223���i�C�O21�������113���C����110���j���W�߂Đ������ɐi�߂�ꂽ�B�ihttp://www.confre.co.jp/nanospd3/�j
To the Overseas Members of MRS-J
���� Thermodynamics as Common Language in Materials Science �c�@p. 1
Dr. Harumi YOKOKAWA, Principal Research Scientist, Energy Technology Research Center, AIST
�@Chemical thermodynamic properties can provide keys in understanding materials
from various kinds of viewpoints. Experimental determination is, however,
time consuming tasks so that many laboratories already disappeared in the
experimental thermodynamics. Even so, they left a large number of the experimental
thermodynamic functions for materials. This should be common properties
to be used in an appropriate way. Attempts have been made to clarify the
interface stability between dissimilar materials with great successes.
Recently, further attempts have been made to bridge the bulk thermodynamic
properties related to phase equilibria and the defect chemical properties
which are essential in understanding microscopic behavior. This attempt
is also leading some interesting success. It is hoped that bulk thermodynamics
will be again targeted by those people who are working in nano-materials
for further development of materials science.
�� The 16th MRS-J Symposium �cp.2
�@In Ochanimizu,Tokyo, in December 9-11, 2005, more than 1000 scientists of all disciplines attended the MRS-J Symposium, which has been held at the Nihon University's Ochanomizu campus. Seventeen symposia with 651 oral and poster presentations highlighted advances in the basic research and applications of advanced materials.
�� IUMRS Somiya Award 2005 �cp.5
�@Professors Zenji Horita of Kyushu Univ. and Terence G. Langdon of Univ.
of Southern California were honoured the IUMRS Somiya Award in 2005 for
their collaboration on severe plastic deformation as a means of processing
materials.
�ҏW��L
�@��16��MRS-J�V���|�W�E�����͓��{��w���H�w���ŊJ�Â���A���N�Ɉ��������A���n�ӔC�҂Ƃ��Ė������Œ���ʂ������Ǝv���Ă��܂��B�����Ԃ̐S�z�́A�|�X�^�[���\�I����A1���ԂŌ������\�p�ɉ��𐮂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃł����B���A���o�C�g�͂قڂ��ׂē������������̊w���ł����B�������Ȃ���A�\�z�ɔ����āA��������30���œ��ꊷ���͏I�������̂ł��B���������܂����B�����������ŁA�w�����m�̎w������ь����A�w�����m�̋��͑̐����������Ă����̂ł��B�����āA�݂Ȃ��݂ȍ�ƏI����i�����}�j�̃C���[�W�������āA�����Ă����̂ł��B�܂��܂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��ȂƁA���������̊w���Ȃ���A�����������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@���āA�����ł͂���܂����A�ŋ߁A��C�u�t�ƂȂ�A��w����ɂ��ĎQ�����A�l���邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�o���ۏ́i�H�j�A��w�@����Ƃ́i�H�j�A���ƁE�C������ۂɋ����Ċw�����Љ�ɑ���o���Ă��邩�i�H�j�A�w���������̌����o�J�ɂ��Ă��Ȃ����i�H�j�B�{�V���|�W�E���̃|�X�^�[���\�Ŋw�����\�ҁi�ꗬ��w�̑�w�@���j�Ƙb�������@�����܂����B���܂�ɂ��������������������̂ŁA����̔����ɑ��āA"�Ȃ��H�ǂ����āH"�Ɩ₢�����܂����B�Ă̒�"����A�E�E�E"�Ƃ����ԓ�����B���_�͎R�قǂ���Ǝv���܂����A���̎��������ɍ��݁A�w���ɂ�����ɂ��������A�����ɐڂ��Ă��������Ǝv���܂����B�@�i��c�W�K�j
�@