
���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.18 No.2 May 2006
�̌��̒~�ς��ɂ��܂��傤

���������H�ƍ������w�Z�Z���@���J�ҋ�
�@�킪���̍ޗ��J���̃��x���͐��E�I�Ɍ��Ă��g�b�v���x���ɂ��邱�Ƃ́A���Ƃ��A���k��╨���ޗ������@�\�̐��E���ł̃����L���O�����ʂł��邱�Ƃł��f����B
�@����ł́A�悭��������Ƃ����20�N�A30�N��̉Ȋw�Z�p�J���̗\���ł́A�ޗ��̊J������̓I�ȃe�[�}�Ƃ��ė���邪�A�U��Ԃ��Č�����ƐV�ޗ��̗\���͕K�������������Ă��Ȃ��B�Z�p�J���A���Ƃ��A�����̋Z�p�ł͘A���I�Ȑi�W�������邪�A�V�ޗ��͓��Ă��āA�s�A���I�ŁA�K�i��ɂȂ�B�ȑO�ɁA��Ƃ̕�����A�ޗ��J���Ɋւ��Đi�W�N��i�ɐ�������̂ɂ͋�J����A�Ƃ̘b�������Ƃ�����B�ܘ_�A�ޗ��̋@�\���P�͍s���Ă��邪�A���P��@�͌�����̂ŁA����قǂ̐i�W�͊��҂ł��Ȃ��B�g����Y�����Ȃǂ�ω������čœK�ȏ�������������@��@��͈ȑO�ɔ�ׂāA�傢�ɐi�������̂ŁA�Z���Ԃ̒B���͋����ׂ����Ƃł���B���Â��b�ł͂��邪�A�������`���Z���~�b�N�X���������ꂽ�Ƃ��ɂ́A�����镪�́A��͎�@����������āA�Z���Ԃł��Ȃ�̍ו��܂Œm�邱�ƂɂȂ����̂͋����ł������B�������A����͍ޗ����̗͂̈�ł̘b�ł����āA���`�����J�j�Y���ƂȂ�ƁA�V���Ȕ��z���K�v�ƂȂ�B
�@�ޗ��J���ɂ͈ȑO����Z�����f�C�v�e�C�iserendipity�j�Ȃ邱�Ƃ������Ă����B�L�����������Ɓu�v��ʂ��̂����R�ɔ�������\�́B�K�^��������́v�Ə�����Ă���B�ޗ��̊J���ł͖ڕW���߂Č�����i�߂Ă����̖ڕW���͊�������Ƃ͌���Ȃ��B�v���W�F�N�g�ł͐������Ă���悤�Ɍ����邪�A�����ނˁA���ʂ������Ă���e�[�}�����グ���邱�Ƃ������A�S�����m�Ȃ���e�̒Nj��͏��Ȃ��B���̂悤�ȃv���W�F�N�g�̏ꍇ�̂˂炢�̈�͊W������Ƃ��W�����Ď�X�̊p�x���瑍���I�ɒT�����邱�Ƃɂ�銮���܂ł̊��ԒZ�k�⍂�������x����������B�����ЂƂ͕��Y���ł���B��������h������e��̐V���ۂ�@�\�A�Z�p�ł���B�ŋ߂͂��̕��Y����ϋɓI�ɕ]�������J��������̂悤�Ɍ�����B
�@�]�Ȋw�҂̖Ζ،���Y���̒����i�u�]�̒��̐l���v�����V���N�����A2005�N�j�̂Ȃ��ŁA�u�v���o�����Ƃ��ɁA�L���͉ߋ���U��Ԃ邾���łȂ������ɉ����N���邩��\�z���邱�Ƃ�A�V�������̂ݏo���n�����̓����Ƃ��W���Ă���v�Ƃׁ̂A�u�����̂Ђ�߂��͑̌����x�[�X�ɂȂ��Ă���v�Ƃ��q�ׂĂ���B�Z�����f�C�v�e�C�͐�ɏ������悤�ȏ����ȋ��R�ɂ��K�^�ł͂Ȃ��u�����̓��̎g�����A�C�̉��ō��E�����B�S��������ŃZ�����f�C�v�e�C�����܂�v�B�s�����Ă����v��ʏo�������Ƃ����킯�ł���B�]�̃��J�j�Y���͕��G�ł��̂悤�ȊȒP�ȕ\���ł͐����ł��Ȃ����Ƃ�Ζؐ搶�ׂ͂̂Ă�����B
�@�܂��A�������F���͑Βk�i�����A���실���u���ɂ����������w����v�����܃v���}�\�V���A2005�N�j�̂Ȃ��ŁA���w�̕���ł̘b�ł͂��邪�A�l�ԂƂ����͉̂����Ȃ��Ƃ��납��V�������̂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�^�̓Ƒn�Ƃ����̂͂��蓾�Ȃ��B�K����ق��̂��̂Ɣ�ׂĂ݂�Ƃ������Ƃ����ł��Ȃ��ƌ���Ă���B
�@�ޗ��J���A���ɐV�@�\�����ޗ��A�V�@�\�Ƃ͉����A����������ł��邪�A�s���̒����猩����\���͍������A����ɋC�Â����ɋ���ꍇ���قƂ�ǂł���B�ق��̂��̂Ɣ�ׂĂ݂�̌���m�����v���o�����Ƃ��s���ł��肻�����B�ޗ��̋���ɂ������ẮA�����̑̌���ʂ��āA�v���o���ׂ������̎�������Ƌ��Ɋώ@�͂��āA�ڑO�ŋN�����Ă��錻�ۂ��ׂ���A�֘A�Â���̌��i�m���j���v���o�����肷�邱�Ƃ��ɂ���ׂ��Ǝv���B����Ɏv���o��w�͂����Ƃ߂��Ă���B
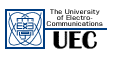 |
ErSiO���i�q���� �\�V���R���t�H�g�j�N�X�Ɍ������V���������ޗ��\ |
�d�C�ʐM��w�d�C�ʐM�w���d�q�H�w�ȏ������@�� �F �G �v
1.�@�͂��߂�
�@�V���R��LSI�i��K�͏W�ω�H�j�̓��[�A�̖@���ɏ]���J�����i�݁A�Q�[�g���̏k�����͗ʎq���E�ɁA�����ăN���b�N���g���͋����z���̓`���ш�̌��E���ނ����悤�Ƃ��Ă���B���̂��߃V���R��LSI�y�уV�X�e���J���ɂ�����p���_�C���V�t�g�������Ă���B�ߔN�A�V���R��LSI�E�V�X�e���Ɍ��z��������u�V���R���E�t�H�g�j�N�X�v������A���āA���{�e����CMOS�v���Z�X�R���p�`�u���̌����g�f�o�C�X�J�����i�߂��Ă���B�������A�V���R�����g�͊ԐڑJ�ڌ^�����̂ł��邽�ߔ����J�ڊm�������ɒႭ�A�����f�q�ޗ��ɂ͓K���Ȃ��B����܂ŃV���R���x�[�X�̔����ޗ��̊J�������͓I�ɍs���Ă������A�܂��L�͂ȍޗ����������Ă��Ȃ��̂�����ł���B
�@���̒��̈�Ƃ��āA�����ƂȂ��y�ރC�I���A���ɃG���r�E���iEr�j�C�I����Si���ɓY�����鎎�݂��Ȃ���A���̔����������ڍׂɒ��ׂ��Ă����BEr�̓V���J�n���t�@�C�o�[�̍Œ�`�������g���ł���1.5��m�тŔ������邽�߁A�G���r�E���E�h�[�v�E�t�@�C�o�[������iEDFA�j�Ƃ��Ĕ���I�Ȑi���𐋂����BEDFA�̏ꍇ�A���g�H���𐔏\m�ƒ������邽�߁Appm�I�[�_�[��Er�h�[�v�ʂŏ\���ȃQ�C���������Ă���B�������V���R���x�[�X�̌��W�σf�o�C�X����邤���ł̓f�o�C�X����mm�ɂ�������K�v�����邽�߁A���̃h�[�v�ʂ�%�I�[�_�[��v����B�������A�P����Si�ɕs�����Ƃ���Er���ŗn���E�i�`0.01%�j�ȏ�h�[�v����ƌ������ׂ�ΐ͂������N�����A1%���x�ɂȂ��Er�C�I���̗�N��Ԃ͋ߐڂ���Er�C�I���Ԃ̃G�l���M�[�`�B�ɂ��A�Ō�ɂ͌������ׂ�ΐ͂ɗ��ꍞ�݁A���J�ڊɘa���Ă��܂��i�Z�x�����j�B
�@�ŋ߁A��X�̃O���[�v��Er���\�����f�Ƃ���15%���x�܂ސV�����ޗ��AErSiO���i�q�����̍쐻�ɐ�������1),2)�B���̌�����Er���\�����f�Ƃ��Ă��邽�߁A�Z�x�����i���J�ځj�̌����ƂȂ錋�����ׂ�ΐ͂��Ȃ����Z�x��Er�Y�����\�ɂȂ�B���̂��߃V���R���t�H�g�j�N�X�ɍ��v�������������̍������^�̔����f�o�C�X�����҂ł���B�{�e�ł̓V���R���E�t�H�g�j�N�X�Ɍ������V���������f�o�C�X�ޗ�ErSiO���i�q�����ɂ��ĊT������B
�@2.�@ErSiO���i�q�����̍쐻
�@ErSiO���i�q�����͓����ASi����ErCl3/�G�^�m�[���n�t��h�z���_�f���͋C900���A3���A���̌�A���S���iAr�j���͋C����1200���A3����2�i�K�M�����ɂ��A���ȑg�D���I�Ɍ`�����ꂽ�B���̂Ƃ���ErSiO���i�q�����̒f�ʓ��ߌ^�d�q�������iTEM�j�ʐ^���ʐ^-1�Ɏ����B���̌����ł͎���0.86nm�̒��i�q�\�����`�����Ă��邱�Ƃ��킩��B���U�t�H�[�h����U���iRBS�j���炻�̑g�����Er:
Si: O��1: 2: 2.4�`4�ƌ��ς����Ă���B����܂ŁA����Ă���ErSiO�n�����͊�y�ތ]�_�����iEr2Si2O7, Er2SiO5�j�ł���A��y�ގ_�����iEr2O3�j�ƃV���R���_�����iSiO2�j�̕����_�����i����q�\���j�ł���A���̉��w�ʘ_��͂��ꂼ��̎_�����̍\���䂪���f���Ă���B����ɑ���ErSiO���i�q������Si�̑g���䂪�����A�_�f�̑g���䂪��r�I�Ⴂ�B�����Er2O3-SiO2�n���}�Ɋ�Â����t�����Ƃ͈قȂ�A�_�f�M������Er-O�O��̂��`������A���̌�̍���������Si�����Si�����������ƂƂ��ɓ���ȔM���t��ԂŌ��������i���̂Ɛ��@�ł���B
�@�ȏ�̋c�_�����Ƃɉ�X��Si���ւ�ErSiO���i�q���������̍쐻���@�Ƃ��ă|�[���X�E�V���R���iPS�j���ނƂ�����@3)�A�]��-�Q���isol-gel�j�@4)�y�їL�@�������q���G�s�^�L�V�[(MOMBE)�@5)���Ă����B�ȉ��A�]��-�Q���@�ɂ��ďq�ׂ�B
�@�]��-�Q���@�͎_���������`���ɓK�������@�ł���A�n�t�����i�K�ŊܗL�����̑g������ȒP�ɐ���ł���B�n�t�����i�K��ErSiO���i�q�������l��Er:
Si��1: 2�Ƃ��ASi���ւ̗n�t�X�s���R�[�e�B���O��A�Q�������Đ������i600���A30���j���s���B���̒i�K��ErSiO�����͔��ł���B����ErSiO���������v���t�H�[���Ƃ��AAr���͋C1250���A30���̎��ȑg�D���i�������j���s�����Ƃɂ��ErSiO���i�q���������邱�Ƃ��ł���BTEM�ώ@�ɉ����A����X����܂̌��ʂ��璴�i�q����0.86nm�̉�܃s�[�N���ϑ�����ƂƂ��ɁA����50nm���x�̔����ɂ����Ĕ��ɔz�����̍��������������邱�Ƃ��킩�����B�܂�����܂ł�Er-O��L����L�@�����ޗ���p����MOMBE�@�ɂ�����Si���ւ̃w�e���G�s�^�L�V���������̉\�����������錋�ʂ������Ă���6)�B
�@3.�@ErSiO���i�q�����̔�������
�@ErSiO���i�q������������Er3+�C�I����4f�d�q���k�J�ځi4I13/2��4I15/2�j�ɋN�����锭���X�y�N�g�����\�����ϑ����ꂽ�B�}-1��PS�@�Asol-gel�@�y��MOMBE�@�ō쐻����ErSiO���i�q�������������20K�i�}-1(a)�j�y�ю����i�}-1(b)�j�t�H�g���~�l�b�Z���X�iPL�j�X�y�N�g���������B20K��PL�X�y�N�g���ɂ����Ĕ��l��1meV�ȉ���8�{�̔����s�[�N���ϑ�����Ă���B�����f�d�q�̑���N��ԁi4I13/2�j�̒ꂩ�猋���ꕪ������ԁi4I15/2�j�ւ̑J�ڂɑΉ�����i�}-1�j�B�����Ώ̈ȊO�̌�����ɂ����Ă��̊���Ԃ̓N���}�[�X�k�d�ɂ��8�i�����Ώ̂�5�j�ɕ��邱�Ƃ��킩���Ă���A���̂��Ƃ�ErSiO�̌������ɔ����ψ�Ȍ�����ɂ��1�̎�ނ�Er�������S���`�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B����ɑ������̊�y�ރh�[�v�����ޗ���K���X�n����ނł́A�s�ψ�Ȍ�����̂��ߔ����X�y�N�g���̕s�ψ�L���肪������\���͊ϑ�����Ȃ��B�����ɂ����Ă����̋ψ�Ȍ�����̌��ʂ͑傫���A�}-1(b)�������Ƃ��蔼�l��4meV�̉s�������s�[�N�����PL�X�y�N�g�����\�����ϑ�����Ă���B�����f�d�q���k�J�ڂ͊i�q�y�уt�H�m���̉e�����قƂ�ǎȂ����߁A�����g���̉��x�ˑ��������ɏ��������Ƃ��m���Ă���B���̂���20K�y�ю����ɂ�����PL�s�[�N�̔g���V�t�g�͊ϑ�����Ă��Ȃ��B�܂��������x�̉��x������20K���玺����1/3�`1/5���x�Ə������B�ȏ�̌��ʂ�ErSiO���i�q���������̍쐻�@�ɂ�炸�ϑ�����Ă���B�����̂��Ƃ���AErSiO���i�q�����͔����g��1.53��m�̍����蔭���ޗ��ł��邱�Ƃ��킩��B
�@4.�@ErSiO���i�q�����̔����̓I����
�@�V���R���E�t�H�g�j�N�X�ɂ����锭���ޗ��Ƃ��ẮAEDFA�̂悤�Ɍ��|���v�ł͂Ȃ��d�C�I�Ȕ������䂪�\�ł��邱�Ƃ��]�܂��B�����ł�ErSiO���i�q�����̔����̓I�����ɂ��ďq�ׂ�B�}-2��ErSiO���i�q���������̌��`���X�y�N�g���y��PL��N�X�y�N�g���������B
�@���`���X�y�N�g���ɂ̓o���h�M���b�v1.1eV���x�ɑΉ�������z���[�����݂��AErSiO���i�q�����������̂ł��邱�Ƃ������Ă���BErSiO���i�q���������̃z�[�����肩��`���^�C�v��p�^�ł��邱�Ƃ��킩��A���̂Ƃ��̎����ɂ�����L�����A���x�́`2�~1019cm-3�A�ړ��x�́`180cm2/V�Es�ł������BPLE�X�y�N�g���ƌ��`���X�y�N�g�����r����ƁA�o���h�\���͂قڈ�v���邪�APLE�X�y�N�g���ł͂���ɏd���s���z���s�[�N������Ă���B���̂��Ƃ�ErSiO���i�q�����ɂ�����Er3�{�C�I���̗�N�ߒ���2���݂��邱�Ƃ������Ă���i�}-2�j�B��߂́AEr3�{�C�I���̒��ڌ��z���i4I15/2��4I11/2�j�ɂ���N�ߒ���PLE�X�y�N�g���ɂ�����s���z���s�[�N�ɑΉ�����B�������ErSiO���i�q�������Ɍ���N���ꂽ�d�q-���E�̍Č����G�l���M�[��Er3�{�C�I����4f�d�q�ɓ`�B�����ߒ���PLE�X�y�N�g���ɂ�����u���[�h�ȋz���o���h�ɑΉ�����B�z���s�[�N�g���ł͒��ڋz���ߒ��̕���4�{���x�����͗ǂ����A�d�q-���E�̍Č����ɂ��Ă͍L���X�y�N�g���ł̓`�B���\�ƂȂ�B�܂�PL�X�y�N�g���̗�N�g���ˑ����ׂ����ʁA��N�ߒ��̈Ⴂ�ɂ��PL�X�y�N�g�����\���̕ω��͌����Ă��Ȃ����Ƃ���A��N�ߒ��ɂ�炸�����Er�������S����N����Ă�����̂ƍl������B�ȏ�̂��Ƃ́A�����̂ł���ErSiO���i�q�����ł͓d�q-���E�̍Č����ɂ������̗ǂ�Er3�{�C�I���̗�N���\�ł��邱�Ƃ������Ă���B���Ȃ킿�d�������^�̔����f�o�C�X�A�����_�C�I�[�h�iLED�j�₳��ɂ͔����̃��[�U�[�iLD�j�J���̉\��������������̂ł���B
�@5.�@������
�@�{�e�ł́u�V���R���E�t�H�g�j�N�X�v�̂��߂ɉ�X���V�����J������ErSiO���i�q�������Љ���B���̌����̓����͎���0.86nm�̒��i�q�\���������AEr���\�����f�Ƃ���15%���x�܂�ł���Ƃ���ɂ���B�P�������ɔ����ψ�Ȍ�����ɂ��AEr3�{�C�I����4f���k�J�ڂɋN������PL�X�y�N�g�����\�����ώ@����APL���������͉��x�ɂقƂ�Ljˑ����Ȃ��B����ɁAErSiO���i�q�����͔����̓I�����������AEr3�{�C�I����4f�d�q���z�X�g�̓d�q-���E�ɂ������̗ǂ���N���\�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�ȏ�̌��ʂ�ErSiO���i�q�������V���R���E�t�H�g�j�N�X�ɂ�����d�������^�����f�o�C�X�̍ޗ��Ƃ��ėL�]�ł��邱�Ƃ������Ă���BErSiO���i�q�����͕M�҂̒m����肱��܂łɕႪ�Ȃ��A�]���̊�y�ތ]�_�����Ƃ͂Ƃ͂܂������قȂ錋���ł���A�����w�I���n����������[���ޗ��ł���B
�Q�l����
1) H. Isshiki, A. Polman and T. Kimura, Fine structure in the Er-related emission spectra from Er-Si-O complexes at room temperature under carrier mediated excitation, J. Luminescence, 102-103, 819 (2003)
2) H. Isshiki, M.J.A. de Dood, A. Polman and T. Kimura, Self-assembled infrared-luminescent Er-Si-O crystallites on silicon, Applied Physics Letters, 85 (19), 4343 (2004)
3) T. Kimura, K. Ueda, R. Saito, K. Masaki and H. Isshiki, Erbium-silicon-oxide nano-crystallite waveguide formation based on nano-porous silicon, Optical Materials, 27, 880 (2004)
4) K. Masaki, T. Kawaguchi, H. Isshiki and T. Kimura, The effect of annealing conditions on the crystallization of Er-Si-O formed by solid phase reaction, Optical Materials, 28, 831 (2006)
5) K. Masaki, H. Isshiki and T. Kimura, Erbium-silicon-oxide crystalline films prepared by MOMBE, Optical Materials, 27, 876 (2004)
6) H. Isshiki, M. Masaki, K. Ueda, K. Tateishi and T. Kimura, Towards epitaxial growth of ErSiO nanostructured crystalline films on Si substrates, Optical Materials, 28, 855 (2006)
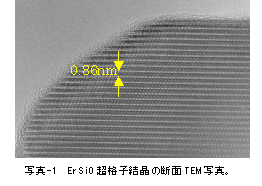
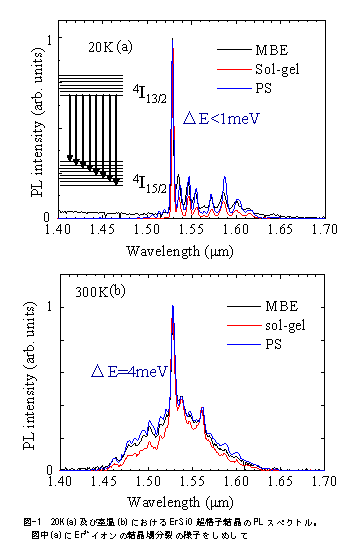
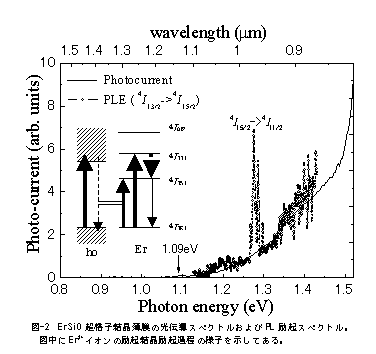
 |
���c�@�l ���P�x���Ȋw�����Z���^�[�� ��^���ˌ��{��SPring-8 |
���c�@�l���P�x���Ȋw�����Z���^�[�L���E�����핔���Ȍ������@���@�@�� �O
�@1.�@�͂��߂�
�@��^���ˌ��{��SPring-8�iSuper Photon ring 8 GeV�j�͐��E�ō����\�̕��ˌ������邱�Ƃ̂ł����^�̎����{�݂ł���A���Ɍ����d���ɂ���B���{���q�͌������Ɨ����w�������������Ō��݂��A���P�x���Ȋw�����Z���^�[�i����JASRI: Japan Synchrotron Radiation Rsearch Institute�j��1997�N10�����狤�����p�{�݂Ƃ��ĉ^�]�E�ێ��E�Ǘ����A�����҂̗��p�ɋ�����Ɩ����s���Ă���i�ʐ^-1�j�B
�@���ˌ��́A���G�l���M�[�̓d�q�����ꓙ�ŋO�����Ȃ���ꂽ�Ƃ��ڐ������ɕ��o�����d���g�̂��ƂŁA1947�N�Ɋϑ�����Ă����60�N�ɂȂ�B���ˌ��͊����̌����Ɣ�ׂāA�@�ɂ߂Ė��邢�i�P�x�������j�A�A���r�[�����ׂ��i���Ă��čL����ɂ����i�w�����������j�A�BX������ԊO���܂ł̍L���g���̈���܂ށA�C�Ό����Ă���A�D���ɒZ�����ԃp���X�̌J�Ԃ��ł���A�Ȃǂ̓���������B
�@2.�@SPring-8�̓���
�@SPring-8�̉�����{�݂͐��^������A�V���N���g�����A�~�σ����O�ō\�������B�~�σ����O�ɓ��ˁE�~�ς��ꂽ8GeV�̍��G�l���M�[�d�q�r�[���́A�~�σ����O�������Ȃ���Ό��d����}�������i�A���W�����[�^��E�B�O���[�j�ŋO�����Ȃ����邽�тɕ��ˌ�����������B�����������ˌ������o���ė��p���邽�߂̑��u���r�[�����C���ł���A��`�����l���A���w�n�b�`�A�����n�b�`����Ȃ�B�Ό��d���܂��͑}�������Ŕ����������ˌ������w�n�b�`�Ő��`������A�����n�b�`�ɓ����A�����ɏƎ˂��Ď�������B���̂悤�ȃr�[�����C����62�{�܂Őݒu�ł��邪�A����48�{���ғ����ł���B
�@SPring-8�̎�ȃp�����[�^��\-1�Ɏ����BSPring-8�͕��ˌ���p�̒~�σ����O�Ƃ��Ă͐��E�ő�̓d�q�G�l���M�[�ƍő�̎�����L���A���O�ȃ}�V���X�^�f�B�[�̌��ʓd�q�r�[���̐��\�i�G�~�b�^���X�A�o���`�̏��x�A�r�[�������A�r�[���d���A����x�Ȃǁj�͕����ǂ��萢�E�ō������ƂȂ��Ă���B�N�Ԗ�5,300���ԉ^�]���A���̂�����4,000���Ԃ����p�҂ɒ���Ă���B
�@SPring-8�ɂ͑����̓����̂���}���������ݒu���ꗘ�p����Ă���B�d�q�r�[�����ʉ߂���^�Ɏ������߂�^�~�^�̃A���W�����[�^��W���^�A���W�����[�^�ɍ̗p���邱�ƂŁA���Η�Ԃ̃M���b�v���������A���̌��ʎ��Ύ�����Z�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B���̔z�u�̍H�v�Ő����Ό��A�w���J���^�A�ϕΌ��^�A8�̎��`�A���{���o�[�^�ȂǁA�Ό������Ȃǂō����\�Ȃ��̂��ݒu����Ă���B�܂����������ɂ͐��E�Œ�25m�̒��ڃA���W�����[�^���ݒu����Ă���B
�@���ˌ��𗘗p���邽�߂̃r�[�����C���ɂ́A�{�ݎ҂��ݒu���đ����̃��[�U�����ԂɎg�p����u���p�r�[�����C���v�A����̃��[�U�����������̕��S�Őݒu���Đ�p�Ɏg�p����u��p�r�[�����C���v�A�u�����̃r�[�����C���v������B
�@���p�r�[�����C����JASRI���Ǘ��^�c���Ă���A�N2��ۑ�̕�W�����ĉۑ�I��ψ���ō̑����ꂽ�����ɗ��p�����B�ۑ�͐����Ȋw�A�U���E��܁AXAFS�A�����A�����Z�p�A�Y�Ɨ��p�ɕ����ĐR�������B��p�r�[�����C���͌���9�{�ғ����Ă���B���p�����͋��p�ł���p�ł����ʂ����\�i���ʔ��L�j����Ζ����ł���B
�@3.�@JASRI�ɂ����錤��
�@JASRI���Ǘ��^�c���Ă���SPring-8�͐��E�ꍂ���\�̌�����������̂���ԑ傫�Ȗ����ł���B�Ő�[�̉Ȋw�Z�p�̎��������邽�߂̍ō����\�̓�������B����䂦�ASPring-8�ɂ����錤���̑����͊O���̗��p�҂��S���Ă���BJASRI�ł����匤���ɂ͗͂����Ă��āA���ˌ���p�������������邪�AJASRI�ł̌����͓���Ƃ��ċ���������̐��\���悭���邽�߂̌��������S�ł���B�����Ă������Ƃ��ĒS���Ă���̂����ˌ��������̉����핔��A�r�[�����C���Z�p����A���p�������i����A�Y�Ɨ��p���i���ł���B�e��������̓O���[�v�E�`�[������~���Ă���B
�@(1)�@�����핔��
�@�����핔��̖����́A���^������A�V���N���g�����A�~�σ����O���̉�������^�]�E�ێ��E�Ǘ����āA����ō����\�̕��ˌ����������邱�Ƃł���B�����핔��͉^�]/�O����́A����A���^������A�����O�������4�̃O���[�v������A���ꂼ��̉��ɂ������̃`�[��������B
�@�����핔��ɂ����錤���J���́A������̉^�]�ɔ������̂Ƃ��āA���^������E�V���N���g�����E�~�σ����O�̉^�]�E�����̍��x���A�r�[���s���萫�̗}���A������f�f�Z�p�̊J���A�O�����萫�̉��P�A����n�̍��x���A�����\�d�q�e�̊J���A�Z�p���X�r�[���̐����̌����A���ː�������^��̉��P�A�����̉��P�A�@��̐U���̗}���̌����A���`���E�C�O���[�̊J���A�d�q�r�[���̒�G�~�b�^���X���A�g�b�v�A�b�v�^�]�ȂǁA������Ƃ��Ă̐��\�����߂錤���������s���Ă���B
�@(2)�@�r�[�����C���Z�p����
�@�r�[�����C���Z�p����́A�r�[�����C���̉^�]�A�ێ��Ǘ�����э��x���A�r�[�����C���Ɋւ��錤���A�{�ݗ��p�̋Z�p�w������ыZ�p�x���A�Z�p���̃f�[�^�x�[�X���A�����s���A�����E��`�����l���A�����n�E�A���`�����l���A����A���ʋZ�p�J���A���ʋZ�p�x����5�̃O���[�v���琬��B����25�̒������ɑ}���������ݒu����A�����̂���}�������̊J���i�Ό������A�Z�M���b�v�j�A���ꑪ��A�O���ϓ��̕�A���������A�Ό��x�̑���Ȃnj����̐��\���P���s���Ă���B���w�n�E�A���`�����l���ɂ�����@��J���ł����w�f�q�̗�p�n���P�A�~���[�̍��x���A���w�n�̐U���}���A���ˌ������o���x�����E�����̕��R���Ȃǂ��s���Ă���B�܂����ˌ��̑����A���o��̊J�����s���Ă���B
�@(3)�@���p�������i����
�@���p�������i����́A�\�������T�A�\�������U�A�\�������V�A���������T�A���������U�A�\�������A�C���[�W���O��7�O���[�v����Ȃ�A���ꂼ��̉��Ƀ`�[��������B
�@����̊e�O���[�v�͕����̃r�[�����C����S�����Ă���A�r�[�����C��1�{1�{�������Ȃ̂ŁA�ʏ�̋K�͂̌������ɑΉ�����̂�������Ȃ��B���p�x���ƋZ�p�x���Ɩ��̑����������s���A�{�ݗ��p�̋Z�p�w���ƋZ�p�x���A���ˌ���p����������@�̌����A���ˌ����p�����A���ˌ��̔����E���p�Z�p�Ɋւ��錤���Ȃǂ��s���B
�@�Y�Ɨ��p���i���͎�ɎY�Ɨ��p�̎x�����s���Ă���B�R�[�f�B�l�[�^���x���[�����đΉ����Ă���B
�@���݁A���p�����ɐ헪�I�Ȋϓ_�����A�V���ȗ��p�҂̎Q���𑣂��A�Y�Ɨ��p���i�E�{�i�I���p���ɉ������g�D�̉��v���s���A�������ʂ̍ő剻��ڎw�����d�_�I�Ȍ������i�ƃv���W�F�N�g�����̎��{�A�R�[�f�B�l�[�^���x�̏[���A�{�݂̍��x���̑��i�ȂǂőΉ����Ă���B�\-2��SPring-8�Ō��݉ғ����̃r�[�����C���Ƃ��̎�Ȍ������e�������B�܂��A�ʐ^-2�Ǝʐ^-3�ɒ~�σ����O�����z�[���̃r�[�����C���Ǝ����n�b�`�̗�������B�r�[�����C�����̎d�l��������Ă��鑪�葕�u�A���p�̎����ʂ̓z�[���y�[�W�ɏڍׂ��f�ڂ���Ă���̂ŎQ�l�ɂ��ė~�����ihttp://www.spring8.or.jp/)�B
�@4.�@����̉ۑ�
�@SPring-8�͋��p�J�n�ȗ������ɉ^�]�E�ێ��E�Ǘ�����Ă����B�������A���ݑ傫�Ȑߖڂ��}���Ă���BJASRI�ƎO�҈�̂Ō����E�^�c�����s���Ă��������E�����̓Ɨ��s���@�l���ł���B2005�N10���ɂ͌��������q�͌����J���@�\�ƂȂ�SPring-8�̉^�c���������������Ƃł���B�����2007�N7������AJASRI�͂���܂Ŏw��@�l�Ƃ���SPring-8���Ǘ��E�^�c���Ă������o�^�@�l�ƂȂ�B����炪SPring-8�̉^�c�ɑ傫�ȉe����^���邱�Ƃ��\�z�����BSPring-8����芪���l�X�Ȋ��̕ω��ɂ��S��炸�A�ݔ��E����@�퓙�𐢊E�ō����\�ɕۂ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Č����Ȍ������ʂ邽�߂ɂ̓C���n�E�X�E�X�^�b�t�ɂ�錤���J�����d�v�ł���A������E�����Z�p�E������@�̍��x���Ɍ����������ۑ��n���Ɏ��{���Ă������Ƃ����܂ňȏ�ɏd�v�ł���Ǝv����B
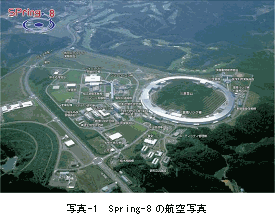
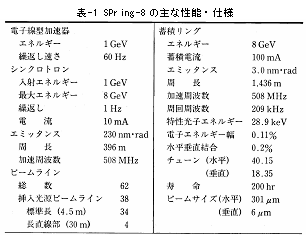
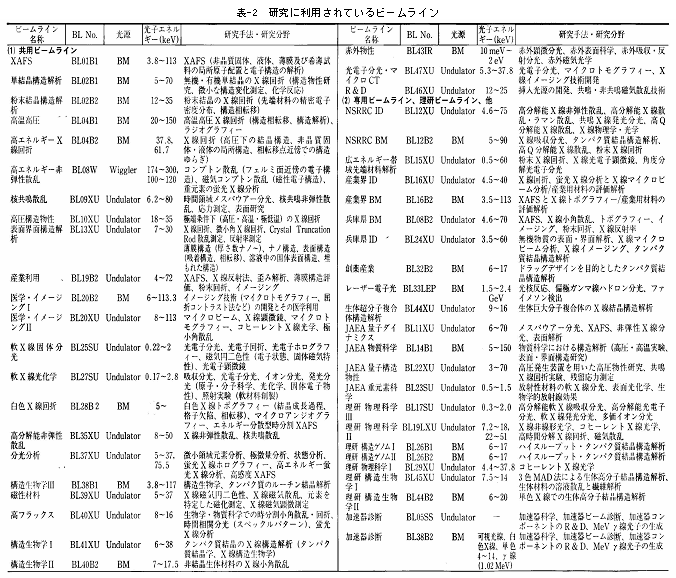
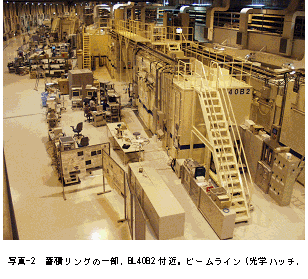
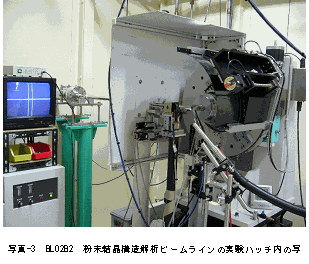
�����ē�
�� �w�p�V���|�W�E���Z�b�V�����e�[�}����у`�F�A���傲�ē�
��17����{MRS�w�p�V���|�W�E���\�C�m�x�[�V�������擱�ޗ������\
��ÁF���{MRS�ihttp://www.mrs-j.org/)
�����F2006�N12��9��(�y)�`10��(��)
�ꏊ�F���{��w���H�w���x�͑�Z��1���فi��101-8308 �����s���c��_�c�x�͑�1-8-14�j
�Z�b�V��������
�@��17����{MRS�w�p�V���|�W�E���̃Z�b�V�����͑g�D�ψ���ł̊��ƂƂ��Ɍ�����t���܂��B�Z�b�V�������Ă��������́A�Z�b�V�������A�����̃Z�b�V�����`�F�A�i��\�`�F�A1���A�A���`�F�A1�����܂ށj�A�Z�b�V�����̃X�R�[�v�i���{��500������щp��200��ȏ�j�A�\�z����锭�\�����i�����A�|�X�^�[�j�����āA5��10���܂łɃV���|�W�E�������ǂɂ��\�����݂��������B
�@�Ȃ��A�@�Z�b�V�����`�F�A�\�������ۓI�ł���A�A�v���[���e�[�V�������p��ōs���A�̗v�������Z�b�V�����́A�u���ۃZ�b�V�����v�Ƃ݂Ȃ��A�w�p�V���|�W�E���̑O��̓����̃T�e���C�g�R���t�@�����X���̕X���}�邱�Ƃ��g�D�ψ���Ō������Ă���܂��̂ŁA�Y������ꍇ�́A�Z�b�V�����\�����݂̍ۂɁu���ۃZ�b�V������]�v�Ɩ��L���Ă��������B
�u����W
�@�������\����]����邩���́A���{MRS�̃z�[���y�[�W�ihttp://www.mrs-j.org/�j�́A��17����{MRS�w�p�V���|�W�E���̍����́A�I�����C���������\�\�����݂̃y�[�W��艺�L�̒��؊����܂łɂ��\�����݉������B�����L�ځu��o��F�A��Chairperson�ꗗ�v�̊e�Z�b�V�����̘A���`�F�A���Ɏ����I�ɑ��M����܂��BHP�������p�ɂȂ�Ȃ����́A�e�Z�b�V�����̘A���`�F�A�܂ł��₢���킹�������B�܂��A�u���̍̔ہA���ҍu���E�������\�E�|�X�^�[���\�̋敪�́A�e�Z�b�V�����`�F�A������v���܂��̂ŁA������̂��₢���킹���A�e�Z�b�V�����`�F�A���ɂ��肢�v���܂��B
�e����؊���
�Z�b�V������Ē��@�@�@2005�N5��10��(��)
�������\�\�����@�@�@�@2005�N9��29��(��)
�I�����C���Q���\�����@2005�N11��17��(��)
Proceedings��o���@�@�������\����
���{MRS�w�p�V���|�W�E�����s�ψ���
���s�ψ����F����@���i���É���j
��抲���F���c�K���i���ދ@�\�j
���S���F�R�{�@���i���嗝�H�j�A�ݖ{�����i���ދ@�\�j�A��؏~�j�i���l����@�j
���n���s�ψ����F��c�W�K�i���嗝�H�j
�L��S���F�ݖ{�����i���ދ@�\�j
�|�X�^�[�E����ܒS���F�ɌF�טY�i�_�ސ�H�ȑ�j�A�����g�j�i���H��@�j
�o�ŒS���F�ߌ��h�́i���H��@�j�A�Ɉ䂳�Ƃ݁i���H��j
���{MRS�����ǁF���È�i�����ǒ��A���ދ@�\�j
�⍇����
��305-0047�@��錧���Ύs�猻1-2-1�����E�ޗ������@�\�G�R�}�e���A���Z���^�[�E���È�AE-mail: mrsj2006��nims.go.jp
�Q�l�i�ŋ߂̊J��Session�e�[�}�ꗗ�����L�Ɏ����܂��j
�E��16��
�u�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��v�i���ہj/�u���q�������̍쐻�E�]���E���p�\���x�Ȕz������A�z����́A����ы@�\������ڎw���ā\�v/�u���ȑg�����ޗ��Ƃ��̋@�\�@�Z�v/�u��炵��L���ɂ���ޗ��\���E�G�l���M�[�E��Á\�v/�u�M�d�ϊ��ޗ��̐V�W�J�`�ޗ��E�f�o�C�X�E���_�`�v/�u��i�i�m�X�P�[���\���́@�|�\���Ɛ����̑��ց|�v/�u������d�q�f�o�C�X�̂��߂̗U�d�̔����Z�p-�E�ʁE�i�m�\������-�v�i���ہj/�u��[�v���Y�}�Z�p���i�m�}�e���A���Y�t�����e�B�A�v�i���ہj/�u�i�m�\���ƕ����@�\�����v/�u�擱�I�o�C�I�C���^�[�t�F�C�X�̊m���v/�@�u�C�I���r�[���𗘗p�����v�V�I�ޗ��v/�u������G�R�}�e���A���\�����a�^���@�\�G�l���M�[�ޗ��\�v/�u�@�\���\�t�g�}�e���A���Ƃ��Ă̍����q�Q���v/�u�����n�����̍ŋ߂̐i���v/�u�i�m�E�ʂ̐V�@�\-���w�I�E�@�B�I�E�d�q�I�@�\�̉𖾂Ɛv�v/�u�G�A���]���f�|�W�V�����@/�R�[���h�X�v���[�@�̐V�W�J�v/�u�}�e���A���Y �E�t�����e�B�A�v
���15��
�u�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��v/�u�L�@�������̍쐻�E�]���Ɖ��p�\���x�ȕ��q�z��E�z�������ڎw���ā\�v/�u���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\VI�v/�u��炵��L���ɂ���ޗ��\���E�G�l���M�[�E��ÁE�����\�v/�u�M�d�ϊ��ޗ��\�i�m�\������ɂ�鍂�������v/�u�t�@�u���P�[�V�������w�������i�m�X�P�[���\���̂̍쐻�Ɛ����\�i�m���q����~�N���g�D�̂܂Łv/�u������d�q�f�o�C�X�̂��߂̗U�d�̔����Z�p�v/�u��[�v���Y�}�Z�p���i�m�}�e���A���Y�t�����e�B�A�v/�u�i�m�\���Ƌ@�\�����v/�u�����K�������q�i�m�ޗ��̍\������Ɠ��I�@�\�v/�u�C�I���r�[���𗘗p�����v�V�I�ޗ��v/�u������G�R�}�e���A���\�����a�^���@�\�G�l���M�[�ޗ��\�v/�u�\�t�g�E�i�m�E�}���`�R���|�[�l���g���D��Ȃ����l���\���f�I�Ȕ��W��ڎw���ā\�v/�u�����������p�Z�p�̍ŋ߂̐i���v/�u�v�Z�ޗ��Ȋw�̍ŋ߂̐i���v/�u�G�A���]���f�|�W�V�����@�̌���Ƃ��̓W�J�v/�u�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�E�|�X�^�[�v
���14��
�u���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\V�v/�u�X�}�[�g�}�e���A���E�X�g���N�`���[�v/�u����ɂ��\���A�g�D�A�@�\����v/�u�i�m���[�^�[�X�P�[���R�q�[�����g��N�n�v/�u�L�@�������̍쐻�ƕ]���\���q�z��E�z������̊ϓ_����\�v/�u�\�t�g�n�t�v���Z�X�𗘗p�����ޗ��n���v/�u��炵��L���ɂ���ޗ��\���E��ÁE�����\�v/�u����i�m�\���̂̃f�U�C���Ɠ����v/�u�A���n�ޗ��̍ŋ߂̐i���v/�u�R���d�r�ޗ��v/�u�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��v/�u���E�̈�Ƃ��ẴQ���̉Ȋw�ƍH�w�\����̉Ȋw�����[�E���Ȋw�܂Ł\�v/�u�X�p�b�^�@�ɂ�锖���쐻�Z�p�v/�u�C�I���H�w�𗘗p�����v�V�I�ޗ��v/�u�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�E�|�X�^�[�v
����P�V��@�N������̊J�Âɂ���
���{MRS��@����@��
�q�[�@�����܂��܂������h�̂��ƂƂ���ѐ\�������܂��B���������{MRS�̊����Ɋւ��܂��āA���s�͎��芴�Ӑ\���グ�܂��B
�@���āA�����ł����A���{MRS��P�V��N����������L�v�̂ɂĊJ�Òv���܂��B���܂��ẮA��ς��萔�ł����A���o���̂��s����ʎ��̏o���͂ɂ��L���̏�A 5��18��(��)�ߌ�R�����ɁA�����Lj��ɂ��ԐM�������܂��悤���肢�\���グ�܂��B
�@���A�����Ȃ̏ꍇ�́A�ϔC�ɂ����L���̏ゲ�ԐM�������܂��悤�A���킹�Ă��肢�\���グ�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��
�@�@�@�@�@�@�@�@�L
�@�����F2005�N5��19��(��)�@13:00?
�@�ꏊ�F(��)�����Ȋw�Z�p�����c��
�@�@�@�@��105-0001�@�����s�`��Ճm��2-5-5�N�r���X�K
�@�@�@�@Tel :03-3503-4681�@Fax :03-3597-0535
�@�c���F
�@�@1. ��P�V���ƔN�x�@���ƕ�
�@�@2. ��P�V���ƔN�x�@���x��
�@�@3. ��P�W���ƔN�x�@���ƌv��
�@�@4. ��P�W���ƔN�x�@���x�v��
�@�@5. ��P�W���ƔN�x�@�����I�C
�@�@6. ���̑�
To the Overseas Members of MRS-J
��Be Sure to Accumulate Many Different Experiences�@�cp.1
Dr. Nobuyasu MIZUTANI, President, The Tokyo National College of Technology
�@We often have encountered to make material developments, especially to discover new functions and phenomena, through experiences and actions in the various fields. We know that the possibility to win a discovery or new idea seems to be high during various actions. However, in almost cases, we do not notice that we are meeting or encountering a opportunity or scene of discovery, and are hitting new idea and fine conception. On considering these processes, it is indispensable to recollect past experiences and knowledge which are comparable with the problems and phenomena before us. It is very important to try to accumulate many experience and knowledge for presentment and also to exploit the capability of observation on phenomena. In the education for material science and engineering, it is required to try to make experiments of student own motion.
��ErSiO Superlattice Crystal: A Novel Light Source Material for Silicon Photonics�cp.2
Professor Dr. Hideo ISSHIKI, The University of Electrocommunications
�@An ErSiO superlattice crystal that we have newly developed for �gsilicon photonics�h is introduced here. To mention the particular features, this material has a superlattice structure with 0.86-nm period and a large amount of Er�i�`15%�jas its constituent. Due to homogeneous crystalline filed by the single crystalline nature, fine structures of photoluminescence�iPL�jspectra of the 4f-intra-shell transitions in Er3+ ions are observed. The PL characteristics hardly depend on temperature. In addition, the ErSiO superlattice crystal behaves as a semiconductor and the Er 4f-electrons are excitable by electron-hole pairs in the host. These results suggest that the ErSiO superlattice crystal is the strong candidate for the light source material of silicon photonics.
��Japan Synchrotron Radiation Research Institute and SPring-8�cp.5
Dr. Masahiro HARA, Director of Public Relations Office, Chief Scientist, JASRI
�@SPring-8, the most powerful synchrotron radiation facility is operated by Japan Synchrotron Radiation Research Institute�iJASRI�jfor almost a decade and have provided users with highly brilliant X-rays stably. The specification of SPring-8 accelerator complex and the performance of the SPring-8 synchrotron radiation are described. SPring-8 is a big facility basically open to users and 48 beamlines are now available. Each beamline corresponds to usual laboratory. Here explained the mission of JASRI, how SPring-8 is managed, how the research and experiments at SPring-8 are performed.
��Call for Proposals of Subjects and Session Chairs�\The 17th Annual Symposium
of the MRS-J�cp.7
�@The 17th Annual Symposium of the MRS-J will be held at the Ochanomizu Campas of the Nihon University in Ochanomizu, Tokyo, on December 9-10, 2006.
�@The symposium includes a number of sessions. The symposium committee is now inviting members�f proposals of the subjects and session chairs to be presented at the 17th symposium of the MRS-J. Proposals should be sent to http://www.mrs-j.org/
�ҏW��L
�@�{�N�x���M���M���̃X�P�W���[���̒��A�Ȃ�Ƃ���2���̔��s�ɂ������܂����B�䑽�Z���ɂ�������炸���������M���������������搶���ɐ[�����\���グ�܂��B���������e���o�ŎЂɓn���������A����S����Ђ���Â����40�L���̎R�x�E�H�[�L���O���ɏo�ꂵ�Ă��܂����B����l�̎Q���҂̕��ϔN��͂����炭50��A���ʂ��������ł͂���܂��A30��̕M�҂͎���̕����X�s�[�h�̑����Ɉ��R�Ƃ��Ă��܂��܂����B�S�[������������R�ƒk���Ă���N�y�̕����ڗ����܂����B�ŋ߃v���X�|�[�c�E�ł͒��������𑱂��Ȃ��琬�т����ȍō����X�V����I�肪���ڂ���Ă��܂����A��ʂɂ������̂������l�����݂��邱�Ƃ�F�����܂����B�����Ԃɓn��ؓ��ɂɔY�܂���Ȃ�����X�̐ߐ��ƃg���[�j���O�̐ςݏd�˂̏d�v�������߂Ċ����Ă��܂��B�i����)
�@