
���{�l�q�r�j���[�X�@Vol.19 No.1 February 2007
���{�̔����ޗ��Ɏv����
���V�d�@������ЋZ�p�J���������E�����@�@�����@�@��

�@�Ⴆ�Όő̍ޗ��́A���q�E���q���K���������z�Ă���ƌ���������A���̌����\�����ς��Ό��q�E���q������ł��ő̂̐����͑傫���قȂ�B�ȒP�ȗ�ł͂��邪�A�V���R���Ǝ_�f�̉��������ɂƂ�A�P�����̐����́A���̃K���X�ɔ�ׂēd�C�`���x�͍������A���z���͏��Ȃ��B�����̌ő̍ޗ��́A���̌����\����ω������邱�Ƃł��̂悤�ɋ@�B�I�A�d���C�I�A���w�I�A���w�I���̗l�X�Ȑ�����ω������邱�Ƃ��m���Ă���A�����̍\���������g�����V�����ޗ������X�Ɛ��܂�Ă����B�V�����ޗ��́A�����܂łɑ����̎Y�ƊE�����[�h���Ă����ƌ����A�܂��ɍH�Ƃ̔��W�̍���ɍޗ��Ȋw�̐i�����K�v�����ł��������͘_��҂��Ȃ��ƌ����悤�B
�@���̂悤�ȍޗ��Ȋw�̔��W�́A�ő̕\�ʂ̍��@�\���Ƃ����j�[�Y�Ŋ��p�����悤�ɂȂ����B�^��Z�p�̔��W�Ƌ��ɂ����锖���ޗ��Ƃ��ď��X�Ɏp��ς��Ă����B�����A�ő̕\�ʂ��֗^���镪��͔��ɍL�͈͂ɓn���Ă���B������̕�����\�ʌ��ۂ��Ȋw�I�ɉ�͂��A�u�\�ʂ̐v�Ɖ��H�v�Ƃ����w�͂��Ȃ���Ă���B���ł����̒��Ƃ�������\�ʉ��H�Z�p�ł́A�����I�A���w�I�A�@�B�I�ȑ����̎�i��g�ݍ��킹���l�X�ȕ\�ʉ����Z�p���a�����āA���ꂼ��̖ړI�ɉ����čœK�ȕ��@�����p����Ă���B�]������̂߂�����h���ɑ�\�����悤�Ȕ������`�����ĉ������鐬���@�A�Z�Y�⒂���@�ɑ�\�����v���Y�}��C�I���̒����ɂ��\�w�����@�A����ɂ����̋Z�p���n�C�u���b�h���������@�ȂǁB���ł������@�͑����̕���Ŏg���Ă���Z�p�ł���A�i�m�}�e���A���ɑ�\�����悤�ȃ~�N���Ȑ����K�v�Ƃ��锼���̂��Õ���̐��E����A�@�B���H�Z�p�ɕK�{�ƂȂ�n�[�h�R�[�e�B���O�܂ŁA�L���H�ƕ���Ŏ��p������r���𗁂тĂ���B���ɓ��{�ł́A�Â��́f60�N��̃T���V���C���v��ɂ�����v���Y�}�Z�p��p�����������z�d�r�̂��Ƃ��A�����ޗ��̊J���͋ɂ߂đ�����������Y�Ɖ��p��ڎw���Ĕ��W���A���ł��ޗ��A���u���ɂ��̋Z�p�I�D�ʐ��͔��ɍ����B�Ƒn�I�Ȕ��z�̌��ɐ��E�����[�h�����鑽���̌������ʂ݂����A���E�I�Ɍ��Ă������ė�鎖�̂Ȃ��Z�p���x���ł���Ƃ͌����߂����낤���B
�@�Ƃ���ŁA���̂悤�ȗD�ꂽ�����ޗ��Z�p����葽���̎s��Ŋ��p����邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ肪����B����̓R�X�g�A�����鐶�Y�Z�p�̔��W�ł���B���Ĉ������ׂɃA�W�A�ɍH������݂��A�����Ȑ��i�����{�֗���ė���悤�ɂȂ����B�₪�āA���n�̐������x�������サ�đ傫�Ȏs����`������悤�ɂȂ�ƁA�����̍H��͌��n�����̐��Y�H��ւƕς���Ă������B�����č��⑽���̐��i�������Ő��������悤�ɂȂ�A��X�̓��퐶���ɂ����Ă��������֗^���Ă��Ȃ����i��������͓̂���B�����֘A���i�ɂ��Ă����l�ł���B�����ł��邪�A��N�x�A�����̑�A�ŊJ�Â��ꂽ�����^���Â̑S�������Z�p������ɃQ�X�g�X�s�[�J�[�Ƃ��ĎQ������@��Ɍb�܂ꂽ�B�����S�y�̔����ޗ��W�̎�Ȍ����҂��W���A2���Ԃ�100���ȏ�̌������\�����{����A���������ł͔�r�I�傫�Ȋw��ł���B���ꂽ�����ޗ��͑���ɂ킽��ATiN��DLC�Ƃ������n�[�h�R�[�e�B���O�ޗ��ATiO2�Ȃǂ̌��w�����A�����đ��z�d�r�����̓d�q�����ޗ����B������̃Z�b�V�����ł��M�S�ȓ��_���s���A���������ł������ޗ��Ɋւ��錤���͊m���ɍ��܂��Ă���Ɗ������B�������҂͑�w�����҂��唼�ł���A��Ƃ̎Q���͔��ɏ��Ȃ��̂�����ł���B��b�����͒����ɐi��ł��邪�A���p�ʂ͂��ꂩ��Ƃ������Ƃł��낤�B�������̂悤�Ȍ����ɑ��Ă͒����̌����ҞH���A�������u�A�ޗ��Ɋւ���Z�p�̂قƂ�ǂ͓��{�A�A�����J�A���[���b�p�A���V�A����̗A���ł���A���ꂩ��̒����̉ۑ�́A�����Z�p�̎����J���ł���Ƃ����B
�@�����҂̒��S�����o�[�͕č�����{�̗��w�o���̂���30��̎��ł���A���̔\�͂Ɠ����ɁA�L��]�邮�炢�̔M�ӂ����Ɍ��˔����Ă���B���ĉ��ďo�����Œ����̐l�Ƙb������@����������A�ɂ߂ăA�O���b�V�u�ŃM���M�����Ă����B�ߔN�A���͒����ɏo������@������Ȃ������A�č��ł݂��M���M�������l�𑽂���������B���{�͏��q�E����ł₪�Đl�������ɓ]����B�Ⴆ������1%���D�G�Ȑl�ނƂ��č������������Ă����Ƃ���ƁA���{�Ƃ͌��Ⴂ�̗D�ꂽ�l�ޏW�c�����Ⴂ�̃X�s�[�h�Ŏ��������W�ɓ��������ł���Ƃ������ƂɂȂ�i������ƁA�����߂����j�B���Ȃ��Ƃ����{�̐l����10�{�ȏ������钆���ł́A���s���Ƃ������Ă����l�I���Y�ɂ���Đ����R�X�g�𑼍����������邱�Ƃ��ł���B����A���{�͗D�ꂽ��[�Z�p��~�ς��Ă��邪�A�����R�X�g�̒ጸ�Z�p�ɂ��Ă͉��ʋZ�p�Ƃ����F��������̂��A�؍����p���[�J�[�̌�o��q���Ă���B���Ă̓��{�������ł������悤�ɁA���������Ȃ������A�ނ�̖ڕW�͌����̂��̂ƂȂ�A���{�̋��ЂƂȂ邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���{�������A�W�A�̑䓪�ɂ��A���E�I��PC���[�J�[���A�W�A�̊�Ƃɔ��������悤�ɂȂ����B�������͂��߁A�؍��A��p�Ƃ��������̒ǂ��グ�ɑ��āA����A���{�͂ǂ̂悤�ɐڂ���ׂ��ł��낤���BDRAM�̎S����J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������{�͕ۗL�Z�p�̗D�ʐ����X�ɍ��߂邱�Ƃ͂������ł��邪�A�����R�X�g�̒ጸ�͋����͂̈ێ��ɕK�{�ł���B�u�ǂ������K�����������̂ł͂Ȃ��A����镨���ǂ����v�Ƃ����������낻��F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
��17����{MRS�w�p�V���|�W�E��
���@�C�m�x�[�V�������擱�ޗ������@��
2006�N12��8��(��)�`10��(��)�A���{��w���H�w���x�͑�Z�Ɂi�����s���c��)
���V���|�W�E������
�@�{�V���|�W�E���́A2006�N12��8��(��)����10��(��)��3���ԁA�����E�䒃�m���ɂ���A���{��w���H�w���E�x�͑�Z��1���قōs���܂����B�{�N�x�́A�u�C�m�x�[�V�������擱�ޗ������v���e�[�}�ɁA�������\�i���ҍu���܂ށj301���A�|�X�^�[���\�A397���A���v698���̔��\���s���A��N���l�i��N���v651���j���Ɋ��C�ɂ��ӂ��V���|�W�E���ɂȂ�܂����B17�̃Z�b�V��������Ȃ镝�L��������J�o�[���A���{MRS�̗��O�u��i�ޗ��Ɋւ���Ȋw�E�Z�p�̐��Ƃ̉��f�I�E�w�ۓI�����𗬂�ʂ��āA���̊w�p�E���p��������ю��p���̈�w�̔��W��}��v���܂��ɍČ����Ă����Ǝv���܂��B��N�Ɉ����������ۃZ�b�V������5�Z�b�V�����i�Z�b�V����A�AH�AK�AM�y��O�j�݂��܂����B����͊؍�MRS�̋��͂āA11���̍u���ҁi���A���ҍu��2���j�̕��X�ɔ��\�����Ă��������܂����B���N�������葽���̕��X�̂����͂����������A���ۃZ�b�V�������𑝂₵�Ă��������ƍl���Ă���܂��B�e�Z�b�V�����̔��\�̗l�q�A�g�s�b�N�X�Ȃǂ́A�`�F�A�̊F�l�ɂ܂Ƃ߂Ē������ȉ��̕��Q�Ƃ��ĉ������B���N���A���̗D�ꂽ�������\�E�|�X�^�[���\��ΏۂƂ�������܂�I�l���A�Ώێ�431���̒�����44����I�o���܂����B��҂��ꗗ�ɂ��Ĉȉ��Ɏ����܂��B��҂̊F�l�ɂ��j���\���グ��ƂƂ��ɁA���Q������������MRS-J����A���\�Ҋe�ʁA�Z�b�V�����`�F�A�Ȃ�тɃV���|�W�E�����E�^�c�ɂ�����ꂽ�F�l���ɁA���炽�߂Ċ��ӂ�\���グ�܂��B
��2006�N���{MRS������
Session A�F��c����i���É���j�A�g�c�����i���Ɍ�����j�A��t�c��i������)
Session B�F�����G�T�i���͒������w���j�A�ؑ��G�l�i�������ȑ�j�A����T�q�i�R�`��)
Session C�F���c�����i������j�A����F���i������j�A���c�S�M�i������j
Session D�F�{���S�i�i���k��j�A�p�c�����i�X���H����)
Session E�F���c�@�C�i��B��j�A��ؔ��H�i�������ȑ�)
Session F�F���J���j�i�}�g��j�A�O�Y�@�q�i�_�ˑ�j�A�ΐ얾�O�i��B��j�A���R�뗺�i�}�g��)
Session G�F���@�q�i������)
Session H�F��c�@���i�L����j�A�_���G���i���É���j�A�≺�L��i��B��j�A�c���m���i�@����j�A�����T�i�����)
Session I�F�����C�Ɓi�c���j�A�������V�i�k�C����)
Session J�F����T���i�}�g��j�A���@�m�M�i������)
Session K�FPiyanuch SOMMANI�i���s��j�A���c�R�F�i���s��)
Session L�FCherry L. Ringor�i���ދ@�\�j�APilwon Heo�i���É���)
Session M�F���b���i���C��j�A�~�э]���i�F�s�{��j�A���V�a��i�Q�n��j�A�n��@���i���l������)
Session N�F����[(�O�d��)�A�ؑ����V�i�V�_�˓d�@�j�A��䖃���i�c���j�A���{����i������)
Session P�F�����`���i�\�j�[)
Session Q�F�ߓ����l�i�����H�Ƒ�j�A���J����i�_�ސ�H�ȑ�j�A���J���V�i�_�ސ��j�A��c�@�B�i���{��)
��Session A�F�h���C���\���ɗR�����镨�������ƐV�@�\�ޗ��@Domain Structure-related Ferroic Properties and New Functional Materials
�@�{�Z�b�V�����ł̓h���C���\����L���鋭�U�d�̂⎥���̘̂b��𒆐S�Ƀh���C���̊ώ@��@����h���C���𗘗p�����A�v���P�[�V�����ɂ�����܂ŕ��L�����_���s��ꂽ�B���\�͏��ҍu��6���A�I�[����10���A�|�X�^�[35���̍��v51���ŁA2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�{�Z�b�V�����͍����5�N�ڂ��}���A����MRS-J�w�p�V���|�W�E���ōs���Ă���Z�b�V�����ł͍ő��ƂȂ����B�܂�����͎������������������\�������A�{�V���|�W�E���ɂ����鎥���̌����҂̎M�ɂ��Ȃꂽ�Ɗ����Ă���B
�@��N�Ɉ��������A��������ۃZ�b�V�������s�����B�����͏��ҍu���҂�TarasKolodiazhnyi���iNIMS�j���`�^���_�o���E���Ɋւ��锭�\�ł��������Ƃ���A�`�^���_�o���E���Ɋւ��錤�����\�͑S�ĉp��Z�b�V�����ōs�����B�C�m�̊w���ɂ��p��������\���s��ꂽ���A�Q���҂�����̃t�H���[�ɂ���Ċ����ȋc�_�ɐi�W���A�L�Ӌ`�ȍ��ۃZ�b�V�����ƂȂ����B�܂��؍�MRS����̎Q���҂��l�����A2���ڂɂ����]�ڂ⌇�א���A�ޗ��v�ȂǑ����̕��p��ōs�������߁A�S�Z�b�V�����̔������p��Z�b�V�����ƂȂ����B �p��Z�b�V�����Ȃ�ł͂̋�J�����邪�A�C�O����̎Q���҂�����邽�߂ɂ��A���N�x�ȍ~�����ۃZ�b�V�����𑱂��Ă��������ƍl���Ă���B
�@���\���e�ł́A��b�����������Ă��藝�w�n�i��b�j�ƍH�w�n�i���p�j�̗Z���͂��܂��͂����Ă���悤�Ɏv���B�������A��N����̉ۑ�ł�������Ƃ���̎Q���҂͏��Ȃ������B����̕����⌻�ۂɂƂ��ꂸ�A�����āu�h���C���v�݂̂��L�[���[�h�Ƃ����Z�b�V�������ł͊�Ƃ���̒��ړx�����Ȃ��̂����m��Ȃ����A��b�����A���p�������o�āA�V�����Y�Ƃݏo�����Ƃɖڂ������Ă������Ƃ��A�{�Z�b�V�����̏d�v�Ȗ����ł���B
�@����A����ܑΏۂƂȂ���28���̒�����A����ʂ���є��m�ے��w���Ƃ��Ĉ�t�c�ᎁ�i�����[���j�A�C�m�ے��w������g�c�������i���Ɍ�����H�j
��c���i����G�R�g�s�A���j��3�����I�ꂽ�B
�@�Ō�ɁA�����ǂ��͂��߁A�{�Z�b�V�����ɂ����͂������������ׂĂ̊F�l�ɂ��̏����Ċ��ӂ̈ӂ�\���܂��B
(��\�`�F�A�@�ēc���G�i���q�͋@�\))
��Session B�F���q�������̍쐻�E�]���E���p�\���x�Ȕz������A�z����́A����ы@�\������ڎw����
�\�@Fabrication, Characterization and Application of Molecular Thin Films�\Structural
Analysis and Control toward the Realization of Novel Functions �\
�@�{�Z�b�V�����ł́A��N�x�Ɉ��������A�L�@EL�f�q��L�@FET�ȂǁA���p���̏o���ɋ߂����q�����f�o�C�X�̌����҂ƕ��q�����̍\���E�����]���Ɏ��g�ފ�b��������̌����҂��𗬂�[�߁A���q�����n�̊�b�E���p�������X�ɔ��W���邱�Ƃ����҂��Ċ�悳�ꂽ�B���\�́A���ҍu��3���A��ʍu��5���A�|�X�^�[���\22���̍��v30���ŁA12��8��(��)�̌ߑO���Ƀ|�X�^�[���\�A�ߌ�ɁA�����u���i��ʍu���A���ҍu���j�Ƃ����X�P�W���[���ł������B�|�X�^�[���\�́A��N���l�A���Z�b�V�����ƍ����ł��������߁A���Z�b�V�����̔��\�҂Ƃ̓��_������AMRS-J�̓�������������A�����M�C�Ɉ�ꂽ�B
�@�ߌ�̌����u���́A�܂��A�u�C���E�ʂɂ�����P���q���\����X����p�������̏ꑪ��v�Ƒ肳�ꂽ�ё�����搶�i�F�s�{��H�j�̏��ҍu���ɂ��n�܂����B���e�́A�V���N���g��������X����p���āA�����p����X����܁iGIXD�j�A����сAX�����˗��@�iXR�j�ɂ��A�C���E�ʂ̕��q���̍\�����A3�����I�Ɂi���̖ʓ��A����ь��ݕ����Łj�ڍׂɕ]�������ŋ߂̐��ʂɂ��Ăł���A�����̒��O�̋������䂫�A�����ȋc�_���W�J���ꂽ�BLB���A�g�D���q���̍\���]���Ɋւ����ʍu����3�������A���̌�A�O���T�搶�i�Y�����E���Z�p�j�ɂ��A�u�|���t���I�����z��������̍��x�ȕΌ��G���N�g�����~�l�Z���X�v�Ƒ肳�ꂽ���ҍu�����������B���e�́A�t���\���f�q�̃o�b�N���C�g�Ƃ��Ẳ\���������q�����f�q�Ɋւ���ڍׂȍ\���]�����܂�ł���A���O�̋����������䂫�A�����ȋc�_���W�J���ꂽ�B���̌�ALB���̍\���]���A����ѕ��q���̌��@�\�Ɋւ����ʍu���������A�����u���̃v���O�����̍Ō�́A�����i�O�搶�i�V����H�j�́u�N���b�`�}���z�u�ɂ�����z�����q�̔����ɂ��\�ʃv���Y������N�v�Ƒ肳�ꂽ���ҍu���ɂ����߂�����ꂽ�B���e�́A�z�����q������̔������i�m���w����Ŕ��ɗL�p�ł��邱�Ƃ������Ă���A�����̒��O�̋������䂫�A�����ȋc�_���W�J���ꂽ�B
�@����A����܂̑ΏۂƂȂ������\��25���������B���̒��ŁA�Ŏ��i�C�m1�N�E�w��4�N���j�̌���������A���̌��ʁA�I�l�͍�����ɂ߂����A���̒��ŁA�����G�T���i���͒����A����ʁj�A�ؑ��G�l���i������@�C�m�j�A����сA����T�q���i�R�`��H4�N�j�̍��v3��������܂ɑI�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@�O�Y�N�O�i�ˈ����l��@�H))
��Session C�F���ȑg�D���ޗ��Ƃ��̋@�\VIII�@Self-assembled Materials:
Synthesis and Applications VIII
�@���ȑg�D���𗘗p�������x�ȑg�D�̂̌`���́A�]���ɂ͂Ȃ��v�V�I�Ȏ�@�ł���B�{�Z�b�V�����́A�L�@�n�A���@�n�A�����n�A����ɂ��̕����E�W�όn�ɂ�����A���ȑg�D�����ۂɊւ���V�ޗ��E�\���̂̑n���A�X�ɂ����̍\���Ƌ@�\�̉𖾓��̍L�͂Ȍ������܂ނ��̂ł���B�{�N�͏��ҍu��2���A�I�[����9���A�|�X�^�[24���̍��v35���̔��\����\������A�����ȓ��_���s��ꂽ�B
�@�ߑO�ɂ�3���̈�ʍu�����A�ߌ�ɂ�2���̏��ҍu����6���̈�ʍu�����s���A���̌�Ƀ|�X�^�[�Z�b�V�������J�Â��ꂽ�B�ߌ�̃Z�b�V�����`���̏��ҍu���ł͎Y�ƋZ�p�����������i�m�e�N�m���W�[��������̋ʒu���V�搶�ɂ��u���W�A�Z�`�����U���̂̎��ȑg�D���Əd�������v�̑�ڂŁA�����q���w�Ɋ�Â��i�m�`���[�u�\���̑n���Ɋւ���ŋ߂̃g�s�b�N�X���Љ��A���l�Ȏ��_����̊����Ȏ��^�������Ȃ��ꂽ�B3���̈�ʍu�����͂���2�ڂ̏��ҍu���́A�c���`�m��w���H�w���̍���G���搶�ɂ��u���ȑg�D���ɂ��K�w�\����L���閳�@�����̍����v�Ƒ肷��u���ŁA���������̐����@�̕��ނɊ�Â��K�w�\���̐v�Ɋւ��錤�����Љ��A�����Ȏ��^�������s��ꂽ�B
�@�ȏ�̂悤�ɖ{�Z�b�V�����ł́A�L�����ȑg�D���Ɋ֘A���ėl�X�Ȋw��Ŋ������Ă��錤���ҁA�w���Ԃ̌𗬂����i����A�{����̈�w�̓W�J�Ɛ[�����}�ꂽ�B�Ȃ�����Z�b�V����C�ɂ����ẮA�D�ꂽ���\�ɑ����鏧��܂ɁA����ʂ�����c�������i����@�H�j�A���m�w�����畽��F�����i����@�H�j�A�C�m�w�����瑁�c�S�M���i����@�H�j��3�����I�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@��v�ےB��(����@�H))
��Session D�F��炵��L���ɂ���ޗ��\���E�G�l���M�[�E��Á\�@Materials for
Living �\ Environment, Energy and Medicine �\
�@�{�Z�b�V�����ł͕�炵��L���ɂ���ޗ����̉��p�̗��ꂩ��A�����ȍu���Ɠ��_���s��ꂽ�B���\�͏��ҍu��1���A�I�[����35���A�|�X�^�[11���̍��v47���ŁA2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�������\�̉��ł͍u���̓��e���L������ł��������A�����ȓ��_���s���A�u�����Ԃ��I�[�o�[������̂��������B
�@9���́A�܂��p�����̃K���X���A�`��L����������9���̌������ʂ����\���ꂽ�B�ߌ�̃Z�b�V�����́A�܂����⌚�ꎁ�i������ЉF���O�H�Z�����g�������j�ɂ�鏵�ҍu���u�N�����J�[����уZ�����g�̏������ɑ���N�����J�[���̏��ʐ����̉e���v���s���A���̌�ŋ߂̃Z�����g�y�уR���N���[�g������5���̐��ʂ�����A�����Ō������̃C�I�������Ɠd�r�̃������[���ʗ}���̐��ʂ����ꂽ�B16�F00�����5���̃|�X�^�[�Z�b�V�������Ȃ��ꂽ�B
�@10���́A9������6���̃|�X�^�[�Z�b�V�������s��ꂽ�B�������\��10��30������A�K�[�l�b�g���̌����\����́A�A�C�\���[�^�[�̐v�A�������C�L�^�̐V�����ɂ��Ă̐��l��͓��̐��ʂ����ꂽ�B�ߌ�͐^��ޗ��̌������@�A�L�@���̋���3������`���w���ʁA�[�I���C�g�A�Y�f�����̕��q�ӂ邢�̐��ʂ����ꂽ�B�Ō�̃Z�b�V�����ł͔g���I�A�G�}�p�����R�́A�_���S�̌��G�}���������ꂽ�B
�@2���Ԃɂ킽����A�G�l���M�[�A��ÂɊւ���L������ł̌������\�ł��������A��N�Ɗr�׃I�[�����Z�b�V�����ł�13�������\�������������A�x�e���Ԃ��\���m�ۂł��Ȃ��ł��������A���̍����u�����тɊ����Ȏ��^�������s��ꂽ�B
�@����A����ܑΏۂƂȂ���26���̒�����A�{���S�i���i���k���i��H�j�A�p�c�������i�X���H�����A�O�O�嗝�H�j��2�����I�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@��������i�R����H))
��Session E�F�ő̂̔������\�i�m�̈�ł̔�������ɂ��V�ޗ��̑n���Ƃ�����x����T�C�G���X�\
�@Solid
State Reaction�\Basic Science and Chemistry for Advanced Materials by Reaction
Control in Nanosize Region�\
�@�{�Z�b�V�����́A���ē��{���w��̘A�����_��̘g����13�N�ԍs���Ă����u�ő̂̔��������_��v�̃|���V�[���p�����A�V�K�ޗ��J���̊�b�ƂȂ�ő̂ƌő́A�ő̂Ɖt�̂��邢�͌ő̂ƋC�̂Ƃ̔�������A�ő̂ƌ��E�d���g���邢�͌ő̂Ɠd�q�ȂǂƂ̑��ݍ�p�ɂ��V�K�@�\���̔�����������ɓ��ꂽ�������_�̏�Ƃ��ĊJ�݂��ꂽ�B�ޗ��v���Z�X�Ɋւ����b���ۂ̉𖾂Ɋւ��錤�����܂߁A�u�ő̂̊֗^�������ۂ�m�����L�����삩������ł����v�����b�g�[�ɁA�������\14���A�|�X�^�[���\15���̍��v29�����x�[�X�ɂ��āA�����ȓ��_���s��ꂽ�B
�@���\���e�́A�Z�b�V�����̃|���V�[�f���A�i�m�\���P�ʎ��Ȕz��̃V�~�����[�V��������K�X�N���~�b�N�ޗ��̓����܂ŁA����߂đ���ɂ킽�����B�������A���̓��e�ɂ́A�i�m�\���̂̐������牞�p�܂ł̗���Ɋւ����ѐ�������A����̍ޗ��v�ɂƂ��čŏd�v�ۑ�̂ЂƂł���u�ٕ��삩��w�ԁv�Ƃ����p���Ɋւ��āA�����̎Q���҂ɂƂ��ē���Ƃ��낪�����������̂Ǝv����B
�@�|�X�^�[�̉��́A�ʘH���s�������l�̔g���A�������̃C�I���̊g�U��f�i�Ƃ�����قǂɖ��ł���A���_������߂Ċ����ł������B�������\�̉��́A�Q���҂ɔ�ׂĂ��L�������������������A�����ȓ��_�ƃX�P�W���[���ǂ���̉^�c���o�����X�悭�������Ă����B
�@����A����ܑΏۂƂȂ���14���̒�����A����ʂƂ��Ċ��c�C���i��B��j�A�w�������ؔ��H���i�������ȑ��b���H�j��2�����I�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@�喼�@�ہi�c��嗝�H))
��Session F�F�i�m�X�P�[���\���̂̐V�W�J�\�\���E�@�\�E���p�\�@
Recent Progress
in Nano-structured Materials�\Structure, Function and Applications�\
�@�{�Z�b�V�����ł́A�L�@�A���@�A����т����̃n�C�u���b�h����Ȃ�i�m�\���̂̍쐻��L�����N�^���[�[�V�����ƁA���̍\���Ɉˑ����������̉𖾂⓾��ꂽ�ޗ��̉��p�Ɋւ��Ċ����ȓ��_���s��ꂽ�B���\�͏��ҍu��2���A�������\20���A�|�X�^�[���\30���̍��v52���ł���A12��9���`10����2���Ԃōs��ꂽ�B�������\�̉��ł͎��⎞�Ԃ�����Ȃ��Ȃ�قǁA���Ɏ��̂��铢�_���Ȃ��ꂽ�B
�@���e�Ƃ��ẮA�����E�_�����E�����q�Ȃǂ̐V�K�ޗ��̑n���ƕ����I�E���w�I�����Ɋւ����b�I�Ȍ����ɉ����āA�����ޗ��̍\�����i�m���[�g�����x���Ő��䂵�A�����ޗ��A�����ޗ��A�G�}�E���G�}�ޗ��A���z�d�r�Ȃǂɉ��p���錤���ɂ��Ă�������������A�L�@�\���@�����i�m�ޗ��̏d�v��������܂��܂������Ă���悤�Ɏv��ꂽ�B���ҍu���ł́A�����ɍ���֎u�������i����@�H�j�ɂ��uABC���^�u���b�N���d���̂̎��ȑg�D���𗘗p���������t�H���W�[����v�Ɋւ���ŐV�̌������ʂ�����AABC���^�u���b�N���d���|���}�[�ɓ��L�̃����t�H���W�[�Ƃ��̐���ɂ��ĕ�����₷���Љ�Ē������B���ɂ́A�|���}�[����Ƃ��錤���҂͏��Ȃ��悤�ł��������A���Ɋ����ȓ��_���W�J����A����A���̕��삪�}���ɓW�J�����Ǝ��������B������2���ڂɂ́A���ԓO�������i���吶���j�ɂ��u����-�����̃i�m�����ޗ��̃v���Y�������Ɋ�Â����d�C���w�@�\�v�Ɋւ��鏵�ҍu�����s��ꂽ�B�_���`�^���Ƌ����i�m���q���n�C�u���b�h���������ޗ��̌��d�C���w�����Ɋւ��ďЉ�Ē������B���݁A���ɒ��ڂ���Ă�������i�m���q�̕\�ʃv���Y�������𗘗p������G�l���M�[�ϊ��f�o�C�X�A���L�^�ޗ��Ȃǂ̑n���Ɋւ��āA�ŐV�̌�����������Ɏ��悤�ɗ����ł����B�{�Z�b�V�����ł́A�����A�|�X�^�[�Ɋւ�炸�A�V�K�ȃi�m�X�P�[���\���̂̑n���ƍ\�����ٓI�Ȑ����ɂ��ċɂ߂Ďh���I�Ȍ������ʂ���������Ă���A����Ƃ��i�m�X�P�[���ޗ��Ƃ��̐����ɏœ_�Ă��Z�b�V�����Ƃ��Čp�����Ă�����Ǝv���B
�@����́A13���̌������\�A29���̃|�X�^�[���\�̌v42��������ܑΏۂƂ��A12���̐R���ψ��ɂ�茵���ȐR�����s�����B���̌��ʁA���J���j���i�}�g��j�A�O�Y�q���i�_�ˑ�@���R�Ȋw�j�A�ΐ얾�O���i���@�������H�j�A���R�뗺���i�}�g��@���������Ȋw�j��4��������܂ɑI�肵���B
(��\�`�F�A�@���{�@�i�i�������w�@�H�w������))
��Session G�F�ʎq�r�[���ɂ�閄���ꂽ�E�ʂ̉�́\�����́E�d�q�ޗ�����\�t�g�}�e���A���܂Ł\�@
Structural Analysis of Buried Interfaces Using Quantum Beam
Technologies�\Wide Applications ranging from Semiconductors to Soft Materials�\
�@�i�m�T�C�G���X�A�i�m�e�N�m���W�[�̌����ł́A�\�ʂɘI�o���Ă�����̂���ł͂Ȃ��A���������̕����ɂ���ĕ���ꂽ�u�����ꂽ�v�i�m�\���������K�v������B�܂��l�H�I�Ɍ`�����ꂽ�ϑw�\���̊e�w��e�E�ʂ́A��ɏ�w�Ɂu�����ꂽ�v��Ԃɂ���B�ŋ߁A���������u�����ꂽ�v�E�ʂ�j���Ɍ������邽�߂ɁAX���A�����q���̗ʎq�r�[���ɂ�锽�˗��@���̉�͋Z�p�����x�����悤�Ƃ���@�^�����܂��Ă���B�{�Z�b�V�����́A�����́A�\�t�g�}�e���A���A�o�C�I�V�X�e�����ɂ��āA�����̎�ʂ�ޗ��Ƃ��Ẳ��p�̈Ⴂ���A�u�����ꂽ�v�E�ʂ̐���A�@�\�A�������Ɋւ��Ő�[�̃T�C�G���e�B�t�B�b�N�E
�g�s�b�N�X���𗬂��A��͋Z�p�̏������_���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�Â��ꂽ�B
�@�v���O�����͏��ҍu���i�����u���j18���A�|�X�^�[16���̍��v34������\������A2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�����u���́A�S�u�������ҍu���ł���A����ɂ킽�镨���E�ޗ��̕�����L�����グ�A���r���[�I�ȓ��e�̍u�������肢�����B������̍u���������ւ�L�Ӌ`�ł��������A���ʓI�Ɏ��^���݂�20���̎������Ԃł͑����s���C���ł������낤���A�c���i�s�������삯���ɂȂ��Ă��܂�����������B���̋@��ɂ́A���_��[�߂₷�����邽�߁A�e�[�}�ɂ��������A�N�Z���g�����铙�̍H�v���l���������B�|�X�^�[���\�ł́A���̃Z�b�V�����Ƃ����ʂ̉��ŁA���苷�ŕ����ĉ��̂�����Ȃقǂ̑卬�G�̂Ȃ��A�����Ԃɂ킽���ϔM�S�Ŋ����ȋc�_���s��ꂽ�B���{MRS�ł̔��\�͏��߂Ă̎Q���҂���������A�u����قǂ̊����ł���A�|�X�^�[���\������1�\������ł����悩�����v�Ƃ��������z�������ꂽ�B
�@X���E�����q���˗��@����т��̊֘A�Z�p�́A�]������\�ʂ┖���E���w���̊E�ʂ̉�͂ɗL�p�ȃc�[���Ƃ��čL���p�����Ă��Ă���B�{�Z�b�V�����ł̓��_�ł́A�K���������̒P���ȉ�������ɂ͂Ȃ��A����Ӗ��ł͂���܂ł̏펯�̘g�O�ɂ���悤�ȁA�v�������g���A���x���ɂނ��Ă̊��Ҋ����������ꂽ�BQuick�v���i���X�ω����閄���ꂽ�E�ʂ̌����j�A�����̈敪�́i�ꏊ�I�ɋψ�ł͂Ȃ��E�ʂ̌����j�A���邢�́A���̎�ނƗʂ𑝂₷���Ƃ��Ӑ}�����ق��̑���Z�p�i��܁A���p�U�����j�Ƃ̗Z���AX���ƒ����q�̑��◘�p���́A���ɏd�v�ƍl�����A�����̔��\�҂��ٌ������ɁA���̈Ӌ`���w�E�����B���I�Ȍ����̎��݂��n�܂��Ă���A����A��w�̍��x���ƂƂ��ɁA�����̋����[�������E�ޗ��ւ̉��p�̍L���肪���҂����B
�@����܂ɂ��ẮA������ƂȂ���9���̒�����A���q���i����V�̈�j�́u���g��܌��ۂ𗘗p����SiO2/Si�E�ʉ��̂Ђ��݂̌����v���I�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@���䌒���i�����ޗ������@�\))
��Session H�F��[�v���Y�}�Z�p���i�m�}�e���A���Y�t�����e�B�A�@Frontier
of Nano-materials based on Advanced Plasma Technologies
�@�{�Z�b�V�����ł͐�[�v���Y�}�Z�p��p�����i�m�}�e���A���Y�̍쐻�ƍ\���E�@�\�]���Ȃ�тɂ��̉��p�ɂ��Ă̊����ȓ��_���s��ꂽ�B���\�͍��ۃZ�b�V�����Ƃ��āA�v���i���[�u��1���A���ҍu��4���A�I�[����6���̍��v11���A�����Z�b�V�����Ƃ��ăv���i���[�u��2���A���ҍu��5���A�I�[����17���A�|�X�^�[40���̍��v64���ŁA3���Ԃɂ킽��s���A�C�O����؍��A�����A�u���W���A�f���}�[�N����̍u���҂��Q�������B�������\�ł́A�����ȓ��_���Ȃ��ꂽ���ߋx�e���Ԃ��啝�ɒZ�k���ꂽ�B
�@�����̍��ۃZ�b�V�����ł́A�܂��؍�Sugnkyunkwan���J.G.Han�����i�m�\�����w����p�����V�����g���C�{���W�[�R�[�e�B���O�ɂ��ăv���i���[�u�����s���A�����ĐF����Si�i�m�����A�K�X���q����Si�N���X�^�[�ABN�~�N���R�[�����̐V�K�i�m�����̑n���A�}�C�N���v���Y�}��p�����\�ʉ������̍ŐV�̋ɂ߂ċ����[���������ʂ����ꂽ�B�{���ۃZ�b�V�����ł̍u���́A�`�����鍑�ۉ�c�ɂ��������Ƃ�Ȃ��ɂ߂č������ł��������Ƃ��������Ă��������B
�@2���ڂ̍����Z�b�V�����ł́A�F�{��̏H�R�G�T�����p���X�p���[�̃v���Y�}���p�A�o�C�I���p�ւ̓W�J�ɂ��ăv���i���[�u�����s���A������Si�֘A�v���Z�X�Ɋւ��錤�����ʂ����ꂽ�B�ߌ�̌㔼�ɂ̓|�X�^�[�Z�b�V�������s��ꂽ�B
�@3���ځA�ߑO�O���E�㔼���킹��38���̃|�X�^�[�u���ɑ����āA�ߌォ�瓌����w�̓c���m�����i�m�e�N�m���W�[�ɂ�����g�b�v�_�E���ƃ{�g���A�b�v�̗Z���ɂ��ăv���i���[�u�����s���A�����Ċe��i�m�}�e���A���̑n���Ƃ��̉��p�Ɋւ���u�����s���A�S�̂Ƃ��Ď��̍����f�B�X�J�b�V�������s��ꂽ�B
(��\�`�F�A�@���J�����i���V�X�e�����))
��Session I�F�i�m�����\������Ƌ@�\�����@The Development of Functional
Materials by Control of the Fine Nano-structures
�@�Z�b�V����I�ł́A12��9���i�y�j�ɏ��ҍu��5���A�|�X�^�[���\8�����A�܂�12��10���i���j�Ƀ|�X�^�[���\15�����s�����B���ҍu���́u�i�m�\������ɂ�鐸���@�\�̔����v���e�[�}�Ƃ��āA�L�@�ޗ��A�L�@�d�q�ޗ��A�����q�A�o�C�I�i�m�ޗ��ɂ��Ă��u�������������B
�@�܂��AERATO�E�����F�T�搶����A���ȑg�D���𗘗p�����L�@�ޗ��ɂ��Ă��u�������������B�����搶�̂������ł́A�w�L�T�x���]�R���l���Ƃ����R�A�ޗ����A�n�t���ŗ��e�}�����A���ȑg�D�������邱�Ƃɂ��A�i�m�t�@�C�o�[�̌`�����邱�Ƃ����o���A�����p�����L�@���d�́AFET�ޗ��A�����d�̂����������B�܂��A�����������ȑg�D���ޗ��̐v�w�j�ɂ��Ă��ڍׂɂ��b���������B
�@���ɁANIMS�E�s�����_�搶����A�\���F��p�����ޗ��n���ɂ��Ă��u�������������B�s�����搶�̂������ł́A�����q�����q�ƃG���X�g�}�[��g�ݍ��킹���ޗ��̑n���ɂ���āA��X�̎h���ɂ���ĐF�����ω�����ޗ��ɂ��Ă��u���������B
�@�܂��A���H��E���쏟�搶����A�����q�𗘗p�����@�\���i�m�ޗ��̑n���ɂ��Ă��b�������B����搶�̂��b�ł́A�����q�̔��\���`���\��A�����q�ƃi�m�����q�Ƃ̃n�C�u���b�h�`���ɂ���āA�����I�ɐ��䂳�ꂽ�i�m�ޗ��̑n�����@�ɂ��Ă��u���������B
�@���ɁA���s��w�E�ؑ��r��搶���A�y�v�`�h��p�����L�@�d�q�ޗ��v�ɂ��Ă̂��b�����B�ؑ��搶�̂��b�ł́A�y�v�`�h�i���Ƀ�-�փ��b�N�X�y�v�`�h�j�̎��A�傫�ȃ_�C�|�[�����[�����g�ɒ��ڂ����d�E�쓮�^�̓d�q�ޗ��ɂ��Ă��u�������������B
�@���ɁA���H��E���c�搶���A���������q��p�����o�C�I�i�m�e�N�m���W�[�ɂ��Ă��b�����������B���c�搶�̂��b�ł́A���������q���g�����ꍇ�̐����w�ҁA��w�҂Ƃ��Ă̗��ꂩ��A�D�ꂽ�@�\�ɂ��ďœ_�ĂĘb��i�߂Ă����������B���������q�̊J���ɂ�����ޗ��Ȋw�̊ϓ_�ɂ��Ă��킩��₷�����b���������B
�@����A����ܑΏۂƂȂ���23���̒�����A����ʂƂ��ď����C�Ǝ��i�c��嗝�H�j�A�w�����獲�����V�N�i�k�C����j��2�����|�X�^�[�܂ɑI�ꂽ�B
(��\�`�F�A�@�O�Y���q�i�k����[�Ȋw�Z�p��w�@��))
��Session J�F�擱�I�o�C�I�C���^�[�t�F�C�X�̊m���@Frontier of Biointerface
�@�{�Z�b�V�����ł́A�o�C�I�C���^�[�t�F�C�X���i�m�E�}�C�N�����x���ŗ������A����𐧌䂵�A�V���ȋ@�\����������ޗ��T���Ɋւ�铢�_���s��ꂽ�B���\�͏��ҍu��4���A�I�[����14���A�|�X�^�[24���̍��v42���ŁA�^�C�g�ȃX�P�W���[���ł��������A12��9����1���ōs��ꂽ�B�������\�ł́A�ǂ̍u�������M�����c�_���Ȃ���A15���Ƃ�����ʍu���̎��ԓ��ł͎��܂肫�炸�A�ŏI�I��40���قǂ̒x�ꂪ�����A�|�X�^�[�Z�b�V�����̎��ԂƏd�����Ă��܂����B�|�X�^�[�Z�b�V�����ł��I�[�����Z�b�V�����Ɠ��l�M�S�ȋc�_�����ꂽ�B�������A�\���Ȏ��Ԃ��Ƃ�Ȃ��������Ƃ����Ɏc�O�ł������B
�@�ߑO�ɂ́A5���̈�ʍu����2���̏��ҍu���A���É���w�̍��䎡�搶�ɂ��u�v���Y�}�i�m�e�N�m���W�[��p�����o�C�I�C���^�[�t�F�[�X�̊J���v�ƁA���s��w�̏����G�r�搶�ɂ��u�Đ���ÂɌ������o�C�I/�i�m�n�C�u���b�h�v���b�g�z�[���Z�p�̍\�z�v���������B����搶�̃v���Y�}CVD�@�ɂ�钴�������\�ʂ́A�V�����o�C�I�C���^�[�t�F�C�X�̉\����������ϋ����[�����̂ł������B�����搶�́A�Đ���ÂɌ������v���b�g�z�[�����ANEMS/MEMS�Z�p��p���č\�z����W�]�ɂ��ču�����ꂽ�B���ł������E�����}�C�N���`�b�v�́A�g�D�H�w�ɂ����ėL���ȉ�̓c�[���ł��邱�Ƃ����������B�ߌ�̃I�[�����Z�b�V�����ł́A9���̈�ʍu���A2���̏��ҍu�����������B��B��w�̍����~�搶�̏��ҍu���u�\�ʊJ�n�d����p�����\�t�g�C���^�[�t�F�[�X�̐����v�v�ł́A�������d���@��p���������x�|���}�[�u���V�\�ʂ��ᖀ�C�������������ƁA�܂��A����Ȃ�i�m���x���ł̊E�ʐ���Z�p�̕K�v�����������ꂽ�̂���ۓI�ł������B�Ō�̏��ҍu���́A���É��H�Ƒ�w�̑��c�G���搶�́u�@�\���������̂ŏC�����ꂽ���d�ɂ̍쐬�v�ŁA�������̔�����͂ɁA�i�m���x���ō\�����䂵���C���d�ɂ̗L�p���������ꂽ�B
�@�{�Z�b�V������ʂ��āA�o�C�I�C���^�[�t�F�C�X�̍ޗ��T�������̕���Z���I�ȍL������������B���N�x�̃v���O�����ł́A���ԓI�ɗ]�T�����������X�P�W���[���Ƃ��A���[���c�_���y���߂�Z�b�V�����Ƃ������B�Ȃ��A����܂́A�Ώێ�22���̒�����A����T�����i�}�g��@�j�A���m�M���i����@�H�j��2���̊w�����I�o���ꂽ�B
(��\�`�F�A�@����܂ǂ��i������))
��Session K�F�C�I���r�[���𗘗p�����v�V�I�ޗ��@Innovative Material
Technologies Utilizing Ion Beam
�@���ۃZ�b�V����K�́A���ҍu��10���i�C�O���6���j�ƈ�ʔ��\37���i�������\12���A�|�X�^�[���\25���j�̍��v47����2���Ԃɂ킽��J�Â��ꂽ�B
�@�{�Z�b�V�����̔��\���e�́A�C�I���r�[���̗��p�͔����݂̂̂Ȃ炸�A�V���ȍޗ��J���ɂ͂܂��܂��傫�Ȑi�W�Ǝ�������҂������B���ɁA���̊֘A����уi�m�e�N�m���W�[�Ɋւ�����̂������A�C�I���r�[���ɂ��ޗ��n�������̕������������Ă����B
�@�i�m���q�`���Ƃ��̗��p�ɂ��ẮA�i�m���q�̌`������i�傫���A�[���A���ʈʒu�A�����Č��f�j���ł���V���Ȏ�@�����\����A�܂��A���p����������̂̒P�d�q�������[�w������A����`�f�q�A�����f�q�A�X�ɂ͍����x�Z���T�[�̊J���ƌq���邱�Ƃ����ꂽ�B�V���ȕ����Ƃ��ẮA�C�I���g���b�N�̕����ɒ��������������q�A�i�m���q�����̖ʓ����z�̌`���A�i�m���q��1�����z��A�C�I���H�w�v���Z�X��p�����V���Ȍ��w�f�q�`����@�������ꂽ�B�i�m���H�̍Ő�[�Z�p�Ƃ��āAFIB��C�I���r�[�����e���\�O���t�B�[�����A���\nm�ȉ��̉��H���x�ɓ���A�C�I���r�[���Z�p���A�Ăыr���𗁂тĂ����B�i�m���q�̏W������ɂ��Ă��A���ȑg�D���Z�p�Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ���āA�i�m���x���ɐi�W���Ă�������������ꂽ�B
�@�܂��A��w�A�����A�_�w�Ȃǂ̋��E�̈�ւ̔��W���傫�����҂��ꂽ�B���ɁA�A���זE��y��ւ̒�G�l���M�[�ł̃C�I���������������ꂽ�B���\keV�Ƃ�����G�l���M�[�ōזE���̉��H��DNA�ւ̏Ռ��ɂ��ADNA�����╔���I�����ɂ��ˑR�ψق����҂���A�L�\�ȕi��̊J���⍂�@�\�ō������ȃA���R�[�����y�̍y��Ȃǂ��J�����邱�Ƃ��ł��A�����̃G�l���M�[���̉�����Ɍq����ȂǑ傫�ȉ\�����߂Ă���B����ɁA�C�I���r�[���ɂ�鍂���q�ޗ��̉����́A�זE�ڒ������p�^�[�j���O�����łȂ��A���זE�̖ړI�זE��ւ̕����U���iMSC����_�o�זE�ցj�̉\�����������Ƌ��ɁA�זE�`�b�v�쐻�̓���Ƃ��ăC�I���r�[�������p�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B
�@���ۏ��ҍu�����ɂ�鐢�E�Ő�[�̌������\�ƂƂ��Ɋw���̔��\�������A�܂��A�|�X�^�[�Z�b�V�����������̗����҂��K��A���C���锭�\�Ɠ��_���s��ꂽ�B
(��\�`�F�A�@�ݖ{�����i�����ޗ������@�\))
��Session L�F�R���d�r�p�ޗ��̐V�W�J�@New Trend for a Development of
Fuel Cell Materials
�@�{�Z�b�V�����ł́A�R���d�r���\������ޗ�����ѐ��f�̐����A�����Ɋւ��ޗ��̍őO���ɂ��āA�����̎�茤���ҁE�w���𒆐S�ɏW�ߋc�_���s���A����̔��W�̉\����T�鎋�_���犈���ȓ��_���s��ꂽ�B���\�͏��ҍu��2���A�I�[����17���A�|�X�^�[12���̍��v29���ŁA12��10���Ɋ�1�������čs��ꂽ�B�������\�̉��ł́A��ʍu���̒���6�����p��ɂ��s���A���^�����ł��p��ɂ�銈���ȓ��_���s��ꂽ�Ǝv���B
�@���\�̒��Ŗڂ��������e�Ƃ��ẮA���l����̐Ό����������A�R���d�r�ޗ��ɂ����čł����ڂ���Ă�����n�d�ɂ̑n���Ɋւ��A�u�����q�`�R���d�r�p�V�K�J�\�[�h�ޗ��Ƃ��Ẵ^���^���n�������v�Ɋւ��锭�\���s���A���̔��\�̒��ŁA���n�d�ɍޗ��̉\���ɂ��Ă̎w�E���s�����B�����āA���É���w��Pilwon
Heo���ɂ��u��������R���d�r�p�v���g���`����Sn0.9In0.1P2O7�ő̓d�����v�̔��\�ł́A�]���̍����q�`�ő̓d�������g�p�s�\��200���t�߂ɂ����鍂���\�v���g���`���̂̊J���Ɋւ��锭�\���s���A�o�Ȏ҂̊Ԃł������S���W�߂Ă����B���̑��A����̗L�]�ȐV�K�Y�f�ޗ��Ƃ��Ẵt���[�����i�m�`���[�u�̍����Ɋւ��āACherry
L. Ringor�����s�������\�́A���̔��\�̓��e�͌����ɋy���A���\�ɂ�����H�v��A���̕�����₷���p��ɂ��������\���A�o�Ȃ����w�����茤���҂������ύD�]�ł���A�����̊w���̌��{�ƂȂ锭�\���Ȃ��ꂽ�Ɗ������B
�@�܂��A���f�֘A�ޗ��̔��\�ɂ����Ă��A�R�������ޗ��A���f�����A���f�����y�уZ�p���[�^�[�ޗ��Ɋւ��āA�Ő�[�̘b�肪����A�R���d�r�ޗ������Ɋւ��A���ɕ��L���w�̌����ҊԂł̗L�p�Ȉӌ��������Ȃ��ꂽ���̂Ɗm�M����B
�@������R���d�r�ޗ��ɊW����A�Ȃ�ׂ����L������̌����҂��ꓯ�ɏW�܂�A�c�_��e����[�߂���ł���悤�A�w�͂��邱�Ƃ�\�����킹�ĕ���B
�@���Ȃ݂ɁA����̏���ܑΏۂƂȂ���20���̒�����A�w������Pilwon Heo���i���É�����w�����ȁj�A����ʂ���Cherry
L. Ringor���i���ދ@�\�j��2��������܂ɑI�ꂽ�B���̎�܂��ꂽ�������͂��߁A����Q��������������茤���ҁE�w���̍���̔��W��S���F�O����ƂƂ��ɁA�{�Z�b�V�������A�R���d�r�ޗ�����̔��W�̈ꏕ�ɂȂ邱�Ƃ��肤���̂ł���B
(��\�`�F�A�@�����@�r�i�����ޗ������@�\))
��Session M�F�l�b�g���[�N�Ɨn�}���D��Ȃ��Q���̃T�C�G���X�ƃe�N�m���W�[�@
The
Science and Technology of Gels�f Characteristics Woven by Network and Solvent
�@�{�Z�b�V�����ł́A�H�i�E���p�i������֘A����ɂ킽��l�X�̗̈�ŗ��p����Ă��鍂���q�Q�����̃\�t�g�}�e���A���ɂ�����\���A�@�\�A�����ɂ��Ċ����ȓ��_���s��ꂽ�B���\�́A���{��Z�b�V�����i���ҍu��2���A��ʍu��10���j�A���ۃZ�b�V�����i���ҍu��2���A��ʍu��4���j�A�|�X�^�[�Z�b�V����28���̍��v46���ŁA2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B���ɍ��߂Ă̎��݂ƂȂ������ۃZ�b�V�����ł͐S�n�悢�ْ��������ɕY���A���ꂩ�獑�ۉ����Ă����V���|�W�E���̎p�����ڂ낰�Ɍ����銴���ł������B
�@�����ߑO�ɂ́A�܂����ҍu���Ƃ��ČQ�n��H�̌E�c���ɂ��u�t�B�u�����Q���`���Ɠ��Ƃ̑��ݍ�p�v�A�����Ď�Ƃ��Đ��́A���̊֘A�������̃Q���A�Q���l�����A���̌�A���������q�n�Q���Ɋւ��鐸�͓I�Ȍ����̐��ʂ����\���ꂽ�B���ł��A�u�Q�����e���v���[�g�ɗp�����i�m�|�[���X�V���J�̍쐻�i���l��������E�n�ꋜ���j�Ƃ������j�[�N�Ȕ��\���s���A���̕���̐V�������W�̈�[���_�Ԍ���ꂽ�B
�@���̌�s��ꂽ�ߌ�O���̍��ۃZ�b�V�����ł́A�����Ȋw�@�ߒ��H���������������̔n���P���iProf.
Ma Guanghui, National Key Laboratory of Bio-chemical Engineering�j�̏��ҍu���uPreparation
and Application of Uniform-sized Microgel by a Special Membrane Emulsification
Technique�v���͂��߂Ƃ���Q���r�[�Y�A�i�m�J�v�Z���̍쐻�@������Ɋւ���u���A�G�A���Q���쐻�@�Ɋւ���u���������茤������̍L���肪�������ꂽ�B���ł��A���C�嗝�̐��b�����ɂ��uDielectric
Behavior of Water in Calcium Silicate Hydrate�iCSH�jGel for Portland Cement�v�ɂ͑����̊S����ꂽ�B���ۃZ�b�V�����̍Ō�̍u���́A���傤�ǂ��̎����ɗ�������Ă���S.K.
Kundu���ɂ�鏵�ҍu���uDielectric and Dynamic Light Scattering Study of
Liposome and Liquid Crystals in Dilute Solutions�v���s���A�_�C�i�~�N�X�̗��ꂩ��̍\���`���\�t�g�}�e���A���ɂ��Ă̐�i�I�Ȓm������I���ꂽ�B
�@���̓��̌ߌ�̌㔼�A�y�сA2���ڂ̌ߑO�Ƀ|�X�^�[�Z�b�V�������s���A�Ђ��߂��������O�̒��ő����̔M�S�ȋc�_���Ȃ���Ă����B2���ڂ̌ߌ�́A����@�H�̉Y�R�������̏��ҍu���u�t���Q���̎h�����������v����Ɏ�ɍ��������q�Q���𒆐S�Ƃ����u�����s���A�Ō�܂ő����̒��O����̊����ȋc�_���W�J���ꂽ�B
(��\�`�F�A�@���@��L�i���@�H))
��Session N�F�����n�����̍ŋ߂̐i���@Advances in the Application of
Biological Resources
�@�{�Z�b�V�����́A��N������K�͂Ő������ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɁA�F�l�̂����͂Ƃ��s�͂̎��ƁA�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B�{�N�����Z�b�V�����ł́u���������̗L�����p�A���T�C�N���A�V�f�ނ̊J����]���Z�p�A�i�m�I�[�_�[�ł̍��@�\���p�@�v�𒆐S�ɍŋ߂̐i���ɂ��ē��_���Ă܂���܂��B�{�N����낵�����肢���܂��B
�@���ҍu�������ꂽ�O�ؐ搶�i���Ɍ���@�H���j�́u�Y�f��p�����d�g�z���̂̊J���v�́A�E�b�h�Z���~�b�N�X�ASiC�A�ؒY��J�[�{���u���b�N�Ȃǂ��x�[�X�Ƃ���1�`10GHz�͈͂̔g�ɓK���ȋz�����u�̊J���ɂ��Ă̍u���ł����B�ɓ��搶�i�ߋE��@�������H�j�́u�A���d�ʂ̓d�C�G�l���M�[�����p�ւ̉\���v�ł́A�A����p�����A�܂������V�������ɂ₳�����d�̓G�l���M�[���ɂ��Ă̌������ʂ����\����܂����B���u���Ƃ��A���^�����������ŁA���̍����f�B�X�J�b�V�������s���܂����B
�@�I�[�����Z�b�V�����́A�ߑO11���A�ߌ�O��10���A�㔼5����3���ɕ�����āA��9������6�������܂ōs���܂����B���k�𗘗p�����V�ޗ��A�؍ށE�A������̐������o�@�A���O�m�t�F�m�[���Ȃǒ��o�����̗��p�@�A�؍ނ̋@�B�I�����A�V�@�\���ޗ��E�b�h�Z���~�b�N�X�̉��p�ȂǑ���ɂ킽���č��x�Ȍ������\���s���܂����B���P�ʂ̃X�P�W���[���ŁA�����Ԓ��߂����X����܂������A�\���Ȕ��\�Ɠ��c���o�������̂Ǝv���܂��B
�@�|�X�^�[�Z�b�V�����̔��\������42���ŁA��N��2�{�߂��̔��\������A16������17���܂ŊJ�Â���܂����B���k�A�a�i���j���ȂǐA���n�������ޗ��Ƃ����V�f�ނ̊J���A�q�o����O�m�t�F�m�[���Ȃǂ̐������o�Ƃ��̉��p�A�ؒY��E�b�h�Z���~�b�N�X�Ɋւ����b��������т��̉��p���A��������҂ł��镪��̔��\�������A������Ƃ���ŁA����ⓢ�_�������ɍs���Ă��܂����B���\�����������ɂ�������炸�A���\���Ԃ͍�N���Z���������߁A�Q���҂̊F�l�ɂ͔��ɕ�����Ȃ��������ƂƎv���܂��B�܂��A���\�҂̕��́A�܂������x�ގ��Ԃ����������Ǝv���܂��B����J�l�ł����B
�@����́A����ܑΏۂƂȂ���30���̒�����A����[���i�O�d��@�E��������JST�@SORST�j�A�ؑ����V���i�V�_�˓d�@�j�A��䖃�����i�c��嗝�H�j�A���{���玁�i�����嗝�H�j��4�����I��܂����B
(��\�`�F�A�@�����q�O�i�X���H�Ƒ��������Z���^�[))
��Session O�F�ޗ��f�[�^�x�[�X�@Materials Database and Application System for
Materials Design
�@�{�Z�b�V�����ł͍ޗ��f�[�^�x�[�X�̍\�z����Ƃ��̉��p�V�X�e������эޗ��]���Ɋւ��铢�_���s��ꂽ�B�ޗ��f�[�^�x�[�X�Ɋւ���Z�b�V�����͏��߂Ăł��������A�؍�����4���̐\�����݂����荑�ۃZ�b�V�����Ƃ��ĊJ�Â����B���\�͊�u��1���A���ҍu��1���A�I�[����5���A�|�X�^�[10���̍��v17���ŁA2���ڂ̌ߌ�ɍs��ꂽ�B
�@�������\�͂܂��A��u����NIMS�R�萭�`����NIMS�����E�ޗ��f�[�^�x�[�X����э����O�̃C���^�[�l�b�g�Ō��J����Ă���ޗ��f�[�^�x�[�X���Љ���B�����ď��ҍu���Ƃ��Ċ؍���Bo-Young
Hur������Rheological Characteristics of Molten Metal for Casting Design�ɂ��ču�������B���m��w�̈���r�G�����͍ޗ��f�[�^�x�[�X�̋��ʃv���b�g�z�[���J���v���W�F�N�g�̏Љ�ƍޗ��f�[�^�x�[�X�\�z�ƃf�[�^�̋L�q�ɂ�������_���w�E�����B�������\����у|�X�^�[���\�Ŋg�U�A�����q�A���`���A�\���ޗ�����ъ����׃f�[�^�x�[�X�Ȃǂ̍\�z���Ⴊ�Љ�ꊈ���Ȏ��^���s��ꂽ�B
(��\�`�F�A�@�R�萭�`�i�����ޗ������@�\))
��Session P�F�}�e���A���E�_�C���N�g�E���C�e�B���O�Z�p�̓W�J�@
The Latest
Achievements and Challenges of the Material Direct Writing (MDW) Technology
�@�{�Z�b�V�����ł́A�]��AD�@��R�[���h�X�v���[�@�ȂǁA�����q�̕��ː����@�ɏœ_�ĂĂ������A���N�́A����琬���@�����A���^�A��R�X�g�������łȂ����i�̑��l����i�T�C�N���̒Z�����ɑΉ��ł���v�E�����Z�p���\�z�ł���V���ȃv���Z�X�@�̔��e�Ƃ��āAMaterial
Direct Wrinting�iMDW�j�Ƃ����L�[���[�h���Ă��A���̂��ƂŁA���\�E�c�_���s�����BMDW�́A���\�̓I�[����17���i�����A��u��1���A���ҍu��1���j�A�|�X�^�[7���̍��v26���ŁA2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B
�@���ҍu���́A�ޗ�����A���ڋ@�\���������\���̍쐻�̎���Ƃ��āA����w�ڍ��Ȋw�������X�}�[�g�v���Z�X�Z���^�[���̋{�{�Ԑ��搶���A�d���g������߂邽�߂̃t���N�^���\�����A�����`�@�ɂ���Č`������Z�p�̌������\�������������B��N���l�AAD�@�֘A�̔��\�������Ȃ��ꂽ���A���e���d�q�Z���~�b�N�X�ȊO�A��J�Q�[�W�ւ̉��p�▀�C��������ȂNj@�B����ւ̉��p�̔��\��A�v���Z�X���̂�����d�͉��s���Ȃǖ�S�I�Ȏ��݂̔��\���݂�ꂽ�B�܂��A�C���N�W�F�b�g�@�֘A�ɂ��Ă��A�V�K�ȃ��I���W�[���������X�����[��MDW�p�]���Q���t�̊J���ȂǍޗ��ʂ̌����A����у��[�U�[���M�Ƃ̑g�ݍ��킹�Ȃǃv���Z�X���x���̃A�v���[�`�ȂǁA�C���N�W�F�b�g�@�̘g���L��MDW�̃R���Z�v�g�ƓK�����悤�Ƃ����������Ȃ��ꂽ�B����̂��V�����̂������A���ׂĂ̔��\�ɐV�K��������A�����[���Z�b�V�����ɂȂ����Ǝv���B
(��\�`�F�A�@���n�@���i�Y�ƋZ�p����������))
��Session Q�F�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A�@Materials Frontier
�@�{�Z�b�V�����ł͉ߋ����N�ɂ��킽���ĕ��L�����@�ޗ��A�L�@�ޗ��A�����ޗ��A�����̍ޗ��A���̍ޗ��A�����̍ޗ��̍ŋ߂̐i���Ɋւ��锭�\���W���Ă����B������A�������j�ŊJ�Â��A����̍ޗ��W�̔��\���������B�ߋ��̂��̃Z�b�V�����ł̓|�X�^�[���\�݂̂��s���Ă������A�O��i2005�N�j����������\�ƃ|�X�^�[���\�̗������s���Ă���B�|�X�^�[���\33���A�������\9���i���ҍu��1�����܂ށj�ł������B���ҍu���ł͕č�Argonne
National Laboratory��J.P. Singh�搶����uResidual Stress Measurements in
Advanced Ceramic Composites by Neutron Diffraction�v�Ƃ�����ڂōu�����Ē������B�u���ł́A�����q��ܖ@�̓����Ɋւ�������̌�A�����p�����Z���~�b�N�X�����ޗ��ic-
ZrO2-m-ZrO2, Al2O3-SiC(whisker), SiC(fiber)-Si3N4�j���̎c�����͑���ւ̉��p�Ƃ��̕��@�̗L������������Ă����������B���̔��\�ł́A�X�e�����X�̔������������Ђ̕ό`�A�����ޗ��̒��Y���ό`�A�_���`�^���i�m�`���[�u�A���C�A�_�����ƗL�@�ޗ��̕����ށA�e�픖���̍쐻�A���ɗp����ޗ��̔��\�Ȃǂł������B
�@�������\���܂߂ď���ܑΏۂ̔��\��29���i�w��5���A�C�m17���A���m5���A���2���j�ł������B12���̐R�����ŐR��������3�ʂ�2���̐l�����_�ƂȂ�A����4���̕��ɏ���܂����^���邱�Ƃ��Ă����B
(��\�`�F�A�@�ɌF�טY�i�_�ސ�H�ȑ�))
�@��17����{MRS�w�p�V���|�W�E���͐����̂����ɏI���ł��܂����B�V���|�W�E����g�D���ꂽ�Z�b�V�����`�F�A�Ɍ��\���グ�܂��B
�`�F��{�@�i����j�A����S��i����j�A����@���i��������j�A�A�c�a�n�i����j�A����_�P�i���Ɍ�����j�A���c�O���iAIST)
�a�F�O�Y�N�O�i�ˈ����l��j�A��c�W�K�i����j�A�R�{�@���i����j�A�r��h��iAIST�j�A���{�r�ǁi������j�A�{��@�́i�ˈ����l��j�A���@���v�i�ˈ����l��)
�b�F��v�ےB��i����j�A�������j�i����j�A�؉������i���H��j�A�ց@���L�i����j�A����J�p�K�i�R�`��)
�c�F��������i�R����j�A���R�����i�R����j�A���ˍW�F�i�R����j�A�R�{�ߕv�i�R����j�A�쑽�p�q�i�R����j�A�}�J�a�j�i�R����)
�d�F�喼�@�ہi�c��j�A�k������i���j�A���c�u�Y�i�k��j�A�Ί_�����iNIMS�j�A��؋v�j�i�Ñ�j
�e�F���{�@�i�i����j�A���������i�}�g��j�A���z�@�h�i�k��j�A�����@���i���j
�f�F���䌒���iNIMS�j�A���c�_�i�i����j�A���X�؉��iJASRI�j�A�|�c���a�i����j�A�����@�~�i���)
�g�F���J�����i���j�A�����a�v�i����j�A�ߌ��T��i���j�A�x�@�@���i����j�A�m���L�T�iNIMS�j�A�͖얾�A�i����j�A���u�i����j�A���R�͎O�i���k��j�A���R�@���i�����j
�h�F�O�Y���q�i�k����[��j�A�L�ꍎ�F�iNIMS�j�A���c�����iAIST�j�A�������l�iNIMS�j�A���c����iAIST�j
�i�F����܂ǂ��i����j�A��ؗ��́i����j�A�V���i�G�i����j�A���q���i������j�A�䓡�@���i���j�A����q�V�i���k��j�A��M�T�i����)
�j�F�ݖ{�����iNIMS�j�A�ҁ@���i�i����j�A�r�R����iAIST�j�A��؉Ö��i�����j�A�n��P���i����H�Z�Z�j�A�����K���iAIST�j�A�����v�K�i�����Z�ȑ�j
�k�F�����@�r�iNIMS�j�A�X�@���V�iNIMS�j�A����q�K�iNIMS�j�A�Гc�N�s�iNIMS�j
�l�F���@��L�i���j�A�y���q���i�Q�n��j�A���،��W�i���C��j�A������F�i���)
�m�F�����q�O�i�X���H�Ƒ��������Z���^�[�j�A�ҏ���Y�i�|���e�N�Z���^�[�Q�n)
�n�F�R�萭�`�iNIMS�j�A���@��k�iNIMS)
�o�F���n�@���iAIST�j�A���ؑ]�v�l�i�Y�����j�A�ߌ��h�́i���H��j�A���c�����iNEC)
�p�F�ɌF�טY�i�_�ސ�H��j�A��ԗ��j�i�_�H��j�A�����@�T�i���C��j�A����[��Y�iNIMS)
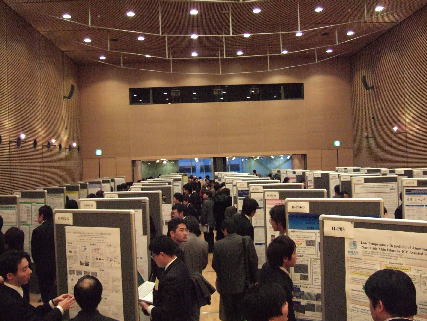 �@�@
�@�@
 �@�@
�@�@
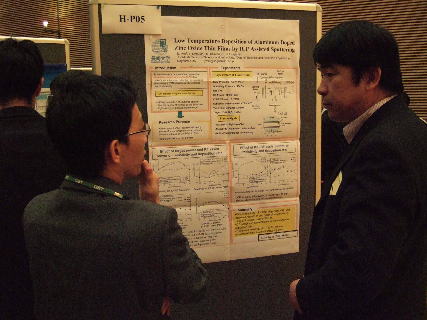 �@�@
�@�@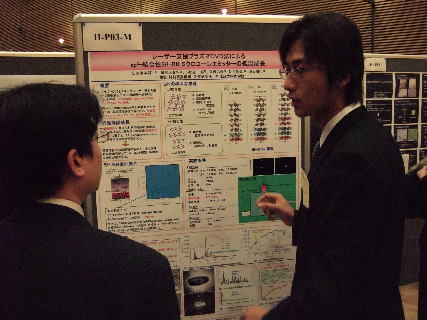
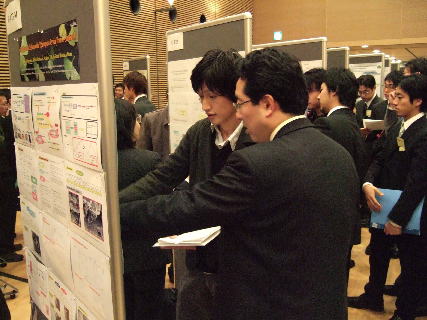 �@�@
�@�@
����18����{MRS�w�p�V���|�W�E��
�@�@��ÁF���{MRS
�@�@�����F2007�N12��7��(��)�`9��(��)
�@�@�ꏊ�F���{��w���H�w���x�͑�Z��
�@�@�ڍׁF�ڂ����ē��͎����B
��IUMRS�W
�@��2007 MRS Spring Meeting
�@�@April 9-13, 2007, San Francisco, CA
�@��2007 E-MRS Spring Meeting
�@�@May 28-June 1, 2007, Congress Center, Strasbourg, France
�@��International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT
2007)
�@ July 1-6, 2007, Singapore
�@��IUMRS-ICAM 2007-10th International Conference on Advanced Materials
�@�@Oct 8-13, 2007, Bangalore, India
�@��2007 MRS Fall Meeting
�@�@November 26-30, 2007, Exhibit: November 27-29, Boston, MA
���V���ē�
�@Trans. of MRS-J, Vol.31, No.4, December����������܂����B
�@�k�F������G�R�}�e���A���\�����a�^���@�\�G�l���M�[�ޗ��\
�@�m�F�����n�����̍ŋ߂̐i��
�@�o�F�G�A���]���f�|�W�V�����\�R�[���h�X�v���[�@�̐V�W�J
�@�p�F�}�e���A���Y�E�t�����e�B�A
�@�ȏ�̃Z�b�V����56��Ƀ��M�����[�y�[�p�[4��A���v60��
�@�ڍז⍇����@mrs-j��sntt.or.jp�܂��͓����H�Ƒ�w ��w�@���H�w������ �ߌ��E�a�c������
�@�@��152-8552 �ڍ���剪�R2-12-1-S7-2
�@�@Tel: 03-5734-2517�@Fax: 03-5734-2514
�@�@mrsjpub��cim.ceram.titech.ac.jp
�����R�V���|�W�E��
�@2007�N9��5��(��)�`8��(�y)�ɓ�����w�����ɂ��Ēr�J�Ȋw�Z�p���c��Â̑�17��r�J���ۉ�c���J�Â���܂��B�e�[�}�́uMaterials
to Save Humankind: The Dream, Creativity, and Working Toward�@its Realization�v�ł��B�{��c�͂܂����{MRS����A��3���œ�����w���_�����A�鋞�Ȋw��w���_�����E���R���j���m�̎P�����L�O����The
Doyama Symposium on Advanced Materials�Ƃ��ĊJ�Â���܂��B
�ڍז⍇����@http://www.iketani2007jks.ynu.ac.jp/
��IUMRS Somiya Award�@2007 Somiya
�@Award�̉������2007�N4��1���ł��B�@�{�܂͓����H�Ƒ�w���_�����E�鋞�Ȋw��w���_�����E�@�{�d�s���m�̍ޗ��Ȋw�ɂ�����Ɛт��������đn�݂��ꂽ�܂ł��B����@�{�܂͊u�N�ő��܂���邱�Ƃ����肳��܂����B�\������2007�N10���C���h�J���i�J�^�B�s�x���K���[���i���o���K���[���j�ŊJ�Â����IUMRS-ICAM-2007��c���ɍs���܂��B
�ڍז⍇����@http://www.iumrs.org
��To the Overseas Members of MRS-J
��Material Research for the Practical Use�cp.1
Dr. Kiyoshi OGATA, Director, R&D Center, Nissin Electric Co., Ltd.
�@It may safely be said that now the technology of the new materials synthesis
in Japan is in the van of the field in the worldwide. A prominent functional
materials and that manufacturing technologies are developing. However,
the production technology in the low cost should be also investigated and
developed to be used for the practical materials.
��The 17th MRS-J Academic Symposium�cp.2
�@Materials Society of Japan organized the 17th academic symposium in December
8-10, 2006, in Ochanomizu, Tokyo. More than 1000 scientists and researchers
from wide range of disciplines attended the Academic Symposium, held at
the Nihon University�fs Ochanomizu Campus. Seventeen symposia with 698
oral and poster presentations highlighted advances in the basic research
and applications of advanced materials.
��Doyama Symposium
�@The 17th IKETANI International Conference on �gDreams, Creation and Realization
of Materials Saving the Humankind�h will be held at the University of Tokyo,
Tokyo, Japan from Wednesday, September 5 through Saturday, September 8,
2007. This Conference is also planned in commemoration of the 80th birthday
of Prof. Masao Doyama and will be supported by the Iketani Science and
Technology Foundation.
��IUMRS Somiya Award
�@The International Union of Materials Research Societies (IUMRS) is seeking
nominations for the 2007 So�Omiya Award, which recognizes research on real
materials conducted by a research team whose members are drawn from at
least two continents.
�@��15�A16�A17��Ɠ��{MRS�V���|�W�E���̌��n�ӔC�҂����������B�V���|�ɂ́A�Z�b�V����B�̃`�F�A�Ƃ��Ă��g���A�{���̓��{MRS�j���[�X�̕ҏW���s�����B�K���Ȏ��ɑ�16�A17��̃V���|�ł́A���������̊w��������܂����B���N�̍P��s���ƂȂ����B����Ȏ��A�V���|�Ŋw������̐�y�ɏo������B�u���܂����撣���Ă���ȁv�Ɨ�܂��ꂽ���A�V���|�ł́u���d���v�ł����ւ���Ă��Ȃ����Ƃ�Ɋ������B�����͂܂�����܂�����������N��ł�����B��18������嗝�H�w���Ŏ��{���邱�Ƃ��قڊm�肵�Ă���B���������̉��f�I��c�ɁA�����҂Ƃ��Ă���ɐϋɓI�ɎQ�����邱�Ƃ𐾂����B(��c)